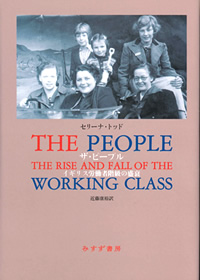
2016.08.29
等身大の労働者群像が織りなす現代史。「訳者あとがき」より抜粋掲載
セリーナ・トッド『ザ・ピープル――イギリス労働者階級の盛衰』 近藤康裕訳
富田玲子『小さな建築』[増補新版]
2016.08.26
東大建築学科はじめての女子学生として丹下健三に師事し、吉阪隆正U研究室を経て、1971年に樋口裕康、大竹康市、重村力と「象設計集団」を創設した富田玲子は、巨大建築とは一線を画したもうひとつの潮流を創ってきた。やわらかい語り口で建築の常識を次々とひっくり返す「小さな建築」とは?
それは、たんに小さい建物というのではなくて、感覚がのびのびと働く空間ではないだろうか。たとえば埼玉県の宮代町立笠原小学校の廊下のコンクリートの柱には、いろいろな言葉が彫ってある。「いぬもあるけばぼうにあたる」「わらうかどにはふくきたる」「みからでたさび」「はらぺこだ」など。校長室の前は「としよりのひやみず」。
この半屋外の廊下は、手すりがそろばんの玉だったり、子どもサイズの「ロイヤルボックス」から校庭を見下ろすことができたりする。それは小学校という建物の「常識」ではないかもしれないが、子どもを主役に考えると、とても自然な形ではないだろうか。
随所に仕掛けられた遊び心ある仕掛けは、居心地よいだけではなく、感覚を刺激する。それは、日々成長している子どもたちが過ごす場所として、理に適っている気がする。校内の動線も、玄関から廊下、教室へと一つの流れに沿わせるものではなく、子どもたちがてんでばらばらに校庭に飛び出していって、また戻ってくるように作られている。
だから、小さな建築とは、自分の体とその動きに合った空間のことではないかと思う。そして体は幼児期から老年期まで、さまざまな変化を遂げる。このたび増補した「建築オノマトペ」に象徴的な言葉がある。赤ちゃんの「だっこひも」が建築の原点だというのだ。
身体に自然に寄り添う居心地よさがありながら、あっと驚かせる遊びもある。建築はもっと自由で楽しいものであっていい。
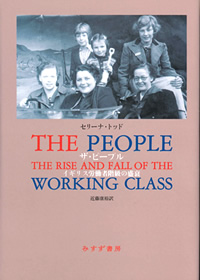
2016.08.29
セリーナ・トッド『ザ・ピープル――イギリス労働者階級の盛衰』 近藤康裕訳
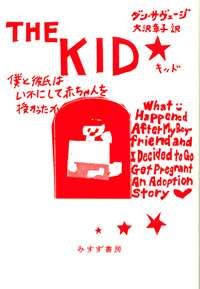
2016.08.16
ダン・サヴェージ『キッド――僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか』 大沢章子訳