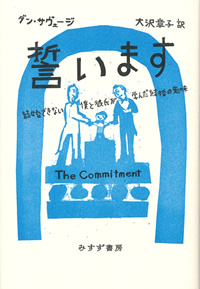
2017.04.20
同性カップルだからこそ純粋に考える「結婚とは…」 『キッド』続編
ダン・サヴェージ『誓います――結婚できない僕と彼氏が学んだ結婚の意味』 大沢章子訳
高橋睦郎『詩人が読む古典ギリシア――和訓欧心』
2017.04.11
「人間が神神のことを語るのは、なぜ自分があり、自分を取り囲む世界があるのかを知りたいから、知って自分という存在の拠って立つ不安を去りたいからではないだろうか。」(本書21ページ)
存在の不安ゆえに人間は自分を超えるものを思うのだという説に、とくだんの新味があるわけではない。にもかかわらず、詩人のこの言葉にひきつけられるのは、神々と踊り字をもちいずに「神神」と書かれた複数形が、砂漠の一神教ではない古代ギリシアの神話世界をくっきりと示しているからだろう。
松岡正剛は、日本文化を解読するうえでギリシアをどう見るかは「鏡像の過程」になっていたという。そして、その探究の過程で導きの糸となったのは、詩人・西脇順三郎による「ギリシア精神の表象の仕方」と並んで、晩年の呉茂一を囲んでつくられた季刊誌『饗宴』による日本語の実験だった。呉茂一を囲んだのは、鷲巣繁男、多田智満子、高橋睦郎という三人の詩人たち。松岡氏は、こう書いている。
「なにしろ高橋さんは22歳のときの処女詩集がミノタウロス幻想をめぐる『ミノ あたしの雄牛』であり、多田さんには思索詩ともいうべき『オデュッセイアあるいは不在について』の連作がある。ぼくはこれらの詩作に助けられ、そうか、なるほど、日本語による思考にもホメーロスの六脚韻の秘密を嗅ぐことができる余地と隙間が穿たれているのか、という展望をもったものだった。」
創立まもない1947年に、みすず書房は、呉茂一『花冠 ギリシヤ・ラテン訳詩集』を刊行した。中学生だった高橋睦郎はその本を手にして、自然のうちに人間との調和をみるギリシアの心に触れた。それから30年、近代日本に育まれた西洋古典文学研究の成果が、出版による大衆化という機会を得て多くの読者にいきわたった頂点の時期が70年代であったともいえる。そうした精神の共鳴を敏感に高度に表現したのは、ほかでもない詩人たちだった。季刊誌『饗宴』も、晩年の西脇による『学鐙』連載のギリシア語論も、その時期のことである。
せっかく広まった古典の素養なのに、その後の世代は先人の残したものを十全に享受しているだろうか。時空をへだてた文化世界と、文庫本一冊でつながることができるのである。日本語で読みながら原語の響きを感じようとすれば、古代ギリシア語によるホメーロス詩の朗読をネットで聞けるらしい。「詩のふるさと、知のみなもと」たる古典ギリシアをめぐる地図として本書『詩人が読む古典ギリシア』をぜひ活用していただきたい。
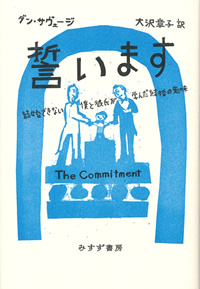
2017.04.20
ダン・サヴェージ『誓います――結婚できない僕と彼氏が学んだ結婚の意味』 大沢章子訳

2017.04.11
[12日刊][第2回配本・全11巻]