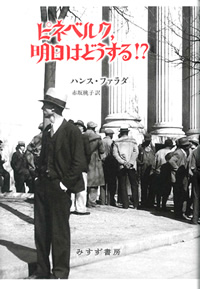
2017.06.27
《ヒトラーへの285枚の葉書》の原作者、ファラダの手になる超ロングセラー
ハンス・ファラダ『ピネベルク、明日はどうする!?』 赤坂桃子訳
桜井英治『交換・権力・文化――ひとつの日本中世社会論』
2017.06.09
足利義満や北山文化などで知られる室町時代は、実にわかりにくい時代である。かつて私は中世政治史の研究をこの時代から始めようと考え、取り組んだことがあったが、うまくゆかず、時代を遡って院政時代の研究から進めることにした。
その全くのお手上げだった室町時代の研究に、真っ向から取り組んで大きな成果をあげたのが桜井英治氏であり、その第一論文集が出版されたのは今から二十年前の1995年である。
書名の『日本中世の経済構造』(岩波書店刊)からしても正面から切り込んだ内容であり、その影響力は、以後、中世史の研究者の多くの関心を室町・戦国時代に引き寄せたことを見ても明らかである。
室町時代を政治史からではなく、社会・経済・文化の動きを丹念に見てゆけば、たいへん魅力的で、不思議な時代だったことを明らかにされたばかりか、著者はそこからさらに政治史をも視野に入れて『室町人の精神』(講談社、日本の歴史12)を、流通経済への関心を贈与にかかわらせて『贈与の歴史学』(中公新書)を著わし、中世史研究者にとどまらず広く大きな影響を及ぼしてきた。
そしてここに第二論文集『交換・権力・文化』を上梓するに至ったのであり、贈与と貨幣の問題を基軸にした9つの論文からなる。待望の論文集である。
序論は本書の構成と視角を提示している。これまで贈与経済史と貨幣史の研究を併行して進め、さらにその2つを架橋する考察を行ってきたことから、それらの論考をもって書をなしたとする。著者の考えている全体像がここから見えてくる。
しかしそれにとどまらずに、著者が今、考えるところの「若干の理論的問題」を提出していて、実に刺激的な内容である。ただこの「若干の理論的問題」にここで触れてしまうと、それだけで終わってしまうので、9本の論考が何を明らかにしてきたのかを示しておこう。
第2章の「折紙銭と15世紀の贈与経済」、第3章の「御物の経済」、第8章の「借書の流通」などは、タイトルから何を論じようとするのか一見してはわかりにくい。だが折紙銭(おりがみせん)や御物(ごもつ)、借書(しゃくしょ)などの動きや働きを探ることで、この時代の流通経済のメカニズムを明らかにする手がかりをつかんだ。
たとえば贈答に際して作成される目録である折紙は、受贈者に渡した後に現物を渡す贈答儀礼が行われており、今にもつながる習慣だが、この時代には現物をなかなか渡さないことがあって、室町幕府は折紙方という機構を通じて催促していた。
私もかつて注目したことがあったが、そこからさらなる追究をするまでには至らなかった。しかし著者はその折紙が第三者に譲渡されたり、相互に贈りあって折紙どうしで相殺したりする事実を発掘し、物の動かない贈与経済のメカニズムを明らかにしたのである。
これに対し、物の動く経済を扱ったのが「御物」の分析で、足利義政に贈られた東山御物がいかに幕府財政を支えたのかを明らかにし、さらに借書については、それが譲渡され、流通する信用経済の在り方を考えてゆく、といった具合である。
第4章の「宴会と権力」、第5章の「銭貨のダイナミズム」、第7章「精銭終末期の経済生活」などは、タイトルを見ただけでも魅力的だが、その分析と内容も秀逸である。宴会については、まず室町時代の宴会の特徴を明らかにした上で、晴(ハレ)の宴会と褻(ケ)の宴会とに分類し、それぞれの費用負担や手土産・引出物を考察し、宴会という場から生まれる権力とその性格を論じる。
銭貨に関する貨幣史の研究は、13世紀後半から17世紀にいたる銭貨の流通の実態を見極めようとしたもので、そこにおける破綻と規則性のサイクルをダイナミズムとして把握する。日本の中世ではどうして銭貨の鋳造が行われなかったのか、戦国時代になって撰銭令がどうして何度も出され、時に米が銭に代わって納められたのか、またなぜ精銭が行われなくなっていったのかなど、これまでいくつか回答が出されてきたが、この長年の謎に迫る卓抜な回答を提出している。
第1章の「中世の贈与について」、第6章の「中世における物価の特性と消費者行動」、終章の「中世における債権の性質をめぐって」などは、いずれもタイトルに中世とあるように、他の社会とは違った日本の中世社会に特有な贈与、価格メカニズム、債権について考えている。
こうして明らかにしてきた日本の中世社会の在り方を踏まえ、そこから飛び出して理論的に探ったのが序論の「若干の理論的問題」の節である。ここでは社会学や文化人類学、あるいは思想家の理論、果ては脳科学の成果にまで踏み込んで考察を加えてゆく。
まだ試論の段階ということもあって、アナロジーを多用しているのがやや気がかりである。贈与と売買の違いについて、有袋類と真獣類の違い、不平等を感じることについて、脳の大脳皮質と扁桃体の関わりなど。しかしこうした見方が起爆剤になって、多くの議論がこれから生まれてくることを期待したい。
copyright Gomi Fumihiko 2017
(著者のご同意を得て転載しています)
贈与・貨幣・信用を緯糸とし、交換・権力・文化の経糸がそれらを編んで進む。シャープに、周到に、大胆に論じられる日本中世社会の特質と変容。
本書のあとがきはごく手短で、余韻を残す文章ですが、著者の研究の出発点からの歩みについては第一論文集の『日本中世の経済思想』(岩波書店、1996年)あとがきで、謝辞とともに詳しく語られています。また、現代を生きる私たちにとって「異文化」であるところの日本中世史の魅力と、現在の研究の地平とをまことにバランスよく俯瞰する著者の文章「中世史への招待」は、『岩波講座 日本歴史 6 中世 1』(岩波書店、2013年)の巻頭に収められています。
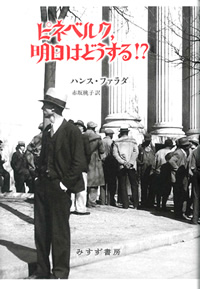
2017.06.27
ハンス・ファラダ『ピネベルク、明日はどうする!?』 赤坂桃子訳

2017.05.29
『トレブリンカの地獄 ワシーリー・グロスマン前期作品集』 赤尾光春・中村唯史訳