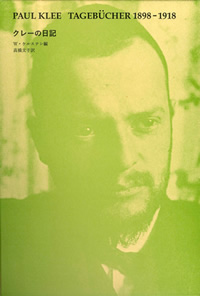
2018.05.11
『クレーの日記』ついに念願の復刊。軽快な造本で
ヴォルフガング・ケルステン編 高橋文子訳
木庭顕『憲法9条へのカタバシス』
2018.04.25
このすがすがしさはどこからくるのだろう。結託や徒党や迎合主義をどこまでも排して、徹頭徹尾、個人の自由を基点にものを考える。だからこのように澄んで明るいのではないか。
憲法9条2項の根を下ろすあたりへと、タイムトンネルをくぐって降りていく(=カタバシス*)と、やはり政治の基礎付けを探究する著者の直近の先行者に、三谷太一郎がおり(本書2–4)、三谷も論じた夏目漱石と森鷗外がおり(本書5、6)、漱石も鷗外も、日本の近代市民社会に最も根底的な欠陥のあることを鋭く突いた。しかも二人のあいだに対論が成り立っていた可能性がある。さらにホッブズがいる(本書7)。ホッブズは抑止力理論の守護神であるどころか、彼の「自然状態」=永続的戦争状態は、それと正反対の結論を導くためにホッブズが組み上げた見事なロジックの一部分であった。ホッブズは古代ギリシャの歴史家トゥーキュディデースが描く戦争をその最深部で理解し、そこから間髪入れずに政治システムが立ち上がる平和構築の論理を考え抜いた哲学者なのである。
構造がくっきり捉えられると、主題の9条2項論はきわめて明晰になる。
現代の日本において文学(例えば歴史学)に携わろうとすれば、当然、憲法9条が袋だたきに遭っている、否、かさにかかった連中に罵倒されている、その場面を見過ごすわけにはいかない。政治は一度も成立しない、徒党は一度も解体されない、としても、貴重な橋頭堡をみすみす見殺しにするわけには行かない(「序」)
1項は、「如何なる理由であれ(「国際紛争を解決する手段としては」)伝統的な国際法が認めてきた戦争(「国権の発動たる戦争」)を、自衛権の行使を含め(「武力による威嚇又は武力の行使」)認めない」と言っているのであり、占有原則への回帰を表明している。2項は、その実質を担保するために(「前項の目的を達するため」)占有原則に一見収まる占有内実力のうち全面的な占有内軍事化(「陸海空軍その他の戦力の保持」)をも禁ずる、と言っているのであり(1 「日本国憲法9条2項前段に関するロマニストの小さな問題提起」)
直ちに導かれる帰結として、「自衛のためには有効」というので構築される抑止力、その種の防衛体制の整備が禁じられることになるのは明白である。(攻撃・侵害を未然に防ぐためとして正当化され易い)報復攻撃を可能とする体制も同様である。抑止力は相手に対する脅威のことであるから、その最大のものたる核武装は(火の玉型軍事化そのものとして)ipso facto に(行使の目的が無くとも)禁じられる(同)
「集団的自衛権」を概念し行使することが何故9条2項違反かもはっきりする(同)
局地的な撃退力やミサイル防衛網などが許されることは明らかだとしても、それらは反撃にも転用しうるかもしれない。むしろ、政治システムに対する軍事組織の徹底した透明性、軍事組織と政治システムないし市民社会との間の厳格な分節的関係、この二つを要請する方面に2項の規定は大きな意味を有するかもしれない。また、例えば文民統制は政軍関係分節の要であるが、指揮権が文民に属するだけでは足りず、頂点の合議体において文民以外の者とその判断が混入することがあってはならない、という帰結が導かれる(同)
政治システム存立にとって不可欠の原則を宣明したこれらの規定は憲法に不可欠であり、削除することは政治システムの破壊に等しいから、改正は違法である(同)
あっ、わかりました。縛りも縛りの縛りも桃太郎も「皆のもの」ではなく「誰のものでもない」でなければいけません。憲法ばかりか憲法改正自体「皆のもの」ではなく「誰のものでもない」ことでなければなりません。ゴンザエモンどのは今回ここも「皆のもの」に変え、そしてそれを橋頭堡としてポンポコ山を自分の徒党で占めようとしている(2 「法学再入門:秘密の扉 ぜんべえドンとオハナぼう、番外篇」)
私の個人的な経験を元にすれば、やがて9条を暴力的に襲うだろうと思われた動きが孵化するのは1980年代後半、バブル期である。以後事態は真っ直ぐに沈んでいった。まず闇の構造が肥大した。その構造の破裂が大量に平岡を生み出した。「改革」は再吸収のサインであった。ゆすりゆすられのコンフォルミスムはスケールの大きな観念上の軍事化を周囲に発散した。何よりも労働現場で暴力的かつ犠牲強要型の過激なコンフォルミスムが吹き荒れた。信用システムはこの劇症のゆすりゆすられ構造に質を取られたようにしばられ、中毒ないし依存症に陥った。根拠のない信用を発生させてジャブジャブとつぎ込みトランス状態のコンフォルミスムに油を注いでいくしかないのである(8 「日本国憲法9条改正の歴史的意味」)
目立つ非論理は、何かを改廃するに際して改廃するものが何か知らないし知ろうとしないという点である。私はこの点において法律家は高いツケを払っているのではないかと危惧している。反撃の側がなかなかこの点を指摘しない。9条をなくすとどうなるかへ議論を直行させるから情緒的に映る(同)
手続未整備はたくさん議論すべきであり、議論は改正を促進するなどと怖れていてはならない。千一夜どころか10年くらいかければよい(同)
序と6は、本書のために書き下ろされた。5の漱石『それから』論は、かつて『現代日本法へのカタバシス』(羽鳥書店、2011年)に書き下ろしとして収められた論考だが、このたび大幅な改訂がほどこされている。6の鷗外論を執筆の途上、「『それから』についてなお残っていた疑問が解けた」からだとあとがきに記されている。
なお、『現代日本法へのカタバシス』は、新版をみすず書房より刊行。民事法に焦点を絞り込んだ一冊として甦る。

[新版]
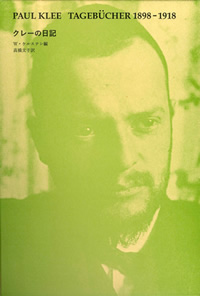
2018.05.11
ヴォルフガング・ケルステン編 高橋文子訳
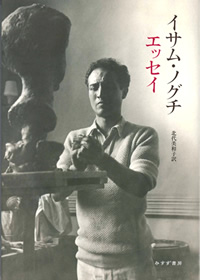
2018.04.16
『イサム・ノグチ エッセイ』北代美和子訳