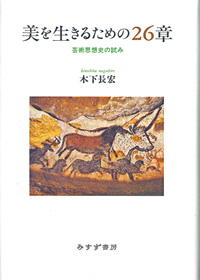トピックス
木下長宏『美を生きるための26章』
芸術思想史の試み
「ラスコーの洞窟と敦煌莫高窟の両方を訪ねた美術史の研究者はボクくらいしかいないかもしれない──とボクはときどき、みんなの前で自慢する。
この両方の洞窟を訪ねて、ボクは〈美〉を経験するとはどういうことか、〈美〉の〈歴史〉を考えるということはどういうことかを、はじめて根源的に考え直す機会を得られた。それまで、どのラスコーや敦煌の本からも学ばなかった〈感覚〉が動き出し、予期しなかった〈発見〉があった。大乗寺を訪ねたときも、既刊の解説書や美術史に書いていない経験をした」
これは、本書の著者木下長宏さんが、誰でも参加できる連続講座「土曜の午後のABC」を開講するにあたって、趣旨を述べた「はじめに」からの言葉です。本書は、この講座のために毎回用意された講義ノートを元に、全編をあらたに書き下ろしたものです。
「土曜の午後のABC」http://kinoshitan.com/
さてそれでは、洞窟の中で木下さんが経験した〈美〉とは、いかなるものだったのでしょうか。本書の「ラスコー」の章には、こう書かれています。
「ラスコーの壁画に描かれているのは、動物の外観や姿、形ではない、ラスコーの人たちは動物の姿を写そうとしたのではない、その生命に触れ合おうとして描いたのだ――」
「どうやら、ラスコーの人たち原初の人類は、動物=獣に対して、現代のわれわれとは全く異なった共感というか感情をもっていたようです。共感と、同時に畏怖の念とでも言うべきもの。(…)力も嗅覚も聴覚も視力も、獲物や食べ物を摂る能力も、走る速さも、なにをとっても自分より秀でた存在。のちの〈聖なる〉という概念は、ラスコーの人びと、原初の人類にとっては、〈動物〉という存在のなかに宿っていたのでしょう」
こうした共感や畏怖は、人類がはるか長い年月をかけて失ってきた感情ですが、それでも現代を生きるわたしたちの内にも、まだかすかに残存している。それが一瞬の閃きのようにして蘇る――〈美〉の経験とはそういうものでしょうか。
「〈美〉や〈芸術〉の営みは、いつも、人間の〈弱さ〉や〈忘れ去ったもの〉の美しさ、かけがえのなさを思い起させてくれる。人間のそれぞれの可能性というものは、そんな〈弱さ〉を大切にするところから見つけ育てることができるのだ」
これも、先に引いた「はじめに」からの言葉です。そんな〈弱さ〉を、木下さんはゴッホの絵画に見いだします。あの「炎の画家」ゴッホ、にです。意外に思われませんか。たとえば「嵐の来そうな空の麦畑」(ゴッホが付けたタイトルではない)。
「ヴィンセントがこの絵に描き出そうとしているのは、静かな夏の終わりのある日の畑の風景、人もいない、烏もいない、風が静かにそよいでいる、そんな静寂の光景ではないでしょうか。(…)そんな自然の姿、〈自然〉のなかの〈弱さ〉へのまなざしがみつけた光景です」
〈弱さ〉に否定的な意味を与えて上から救済するのではなく、まさしくわたしたち人間の生存の条件としての〈弱さ〉を、そっと掌で掬い取ること。美と芸術をめぐって、おおくの示唆と発見にみちた本が、この『美を生きるための26章』です。
さて、本書のほかにもみすず書房では、美と芸術をめぐって意義ぶかい既刊書を取りそろえております。たとえば――
狭い意味での芸術書や美学の本の枠には収まりきらない思索的な書物を、ほんの三点あげてみました。ぜひあれこれとお手にとってみてください。とりわけ『美を生きるための26章』の関連書といえば次のように、ジャンルをかるがると越えていくでしょう。
- フーコー『臨床医学の誕生』(神谷美恵子訳)はこちら
- 『ジャコメッティ エクリ』(矢内原・宇佐見・吉田訳)はこちら
- 『北一輝著作集』全3巻はこちら
- 『ファン・ゴッホの手紙』(二見史郎編訳・圀府寺司訳)はこちら
- 『ヴェイユの言葉』(冨原眞弓編訳)《大人の本棚》はこちら