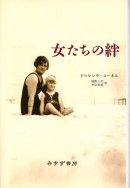トピックス
岡野八代『フェミニズムの政治学』
ケアの倫理をグローバル社会へ
フェミニズムと政治学は遠いものと思われていた。フェミニズムは政治学の想定する「人間」とは男性のことだと批判してきたし、政治学は女性を政治の領域から排除し、あるいは承認したうえで包摂してきた。
フェミニズムによる政治学は可能だろうか。既存の社会の批判を超えて、フェミニズムは新たな社会を構想することができるだろうか。本書は、現代のフェミニズム理論に「リベラリズムとの対決」という一本の軸を通し、新たな政治学をうちたてる。
第一部では、政治学の根本を問う。まず、歴代の政治思想の議論を紹介し、男性を公的領域、女性を私的領域に割り振る公私二元論が、政治思想を貫いていることを指摘する。この公私二元論が「性的役割分担」の大元なのだが、ここでは性役割の解消がゴールではない。本書ではさらに、公私二元論がリベラリズムの根底にあることを洞察し、それが隠蔽するものを明らかにする。つまり、ひとは「自立した個」ではなく、たがいに依存して生きるという事実だ。
第二部では、ケアの倫理を社会に開く。依存する者たちの共同体=ケアは、リベラリズムの限界がもっとも鋭く現れる場である。自律した主体の能力とされてきた「責任」や「自由」は、ケアという地点から見るならば、他者の呼びかけに無責任である限りでの責任であり、応答しなくてもよい自由に他ならない。ケアが愛という名の下に女性に背負わされてきたというフェミニズムの批判に応えた上で、ケアや家族を社会にひらく道を発見する。
第三部では、強い主体ではなく、ヴァルネラブルな存在からはじまる政治が構想される。ひとは傷つき依存して生きるという「人間の条件」を基礎にした政治である。女イコール平和という図式をめぐるフェミニズムの論争をふまえ、グローバルな責任とは何かを探っていく。もっとも私的とされるケアの倫理が、国際平和への道を切り開くのだ。
「個人的なことは政治的なこと」というフェミニズムの発見が、これほど見事に政治学に練り上げられたことはない。政治を根底で支えている論理をクリアにするばかりでなく、社会を生きるための力が湧いてくる本だ。フェミニズム理論の到達点であり、決定的な出発点。
- ドゥルシラ・コーネル『女たちの絆』岡野八代・牟田和恵訳はこちら
- ハンナ・アーレント『過去と未来の間』引田隆也・齋藤純一訳はこちら
- 矢野久美子『ハンナ・アーレント、あるいは政治的思考の場所』はこちら
- E・ヤング=ブルーエル『なぜアーレントが重要なのか』矢野久美子訳はこちら
- アイザィア・バーリン『自由論』小川・小池・福田・生松訳はこちら
- ロールズ他『人権について――オックスフォード・アムネスティ・レクチャーズ』中島吉弘・松田まゆみ訳はこちら
- ジャック・デリダ『ならず者たち』鵜飼哲・高橋哲哉訳はこちら
- ジャック・デリダ『友愛のポリティックス』 1 鵜飼・大西・松葉訳はこちら
- ジャック・デリダ『友愛のポリティックス』 2 鵜飼・大西・松葉訳はこちら
- トニー・ジャット『荒廃する世界のなかで――これからの「社会民主主義」を語ろう』森本醇訳はこちら