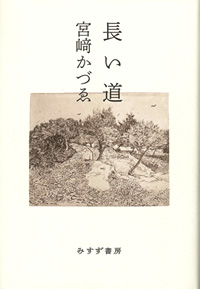トピックス
宮﨑かづゑ『長い道』
『長い道』著者の宮﨑かづゑさんは1938年、10歳で国立ハンセン病療養所・長島愛生園に入園。以来、70年余を島で暮らしてこられた。重い後遺症を持ちながら、料理や裁縫を楽しみ、読書を友として静かに暮らしてきた方が80歳を越える頃から文章を書き始めた。ここでは本書『長い道』が世に出るまでのいきさつをご紹介したい。
宮﨑かづゑさんに初めてお会いしたのは、2010年、ハンセン病の国立療養所・長島愛生園でのことである。故・近藤宏一さん(愛生園で盲人のハーモニカ楽団「青い鳥楽団」をつくった方。神谷美恵子『生きがいについて』にも登場する)の遺著『闇を光に――ハンセン病を生きて』の刊行準備のため『愛生』編集部にお邪魔していたときだった。
宮﨑さんの文章は『愛生』で時折目にしていて、食べ物の表現がうまい方だなあという印象があった。『長い道』にも収録した「愛生園の片隅で」(『愛生』2009年9・10月号)に登場する「塩鮭と季節野菜のスープ」は、読んだとたんに無性に食べたくなり、スーパーに塩鮭を買いに走ったのをおぼえている。でもそのときはそれきりのことで、宮崎さんの本をつくることになるとは思ってもみなかった。
お会いしたとき、親友の看取りの記録をまとめた小冊子「あの温かさがあったから生きてこれたんだよ」(本書にも収録)を頂いた。この中に普通の食事がとれなくなった親友のために毎日作り続けたスープの話がちらっと出てくる。手記に詳しい記述はないが、手羽先でだしをとり、根菜をふんだんに使ったポタージュだったそうだ。
湯気が漂ってくるような話ぶりは宮﨑さんの文章に通じるところがあり、「美味しそうだなあ」と思っていると、宮﨑さんがふっと「いま思い出したけど、辰巳芳子さんのテレビ番組を見ておぼえた作り方だった」とおっしゃったのである。ずっと忘れていたが、話をしているうちにひょいと記憶が甦ったそうだ。
じゃあ、せっかくだからこの「あの温かさがあったから生きてこれたんだよ」を辰巳先生にお届けしましょうよと軽い気持ちで思いついた。宮﨑さんは「そんな畏れ多いこと」とためらっておられた。詳細は省くが結果として、他社の編集者を通してお届けした宮﨑さんの本と手紙に、深く心を寄せてくださった辰巳芳子さんが、本書『長い道』刊行の背中を押してくださったことになる。
辰巳さんは2010年秋、長島に宮﨑さんを訪ねた。二人の初めての出会いの場面は、辰巳さんのドキュメンタリー映画『天のしずく――辰巳芳子“いのちのスープ”』(監督・河邑厚徳、2012年11月劇場公開予定)で紹介される。
昨年秋には、宮﨑さん夫妻が鎌倉の辰巳邸を訪れた。辰巳さんとかづゑさんは、違う場所で生きてきた二人なのに不思議なほど共有するものが多い。二人の対話はそのことを改めて感じたひとときだった。(本書巻末付録に二人の対談「生きなければわからないこと」を収録)
『長い道』には、宮﨑さんが『愛生』に書いた文章と、今回新たに語り下ろした「島の七十年」を収録した。「島の七十年」の聞き手をつとめてくださったのは、辰巳芳子さんと旧知の伊藤幸史神父である。2011年夏、延べ六日間のインタビューは、虚心に人の話を聞くとはどういうことかの見本のようなものだった。伊藤神父の問いかけに、宮崎さんの記憶の糸がするするとたぐりよせられるのを目の当たりにした。
宮﨑さんは「らい患者を自分の考える枠の中に入れて、それに当てはまらない答えは気に入らない」(「島の七十年」より)メディア関係者に強い不信感を持っておられる。なまなかな聞き手では決して引き出せなかった言葉が本書には溢れている。「島の七十年」は、伊藤神父というまたとない聞き手を得て完成したものである。
先述したように、宮﨑さんは80歳を越えて綴り、語りはじめた。何かに突き動かされるように、書かずにはいられない気持ちになったのだという。
本書の企画が立ちあがって一年半、宮﨑さんとのお付き合いを通して確信したことがある。宮﨑さんは、ひと言たりとも自己表現のために、自分のために書き、語っているのではない、ということだ。
ご自身では全く意識されていないが、本書『長い道』は、宮﨑さんが生涯の天地とする長島で共に生き、黙々と働き、声を発することなく逝った療友、医療者、職員の皆さんに捧げる「鎮魂の譜」であると私は思う。
(編集担当 宮脇眞子)
- 神谷美恵子『生きがいについて』はこちら
- 神谷美恵子『人間をみつめて』はこちら
- 神谷美恵子『こころの旅』はこちら
- 神谷美恵子コレクション[全5巻]はこちら
- 『神谷美恵子の世界』はこちら
- ヴィクトリア・ヒスロップ『封印の島』上 中村妙子訳はこちら
- ヴィクトリア・ヒスロップ『封印の島』下 中村妙子訳はこちら
- 斉藤道雄『悩む力――べてるの家の人びと』はこちら
- 斉藤道雄『治りませんように――べてるの家のいま』はこちら