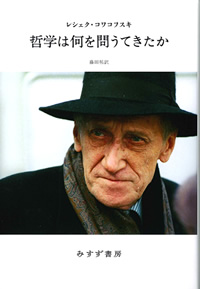
2014.01.24
レシェク・コワコフスキ『哲学は何を問うてきたか』
藤田祐訳
溝口健二映画を聴く
2014.01.24
映画の音響を理論化する作業が本格化したのは、映画が生まれて実に90年もの歳月を経た1980年代の欧米においてであった。これは明らかに、映像ないし映画の物語(ナラティヴ)に関する研究に比して著しく遅い。ビクトル・エリセのように「映像の要素と音の要素に同じくらいの重要性を感じている」(梅本洋一1986)映画作家というものがどのくらい存在するのかは分からないが、一般に映画を鑑賞するすべての人々は、映画とは何よりもまず「動く写真」motion pictureのことであると信じて疑うことができない。音響はその付随物であることを免れることはできない。
(中略)
80年代欧米における映画音響研究の勃興は、音楽学の領域で見られた「録音テクノロジー」への関心の高まりとある程度連動している。また同時的に、映画の「ストーリー」(ないし登場人物の「内面」)中心型分析から離れた、映画諸要素のテクスチャーを相互的に精査するテクスト分析への方法が、映画の音響研究においても模索されるようになった。ただし、音響を映画の「テクスチャー」として理論化しようとする機運が高まりをみせた時期が、映画史の比較的初期の段階で一度だけ起こっていることを忘れてはならない。それが1920年代後半から30年代にかけての時期である。その要因はもちろん、映画の「トーキー化」という巨大な地殻変動であった。しかし、トーキーの技術的進展および音響に関する実用的な方法論が一定の落ち着きを見せて以降(およそ1930年代後半以降)は、映画の音響は議論の俎上に載せられることがなくなっていった。爾来80年代に至るまで、少なくとも言説的レベルにおいて、映画の音は不当な位置に甘んじることになる。
映画の音楽が議論の対象になりにくかったのはなぜだろうか。考えられる理由を列挙してみよう。
(1) 映画学者が音楽に疎かった。あるいは、音楽理論を知らない限り映画の音楽は語れないと考えられてきた。
(2) 音楽学者が映画に疎かった。あるいは、映画の音楽は「純音楽」に比べて「芸術性」の点で劣るものと見なされ、蔑視の対象であり続けた。
(3) 映画の音楽をめぐる言説が、作曲家本人の発言によって形成される傾向にあったため、実用性には長けていても批評性を欠いていた。
(4) 上記(3)の傾向と連動して、映画の音楽をめぐる言説においては「作者の死」(ロラン・バルト1990)が起こらず、作品=テクストを作家へ還元する素朴な作家還元主義が残存した。
本論の目的は、音楽を含む映画の音響を、映画作品を構成する一要素として捉えたうえで、その映像ないし物語に対して有する効果を分析することにある。この分野の研究は、先述の通り欧米においては主に80年代以降の議論の蓄積があるが、わが国においてはいまだその緒に就いたばかりというのが現状である。本論は必ずしも、映画なるメディアが視覚主体の芸術であることに異を唱えるものではないが、「視覚偏重」へと傾いていた従来の映画言説を見直すことも我々の大きな目的の一つである。
copyright Nagato Yohei 2014
(執筆者のご同意を得て抜粋掲載しています)


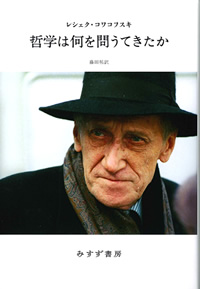
2014.01.24
藤田祐訳

2014.01.24