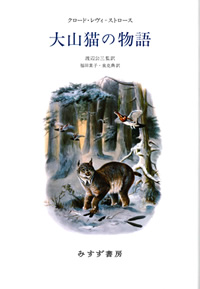
2016.03.11
ライフワーク『神話論理』に連なる「小神話論理」終結の巻
C・レヴィ=ストロース『大山猫の物語』 渡辺公三監訳 福田素子・泉克典訳
ウィリアムズ『想像力の時制 文化研究 II』 川端康雄編訳
2016.03.11
「文化のような浸透性のあるヘゲモニー的システムの耐久力と持続性とをよりよく理解するためには、このシステム内部の統制力が、ただ抑止的なだけではなく生産的でもあるということを認識しなければならないのである。そしてこの考え方こそ、いうまでもなくグラムシが、そしてフーコーとレイモンド・ウィリアムズが、それぞれの方法でもって説明しようと努力してきたものなのである」
(E・W・サイード『オリエンタリズム』上、板垣雄三・杉田英明監修、今沢紀子訳、平凡社ライブラリー)
本書『想像力の時制』はイギリス20世紀後半の著述家レイモンド・ウィリアムズによる「文化」をめぐる一連の著作から独自編集した「文化研究」(全2巻)の第II巻にあたる。
ウィリアムズが関心をもって扱った問題領域は多岐にわたり、とりわけ後期にはその(多様化の)度合いが高い。「文学批評家」「社会学者」「政治理論家」「文化研究者」「演劇学教授」「メディア評論家」といった肩書は、既存の学問分野を越境したウィリアムズの仕事の全容を部分的に示すものでしかない。これら多方面の分野にまたがる論考を通して、ウィリアムズの多面性が確認できるであろうが、同時に、それらを貫く――また著作以外の他の活動にもつながる――彼の思想の筋道が見えてくることが期待できる。むしろそうした「越境者」としてのウィリアムズを包括するためには、端的に「ライター」と形容してしまうほうが手っ取り早いのかもしれない。(…)
イーグルトンは「ウィリアムズがもっとも尊重しなかった境界は、伝統的な各学問領域間のそれであった」と冗談めかして語っている(「レイモンド・ウィリアムズの死」関口正司訳、「みすず」1989年1月号)。1981年の論考「英文学研究の危機」でウィリアムズは人文学研究のパラダイム変換を迫られている状況を分析しつつ、人文学の「既存の分野を大規模に再編して新しい意味をもつ共同的な編成につくりなおさなくていいのか」と一種の修辞疑問を読者にぶつけている。
これはサッチャー政権の三年目にあたる時期の発言であるが、考えてみるとウィリアムズの晩年の仕事はサッチャリズムが跋扈した状況――労働組合と福祉制度の土台の破壊を図り、規制緩和によって(第一期の)新自由主義を推し進めた、「労働者階級への悪意をむき出しにした言語道断の政権」のもと――でなされたのだった。「社会などというものはない」という揚言に対して、あくまで「社会のなかで書くこと」の意味を問い、かつそれを実践したのである。ウィリアムズが没した翌年の1989年に出た論集『モダニズムの政治学』の副題は「新順応主義者たちへの対抗」とされている。それは論集に加えるはずだったが著者の急逝によって書かれずに終わった論考のタイトルでもあった。
戦後70年という節目をすぎた現在の日本において、ウィリアムズが提起した問題群は以前よりもいっそう関連性の度合いを増した。つまり、それこそ民主主義の危機も含め、危機の度合いが増した。じっさいこの2巻本論集の企画がもちあがった数年前から考えても由々しき状況にいたっている。人文学が置かれた現況もその危機の一局面にちがいない。
そうしたなかで、関連する一連の難題にいちはやく取り組んだこの「ライター」が私たちのいま・ここでの取り組みのための思考のヒントになると編者は確信している。「文学と社会学」の最後にウィリアムズが記したゴルドマン評は、ウィリアムズ自身についての私たちの感覚ともなるのではあるまいか。それは「持続する探求、持続する議論、持続する関心の感覚」である。「この時代に意味をなす反応をした人物」、わたしたちが「意味をなす共同体」を見いだし、「世界のなかにいてまなざしをむけ、存在し、行動する方途を見いだすためにそばに寄り添っていてくれる、そんな人物の感覚」である。
copyright Kawabata Yasuo 2016
(編者のご同意を得て抜粋掲載しています)
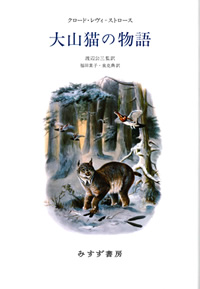
2016.03.11
C・レヴィ=ストロース『大山猫の物語』 渡辺公三監訳 福田素子・泉克典訳

2016.03.10
W・シュトレーク『時間かせぎの資本主義――いつまで危機を先送りできるか』 鈴木直訳