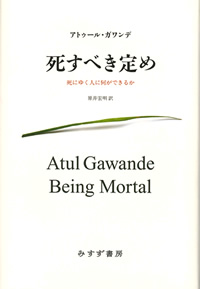
2016.06.27
「多くの人を感動させ、人生観を、人生を変えるはずだ」(仲野徹)
アトゥール・ガワンデ『死すべき定め――死にゆく人に何ができるか』
レジス・ドゥブレ 樋口陽一 三浦信孝 水林章 水林彪
『思想としての〈共和国〉――日本のデモクラシーのために』[増補新版]
2016.06.24
(2016年5月28日)
この国は「15年戦争」の国である。この国は、「15年戦争」の時代に天皇制を軸とする独特のファシズムを生み、天皇の神格化とともに、社会主義・自由主義思想の徹底的な弾圧を経て、ついには言論・出版・結社の自由の完全な抹殺にまでおよんだ。わたしの父母が生きた暗い時代である。
内外におびただしい犠牲を強いたその国がまともな近代国家としての歩みをなんとか開始することを可能にしたのは、日本国憲法である。その憲法が今危殆に瀕している。この異常事態に対して「共和国」の側から反応しないという選択はありえないと、わたしは即座に判断した。
敗戦から70年という年月が流れたわけだが、何故にこの国は、時効にかかることのない神聖不可侵の自然的権利の思想(「人権宣言」の思想)を引き継ぐ日本国憲法を血眼になって葬り去ろうとしている現政権の相次ぐ暴挙を許すほどに近代的成熟を欠いているのか。この問いと正面から向き合うことが『思想としての〈共和国〉』の増補版に期待されていることの少なくとも一部であるに違いないと考え、わたしはその旨を島原氏に単刀直入に伝えた。すると、島原氏はわたしの返答に驚くどころか、全面的に支持してくださったのである。この時期を選んでの増補版のお誘いの意味はそこにあったに違いないと、わたし自身は勝手に解釈している。
さて、その増補版の構想についてであるが、わたしは迷うことなく、水林彪に論考を依頼した。古代にまでさかのぼって日本の歴史の全景を視野に収めると同時に、その形成・展開に決定的な影響を及ぼした中国と西欧の文明を参照軸にすえつつこの国における「近代法の不全」の論理を明らかにせんとする彼の学問が、今この国で起こっている憲法をめぐる危機の根源を理解するうえで、もっとも鮮明な光をあてているように思われたからである。
ドゥブレ論文の深化と発展をめざすこの論考を読んで、わたしは多くを学んだ。西欧近代が何故にイギリス型の「自由主義(君主制国家からの自由)」とフランス型の「共和国」(市民的公共権力による自由)に分岐して登場したのか、なぜイギリスでは中世立憲主義の成果であるマグナカルタや権利章典が現在でも生きているのか、その社会経済史的由来を知り(ここで重要なのは、高橋幸八郎によって先導されたフランスにおける「封建制から資本主義へ」という通説史的理解への批判である)、そのうえで「共和国」とともに生まれた近代市民法的秩序が、いかなる意味において、市民共同的自己統治秩序と呼ばれるにふさわしいものであるのかを理解した。
また、日本国憲法の根底にあるのは実は「市民的公共権力による自由」を追求する共和国の精神なのであり、にもかかわらずその解釈と運用は、初発の美濃部憲法学のときからしてすでにそこからの逸脱であり、「国家からの自由」への横滑りであったことを了解した。
そして、さらには、今日の、自民党による「日本国憲法改正草案」にいたっては、一方では「国家からの自由」を極大化させ社会的権力を野放しにし、他方では「憲法」を、あろうことか、国民の行為規範とすることで近代法の立憲主義的構成それ自体を破壊しているという二重の意味において、「人権」に対して加えられた許しがたい攻撃であるということも納得した。
そして最後に、そのような憲法の立憲主義的危機の歴史的起源をたずねるならば、近くは江戸の幕藩体制、遠くはそれを規定した古代律令天皇制にまでさかのぼらねばならないことを知るにおよんだ。〔……〕
憲法学、憲法史学の立場からの樋口陽一のコメントは、「社会経済史を基礎とする欧米憲法史論の全体を再構成する」という課題が「手つかずのままに残されている」という水林彪の批判に敏感に反応して、とくに「共和国ヴァージョンによる体系組み替えの困難」について語っている。樋口は、この困難に「学問内在的問題」があることを認めつつも、あえて「自由主義型の近代憲法図式の中に止まり」、「国家からの自由に」執着するのは、国家権力が他者であり続けている「2012-16年のこの国の「状況」に対するいわば「法の賢慮」に発する戦略的な構えでもあるのだと述べている点が印象に残る。樋口のコメントでは、この部分が水林彪論考の「日本国憲法問題」を扱った第Ⅱ章に対する間接的な応答になっていると思われる。
憲法学・法学にまったく不案内なわたしはといえば、これまで「共和国」と「自由主義」の原理的対立の構図を十分に考えてこなかった憲法学界全体に差し向けられたこの壮大な規模の議論を、とりわけ、近代フランスが創出した市民社会(市民的政治社会)の原像を再構成するまことにスリリングな考察として読んだ。
copyright Mizubayashi Akira 2016
(ウェブ転載にあたり一部改行を加えました)
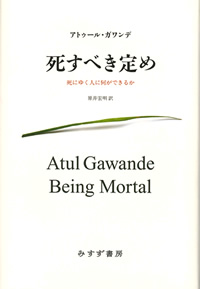
2016.06.27
アトゥール・ガワンデ『死すべき定め――死にゆく人に何ができるか』

2016.06.24
M・レディカー『奴隷船の歴史』上野直子訳 笠井俊和解説