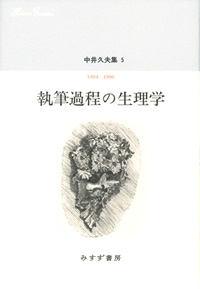
2018.01.10
『中井久夫集 5 執筆過程の生理学 1994-1996』最相葉月「解説 5」より
[第5回配本・全11巻]
明田川融『日米地位協定――その歴史と
2017.12.26
半世紀あまり前、思想家の藤田省三氏は「普遍的な道理にしたがう精神」を論じるにあたって、一八七二(明治五)年のマリア・ルス号事件から書きおこした。同事件は、マカオから二百数十名の中国人苦力を乗せたペルーのマリア・ルス号が横浜に寄港するが、荒天をついて脱走した苦力が日本政府の役所に駆けこんだことに端を発する。明治政府はどうしたかというと、協議の結果、そのうえ英国公使の意見をきいた結果ではあったが、奴隷売買は「文明の通義」(通は普通の通であり義は正しいという義であり、普遍的な道理という意味である)に反するといって船を拘束し、最終的に苦力全員を解放したのである。
事件には第二幕があった。苦力を解放されたマリア・ルス号の船長が、この航海は移民労働契約に基づくものであり、日本が苦力たちを解放したのは不当だと提訴したのである。さらに、その裁判途中で、船長側の弁護人が、「日本自体に奴隷がいながら、他国の奴隷売買を攻撃する資格が日本にあるのか」と指摘した。当初、日本側は面くらったものの、「成程、日本には伝統的な娼妓の制度がある。これはまぎれもなく人身売買によって成り立っている制度である」ということになり、時の司法大臣が娼妓解放令を出したというしだいである。藤田氏が言うように、「むろんこの法律一つでその制度がなくならなかったこと」は「これ以後の日本政府と日本社会の問題」なのだが、「その時にとった日本の政府の態度は、「文明の通義」つまり世界中の人類に妥当すべき道理の前には、よし、こちらの非道理をついた相手が弱小国であっても、その前に頭を下げるという、そして自己を正そうと努力しようとする精神、社会の変革期に必ず出て来る精神を一面で持っていた」ことを示すものであった。
筆者は、日米地位協定をめぐる政治史的考察の終わりちかくになって、明治初期に日本政府の指導者たちが持つことになったこの精神的経験の物語を想起せざるをえなかった。
(『日米地位協定』271-272頁)
このように、本書は「日米地位協定」をめぐる諸問題を、巨視的にも微視的にも描きながら、歴史から学ぶ・他者から学ぶという視点が基本に流れています。本書のテーマを自分の問題とするためには、このような物の見方が大切だと、あらためて思いました。
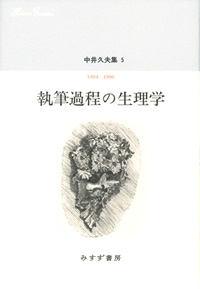
2018.01.10
[第5回配本・全11巻]

2017.12.11
ケイト・フォックス『イングリッシュネス――英国人のふるまいのルール』北條文緒・香川由紀子訳