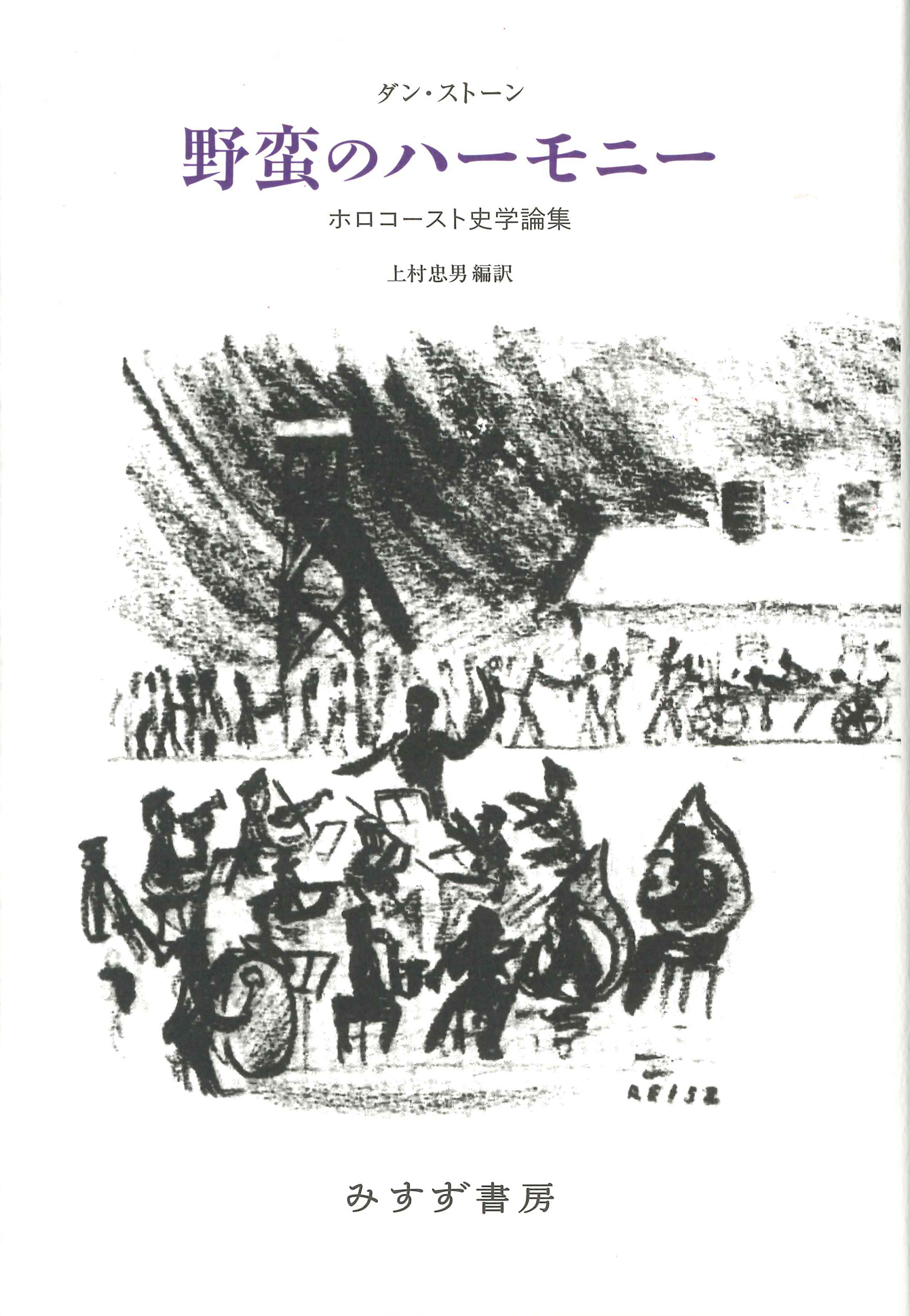
2019.11.12
歴史を書く・語る行為の方法と思想の最前線
ダン・ストーン『野蛮のハーモニー――ホロコースト史学論集』上村忠男編訳
『続・世界文学論集』田尻芳樹訳
2019.11.11
『思想』(岩波書店)2019年11月号の特集は「危機の文学」、この特集を提起したひとり沼野充義氏の論文のタイトルは「世界(文学)とは何か?」である。今世紀になったころから文学研究の焦点の一つとなった「世界文学」を「理念、現実、実践、倫理」の四つの側面からまとめる明快な記述には学ぶところが多い。ましてや、クッツェーのエッセー集の日本版(2015年)に『世界文学論集』と名付け、このたび『続・世界文学論集』を刊行するからには、「世界文学」という言葉が今日において孕んでいる問題を強く意識しないわけには行かない。
『エッカーマンとの対話』で1827年にゲーテが語ったという、「今日、国民文学はあまり意味がない。世界文学の時代が到来しているのだ」という提言には、何度でも立ち戻る意義があると思わされた。つづけて沼野氏はマルクス=エンゲルスの『共産党宣言』からのフレーズ、「民族的な一面性や偏狭は、ますます不可能となり、多数の民族的および地方的な文学から、一つの世界文学が形成される」を、片や努力目標、片や歴史法則の必然的な帰結、という違いを指摘しながら引用している。
ところで、戦後日本で「世界文学」全集と銘打たれたアンソロジーによって小説を読む喜びを知った世代にとって、そこから外れた河出書房「世界新文学双書」(例えばデュラス『夏の夜の十時半』)に刺激を受け、「新潮・現代世界の文学」シリーズ(例えばガルシア=マルケス『百年の孤独』)の変化球をキャッチしてきたにせよ、圧倒的に欧米の白人男性作家によって文学イメージが作られてきたことは否定できない。
しかし出版も読者も、全集という名のアンソロジーを通読乱読するのではなく、そのときどきで個別の作家・作品を選ぶ(流行により選ばされる?)傾向がつよまった。いっそ普遍の対極にある個人(すぐれた作家や翻訳家)のセレクトやレコメンドにしたがって読んでいるほうが、ずっと楽だし外れがない。どんどん広がる文学の領域(文学の脱中心化)のすべてを追うことなど、どうせ誰にもできない。ましてやジェンダーやポストコロニアルやグローバリゼーションの概念を無視していわゆる「名作」を享受することなどなんの意味があるのだろう、というわけだ。そんなとき世界の文学を、いったいどう読めばいいのか?
一つの答えがここにある。南アフリカ出身、『マイケル・K』と『恥辱』でブッカー賞を二度、ノーベル文学賞も受けた作家クッツェーは、2013年から2015年にかけてアルゼンチンの出版社「アリアドネの糸」からスペイン語訳の「個人ライブラリー」全12巻を刊行した。カフカ『短編集』、ベケット『モロイ』、デフォー『ロクサーナ』、フローベール『ボヴァリー夫人』などの巻があるが、それとは別の五作品の巻頭に付された序文が『続・世界文学論集』には収められている。一貫して人間のモラルを物語で追究してきたクッツェーは、自作の刊行においても、「英語中心主義」と出版における「北半球のヘゲモニー」にたいする抵抗として、最近は英語以外の言語(南米のスペイン語やオランダ語、日本語)の出版を先行させている。
こうした姿勢にくわえて、「世界文学」研究の潮流における課題である「翻訳」についてもクッツェーは見逃さない。たとえばゲーテの『若きヴェルタ―の悩み』の最初の英語訳はフランス語からの重訳だったと、本書に書いてある。そして、「彼女の心を支配した優しさ(the tenderness)に関して私は責められるべきだろうか」とあるのは、ドイツ語原文のeine Leidenschaft(情熱)がフランス語に訳されたtendresseから来ていると指摘する。現代の英語訳では「かわいそうなレオノーレの胸に本物の情熱(a real passion)が生じていたとしても僕の責任だろうか?」となっている箇所である。でもそれを「誤訳」とは言えないとクッツェーは言う。「われわれが恋愛感情の作動を観察し、情熱が支配的になっているのを見る所で、1770年代の教育あるイギリス人は優しさを見たのである。われわれの21世紀流のゲーテ理解に忠実だが、1770年代の読者も安心したであろうような『若きヴェルタ―の悩み』の翻訳など、達成不可能な理想なのだ。」
クッツェーの「私はこう読んだ」と思わせる批評を読む者は、古今のそして南北の文学に惹きつけられる。たとえば1956年クリスマスに雪原で凍死した作家ローベルト・ヴァルザーの小説『助手』から、季節の変化と自然を描いた長い段落を引用してから、クッツェーはこう書いている。「ヴァルザーは生涯に多くの詩を書いたが、経験主体の歴史に埋め込まれたこの一節のように心に響く詩は一つもありえない。このような陶酔して祝福するような散文は、一人の男の心中にわれわれを引き込む。移ろい行くスイスの風景につねに変わらぬ慈悲深さの現れを感じるが、同時に、暖かいベッドの安逸にも同じくらい感謝するかもしれない、そんな男の心中に。」
沼野氏の論文「世界(文学)とは何か?」は、「世界文学とは遠くの他者と関わることを可能にする形式なのだから。」と結ばれている。「他者」をじっと見つめてきた作家クッツェーによる文学論をきっかけに、文学のさらなる沃野に踏み出す読者が一人でも多いことを願っている。
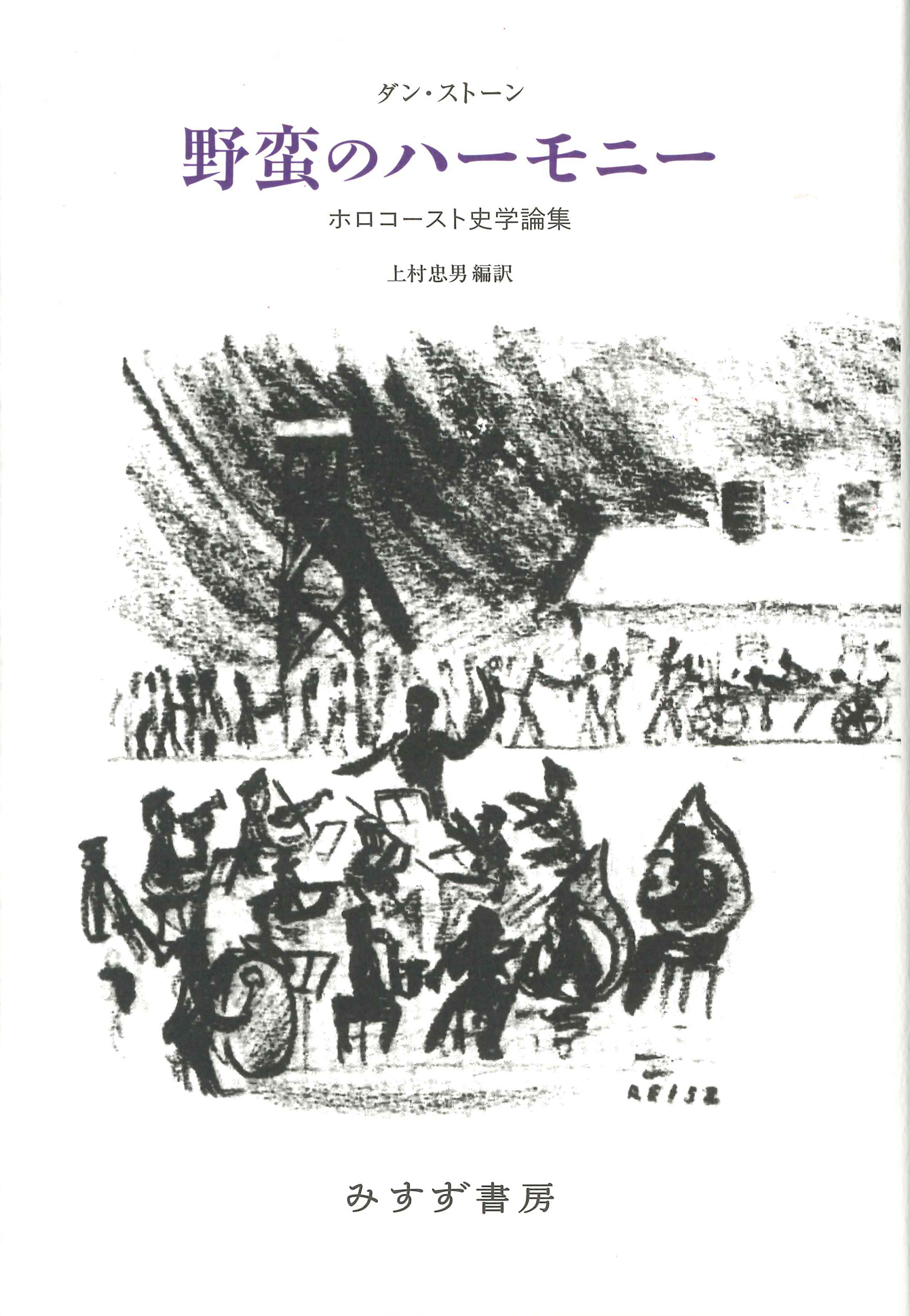
2019.11.12
ダン・ストーン『野蛮のハーモニー――ホロコースト史学論集』上村忠男編訳

2019.11.05
池内了『科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか』