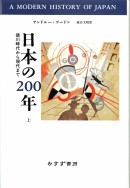トピックス
小林修一『日本のコード』
〈日本的〉なるものとは何か
小林修一
(著者)
本書は、前著『ヒト・社会のインターフェース』(法政大学出版局、2005年4月)http://www.h-up.com/のいわば応用編として、日本の社会文化を対象として分析を試みたものである。前著の段階では認知言語学や認知意味論の詳細についてはフォローしきれていなかったので、前著刊行後、そうしたレトリカルな認知構造を基底とした社会文化的な上部構造の理解を具体化する可能性に注目して、一連の日本の社会文化分析を試みてきた。
その成果として本書では、社会学、言語学、思想、それぞれの先行研究をふまえて、日本の社会・言語・文化に潜在する構造を析出し、日本の文化と社会を論ずる礎を築いてみた。日本語、日本文化、日本社会、各々のコードを析出し、日本社会の変革を展望するための、認識の整理に努めた。
たとえば、「第六章「世間」のコード」。前章までに、日本語、日本文学、形象文化など、日本文化の諸相に潜在する一連のメトニミー性に注目した分析を試みた。しかし、レトリックがたんなる認知の方策であるだけではなく、そのことを通して、人々の社会的実践をも方向づけるものであるとしたら、それは日本社会のあり方をも規定することが予想される。日本固有の社会のあり方として、「世間」に多くの関心が払われてきたが、この「社会」と「世間」の両概念をめぐっては、今日にいたるまで錯綜がみられる。そこで、この混乱を整理したうえで、「世間」に潜在するメトニミー性の解析を試みた。
さらに、続く章では、家族国家のコードを探究した。明治末年以降、戦中にいたる日本固有の「社会イメージ」としての「家族国家」観を支えた思惟構造はメトニミー的認知図式であった。そこで、この認知図式の特質を「家族国家」観の主要な特徴と関連づけることを通して、その点の検証を企てた。もとより、家族国家観に関する幾多の研究の蓄積を前提とした試みではあるが、そうした論議から提示されてきた主要な指摘や特徴、発想などをより整合的に一貫して説明可能にする枠組みこそ「メトニミー」的な認知図式であることを示した。
一貫して、日本社会の現状分析のための原理論構築に腐心した。読者の方々各自の問題意識に沿って、なにがしかの役に立てば幸いである。
- 丸山真男『戦中と戦後の間』はこちら
- 丸山眞男の本はこちら
- 藤田省三著作集 1 『天皇制国家の支配原理』はこちら
- 藤田省三の本はこちら
- 鶴見俊輔の本はこちら
- E・T・ホール『かくれた次元』(日高敏隆・佐藤信行訳)はこちら
- 外山滋比古著作集 5 『日本の言葉』はこちら
- A・ゴードン『日本の200年』上(森谷文昭訳)はこちら
- A・ゴードン『日本の200年』下(森谷文昭訳)はこちら
- 細川周平『遠きにありてつくるもの』はこちら