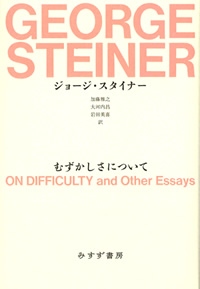
2014.09.25
ジョージ・スタイナー『むずかしさについて』
加藤雅之・大河内昌・岩田美喜訳
宇野邦一解説
2014.09.25
「長い間、絶版となっていた『文学的考察』は、七十年代の末に渡辺一民の努力によって、冨山房百科文庫の一冊に収められた」。本書の編集作業中、中村眞一郎『戦後文学の回想』を読んでいて、この一文と出会った。増補版のために書き下ろされた「二十年後の再説」のなかにある。
じつは著者・渡邊一民さんと冨山房百科文庫との関わりについては十年ほど前、ご本人からほんの少しばかりうかがっていた。たしか海外文学全集が全盛だった時代とそこに編訳者として参加した海外文学者、といった話の流れのつづきだったように思う。しかし、なにぶん酒の席でのことで、編集委員的存在としてほかに川村二郎、篠田一士の名があがったことぐらいしか記憶にない。
そこであらためて調べてみると、戦後版冨山房百科文庫の創刊は1977年4月。同月中に5冊刊行されていて、『1946・文学的考察』はそのなかの1冊である。渡邊一夫訳ゴーチェ『青春の回想』は「解題・渡辺一民」であり、スタンダール『エゴチスムの回想』訳者あとがきには「旧稿の存在を書肆に伝えて下さった渡辺一民氏」とあるから、創刊5冊のうち少なくとも3冊と一民さんは関係があったことになる。
さらに同年8月刊のペイター『ルネサンス』訳者あとがきは協力者として中世フランス語研究者の名前をあげているが、翌年1月刊ロジェ・ステファーヌ『冒険者の肖像』の訳者と同様、こちらは若い世代の「一民」人脈である。みずから翻訳者として名を連ねはしなかったものの、たんなるブレーン的存在にはとどまらない働きをしていたことはたしかだろう。戦時中の座談会に竹内好の論考を加えた『近代の超克』(1979年2月刊)もまた「渡辺一民の努力」によるものではなかったか?
先日、荒正人『第二の青春・負け犬』を神保町の古書店で入手した。1978年5月刊、冨山房百科文庫の16冊目にあたる。解題を執筆したのは一民さんで、こんなふうに書きだされている。
「わたしは『第二の青春』『負け犬』の二冊を読んだときの感動をいまでも忘れることができない。わたしが刊行されたばかりの『第二の青春』と友人から借りた『負け犬』とをつづけて読んだのは、たしか一九四七年晩秋のことだった」
なんだか本書の「序章 一九四七年夏」冒頭とそっくり――ではないか。ただし「夏」と「晩秋」という微妙な時間差ではある。少々長くなるが続きを引用しておきたい。
「そのころのわたしは、ドストエフスキーに憑かれ、焼け残ったむきだしの壁の映画館の固い木の椅子にすわって『外人部隊』や『地の果てを行く』の画面を喰いいるように見つめる一方、彰考書院の『共産党宣言』や『国家と革命』のパンフレット、あるいは永田廣志の『唯物史観講話』に読みふけり、しだいに政治運動にかかわりだしていた。けれどもそんなわたしにも、古本屋で探してきた伏せ字だらけの部厚い蔵原惟人の『芸術論』だけはどうしても納得できず、読書会のたびに作品の社会的価値と芸術的価値といった概念に異議をさしはさみ、いつも仲間の集中攻撃をうけていた記憶がある。わたしには社会主義をめざしての実践については何ひとつ異存はなかった。ただそうするために、『カラマーゾフの兄弟』やシャルル・スパークを否定することだけは断じてできないことだった」
この姿勢はその後「思考と行動の指針」にも導かれ、さまざまな思潮にもまれつつもますます揺るぎない確信となった。そしてそれはモーリス・バレスや対独協力派といったフランスの「右翼」作家を日本で最初に批評の対象としたデビュー作『神話への反抗』(1968年)から本書『福永武彦とその時代』にいたるまでの全仕事をつらぬいている。
夏の「衝撃」、晩秋の「感動」。それゆえにこそ著者は「短かったとはいえ過去とのきびしい対決のなかでさまざまな根源的問いかけのおこなわれた〈戦後〉とよばれるあの神話的時代」を執拗に問いつづけた。とはいえ冨山房百科文庫編集の精神と同様、みずからの開いた問いが手渡されるべきバトンであることに十分自覚的だったにちがいない。


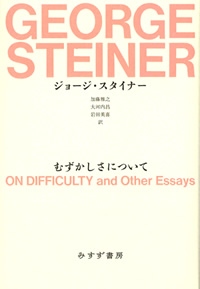
2014.09.25
加藤雅之・大河内昌・岩田美喜訳

2014.09.16
若島正・選