
2014.10.24
池内了『科学・技術と現代社会』
全2巻
[新装版]
2014.10.10
今年1月の生誕百年を記念して、今夏刊行した詩集『うつわの歌』[新版]につづき、『若き日の日記』の新装版を刊行いたします。
本書は、1942年4月から1945年12月まで、戦争中の医学修業および空襲下の東京で医師として被災者支援に勤しむ様子が書きしるされています。神谷(前田)美恵子29歳から31歳の時期にあたります。
戦中・戦後の東京市民の状況を知る意味でも興味深い資料であり、そして何より、のちに精神科医・神谷美恵子が誕生する礎となった、青春時代の葛藤がいきいきと描かれている点が貴重です。
神谷美恵子の葛藤、それを象徴する言葉が本書の帯にあります。
「私が医学を選んだのは正しい。(……)あまりはみ出して困る分は詩にせよ」
病める人、とりわけハンセン病に苦しむ人々に現場の医療者として役立ちたいと、26歳にして医学の道へと転身し、そのことへの迷いは一切ないものの、自分のあたまでものを考え、それを自分の言葉で表現したいとの思いはいっそう強くなってゆきます。その葛藤がやがて、『生きがいについて』『うつわの歌』などへと昇華してゆくことになるのでしょう。

日本の小説や随筆を味読し、折々に感想を書きとめているのも読みどころです。その中の一冊、寺田寅彦『柿の種』は、実際に神谷さん(当時は前田さん)が所蔵していた本がいま手元にあります
「(……)薬物70頁、細菌10頁読んだ。どうもまだ試験気分が出ない。いろいろな考えがただよっていて困る。(……)前原さんに頼んで神田から買って来てもらった『柿の種』をひもといて巻頭のいくつかの文に強く惹かれた。」(1942年6月17日)
昭和8年小山書店版のこの本には、ところどころにエンピツ書きの書き込みがのこされています。
『うつわの歌』[新版]に増補した、感謝と祈りの気持ちが優しくうたわれた晩年の詩は、本書『若き日の日記』にある、次のような言葉と重なりあいます。
「人の心の喜びや悲しみを、心から歌いつつ死にたい。(……)人の世も、人の心も、己が心も、要するに謎である。それをあるがままに歌おう、わからないままに美しく、色とりどりであるそれを」
(1943年2月22日)
苦闘しつつも、ひとすじの道を歩き通した神谷さんの姿が浮かんでくるような『若き日の日記』、この機会にぜひお読みいただけたら幸いです。


2014.10.24
全2巻
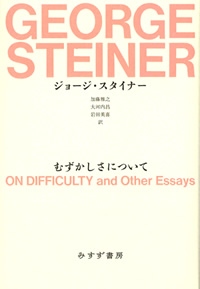
2014.09.25
加藤雅之・大河内昌・岩田美喜訳