
2016.09.12
夢についての論考をはじめて一冊に。臨床家ユングの姿を生き生きと伝える
『ユング 夢分析論』 横山博監訳 大塚紳一郎訳
カルロ・ギンズブルグ『ミクロストリアと世界史――歴史家の仕事について』 上村忠男編訳
2016.09.12
本書に寄せた著者カルロ・ギンズブルグの「序文――日本の読者へ」をここに掲載します。短いながら、本書の紹介と特徴がよくあらわれています。
本書(この形態では他のどの言語にも存在しない)を出版するよう促してくださったのは、上村忠男教授である。かねてよりわたしの仕事に関心を示され、それを日本の読者に提供すべく不断の努力をなさってこられたことにたいして、深く感謝する。上村教授の示唆にしたがって、わたしはここ10年間におけるわたしの仕事の支配的なテーマのいくつかを――とりあげた素材こそさまざまであるが――示しているとおもわれる一群の論考を選んだ。もしわたしの判断が間違っていなければ、これらの論考すべてにおいて、経験的研究と方法論的分析とが密接に絡まりあっている。
「方法」という語に接するたびに、わたしは決まって、ジョルジュ・デュメジルの伝えるフランスの有名なシナ学者マルセル・グラネの「方法というのは、ひとが通り抜けたあとでできる道のことである」という言葉を想い起こす。ギリシア語の語源が示唆しているように、方法――メタ・ホドス(metà hodòs)――は文字どおりには「道のあと」という意味で、研究のための処方箋のようなものではまったくなく、回顧的な省察のなかから姿を現わす(あるいは現わすのでなければならない)。回顧的な――しかし、どの段階においでであろうか。「わたしたちの言葉と彼らの言葉」や「無意志的啓示」のような論考からは、分析の道具を消毒する必要が生じるたびに人の研究がたどる軌道に句読点を打たなければならなくなっていることがわかる。
もし間違っていなければ、この方法論的関心はわたしの仕事をそもそもの出発点以来ずっと支配してきたものだった。わたしが公表した最初の論考「魔術と民衆の信仰心」(1961年)は、魔女であるとして告発されたひとりの農婦、キアーラ・シニョリーニにたいする16世紀の異端裁判に焦点を合わせたものであったが、「キアーラ・シニョリーニのケースは、それの還元不可能な個人的側面にもかかわらず、なんらかの仕方で模範(パラデイグマ)的な意義をもつことがありうるのである」という文章でもって終わっていた。今日では、「模範(パラデイグマ)的」という語を聞けば、ただちにトマス・クーンの 「パラダイム」のことが思い浮かぶ。しかし、彼の多大な影響をおよぼすこととなった『科学革命の構造』が出版されたのは、わたしの論考が公表された一年後の1962年のことであった。個々のケースとそれらに含まれる一般的な(ときとして範例的な)意味にたいする関心は、すでにそのわたしの最初の研究の核心に存在していたのだった。そして、「緯度、奴隷、聖書――ミクロストリアの一実験」や「世界を地方化する――ヨーロッパ人、インド人、ユダヤ人(1704年)」の読者なら容易に見てとることができるように、それ以来ずっと核心でありつづけてきたのである。ラ・クレキニエールとかピュリといったほとんど無名に近い個人でも、はるかに大規模な現象にかんする省察への道を拓くことがありうる。「ミクロストリアと世界史」(本書の標題にもなっている論考)は、互いに両立不可能であるどころか、相手を強化しあうのだ。
事例研究(ケース・スタディーズ)とそれらの含意へのわたしの深い関心は、多くの学者たちからインスピレーションを得てきた。なかでも最もきわだった人物の一人がアビ・ヴァールブルクだった。「ヴァールブルクの鋏」はわたしが彼の仕事に知的に負っているものにかんしてなにがしかの光を投げかけてくれるだろう。「神は細部に宿る」とヴァールブルクは言っていた。これは「悪魔は細部に潜んでいる」という諺をもじったものである。悪魔ではないまでも、少なくとも悪魔の代言人が、わたしの知的旅における親しい同行者であった。もうひとつの論考「悪魔の代言人としてのユダヤ人」がその理由を説明してくれている。
ボローニャ、2016年6月
カルロ・ギンズブルグ
〔上村忠男訳〕

2016.09.12
『ユング 夢分析論』 横山博監訳 大塚紳一郎訳
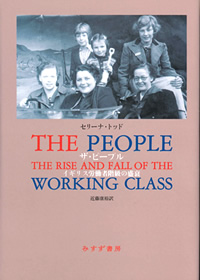
2016.08.29
セリーナ・トッド『ザ・ピープル――イギリス労働者階級の盛衰』 近藤康裕訳