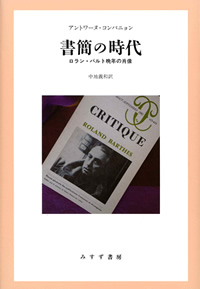
2016.12.12
手紙を交わしていたあの頃、道具もまた個人の道具であった。
アントワーヌ・コンパニョン『書簡の時代――ロラン・バルト晩年の肖像』 中地義和訳
[全11巻]
2016.12.06
その透徹した知性と柔らかな感性で、われわれの時代に鮮やかなしるしを刻んできた精神科医・中井久夫。半世紀におよぶ思考と実践の道筋を、全11巻で追う。
[第1回配本]
第1巻 働く患者 1964-1983
1月中旬刊 予価3200円(税別)
詳しい書誌情報はこちら
日本の精神医学に新たな道を切り拓き、透徹した理性と柔軟な感性、研ぎ澄まされたアンテナ感覚で人と時代を捉えてきた精神科医・中井久夫。専門論文であれ、エッセイであれ、小サークルに向けたことばであれ、区別することのないその気品あふれる文章は、詩集を始めとする翻訳ともども、多くの読者の心に響いた。
1964年にペンネームで発表した論考から東日本大震災以後まで、半世紀にわたり世に届けつづけた作品の数々をここに年代順に編み、著者の歩みの一端を共有したいと考える。
類い希な叡智、まさしく本物の品性、時代や社会を全体的に鋭く深く的確に捉えつつ、かたや声を挙げる術を持たず、日陰に苦しむ人々へも眼差しを向ける社会性の結実がここにある。この著者の世界に触れる幸せ!
村瀬嘉代子(臨床心理学者)
気品。高雅。透徹。この比類のない賢人と同時代を生きられた幸運を慶ぶ。中井久夫先生の思索は、内に閉じ小さく縮こまろうとするわたしの心と身体を、絶えず外に向けて開きつづけてくれた。
松浦寿輝(作家・詩人)
この人と同時代に生きていてよかった…と思えるオジサマのひとりが中井久夫さん。精神病についても、災害についても、この人がいたおかげで日本の社会はどれだけ変わっただろう。詩とエッセイにはいつも目を洗われるし、時評にはいつも背筋をゾクリとさせられる。
上野千鶴子(社会学者)
知性とはテクノロジーと同じほど危険な道具で、人を凶暴にも尊大にも愚かにもさせるものだが、中井久夫は知性本来の崇高さの中で文章を肉声で静かに語るように書く。私は同時代に生きられたことを奇跡と感じる。
保坂和志(小説家)
トラウマの領域は、ヒステリーのように胡散臭いか、あるいは反戦や女性運動のように政治的かという両極端を揺れ動いて、まともな精神科医が相手にするものではないように長年思われてきた。中井先生は明晰でみずみずしい言葉によって、日本の状況を変えてくださった。
小西聖子(臨床心理士・精神科医)
時には花の香にふくらむ春風のような甘やかな言葉遣いをする、あたたかい叡智と、透徹した明察と、この世の正を求める情熱とを兼ね備えた友人を、一人あなたは書架に持ちたくはないか。名を中井久夫と言う。
佐々木中(作家・哲学者)
文系と理系の壁を易々と乗り越えた、ウイルス学者の父も政治学者の私も心して読まねばならない著作集。それが「中井久夫集」だ。拙著『大正天皇』は、3巻所収の「「昭和」を送る」から着想を得ている。
原武史(政治学者)
精神医学の核心へとつらなるいくつもの道筋、時代を画する臨床=治療論、ヒトが生き・病み・老いることをめぐって広がるさらなる思索。年代順に編まれた「中井久夫集」からそれらすべてがあふれだしてくる。
江口重幸(精神科医)
おだやかな言葉なのに、強い。自分が道を見失っている気がするとき、この強さにふれると、諭されたように正気に返る。「中井久夫集」は、漂流するわが本棚の、錨となってくれるだろう。
渡邊十絲子(詩人)
この全集に収録されている300本を越えるエッセイの表題をチェックしているうちに、唖然としてしまう。「認知症に手さぐりで接近する」「現代中年論」「クラス会に出る」「いつも誰かが被災地に」等々。やっぱり中井久夫さんはすごい!
富山太佳夫(英文学者)
中井先生のご本はもう書棚にぎっしり。全集のスペースに悩ましいけれど、やはり揃えたい。年代順の編集で1巻から読み進めば、ときには大河ときには清流のような先生の長い思索の流れを深くたどってゆけるからである。
滝川一廣(精神科医)
中井先生の著作は、ヴァレリー/身体/生理学をめぐる私の思索の導き手でした。特にリズムに対する視点には目が開かれました。
伊藤亜紗(美学者)
医学生の頃からこのかた、壁にぶつかるたびに中井先生の本を開いてきた。迷ったときに採るべき途を照らす北極星のような先生の著作の数々が、一斉に世に出ることは、これからの人たちにも、きっと大きな導きと励ましになることでしょう。
津田篤太郎(漢方医)
中井の尋常ならざる博識と、難解な思想を見事に翻案してみせる卓抜なセンスに触れる者は、この知性に飲み込まれる恐怖を体験する。だが、彼は同時にそれをケアする能力にも長けていた。読むのを恐れることはない。
松本卓也(精神科医)
中井久夫氏は文系・理系の枠組みを超えた存在だ。私達は彼を通じて、そのどちらもが人間の存続にとって必須のものであることを知るに至る。
名越康文(精神科医)
臨床家としての中井久夫氏の文章は、まるで3Dの投影機のようだ。私は何度も、行間から医師と患者さんの姿が浮かび上がるのを見て、やり取りの声を聴いた。そのときの感触を頼りに、私はいまも臨床を続けている。
香山リカ(精神科医)
理論と臨床。思想と行動。知識と知性。洞察と優しさ。ある種の「ねじれ」のもと、ひとりの人間の中で、それらが奇跡的にも両立しうることを示してくれたひとは、中井久夫を措いてほかにない。その文章は、日本語による最もみごとな科学と詩の共鳴混成体であり、一切の体系化をしりぞける「箴言知」として、北極星のごとく瞬いている。
斎藤環(精神科医)
どんな隙間にも入ってゆく針金のように強靭でしなやかな思考と、「心の生ぶ毛」ともいわれる繊細な思いやり。生きものとしての私たちに未だ残照のように残っているはたらきを知らされて、どれだけ勇気を得たことか。
鷲田清一(哲学者)
ミクロにはウイルスの生物・無生物の境から、マクロには阪神淡路大震災の経験から、そして、ほかならぬ精神を病む統合失調症者のこころの内側にそっと手をのべ、希・仏の詩の心をもって優しく語りかける、それが、中井久夫先生です。
山中康裕(精神科医)
変われるかもしれないと思い、中井先生の本にすがるのは私だ。『「昭和」を送る』の「往診先のペット」を読んだ時、一匹の犬に敗北する人の美しさに打たれた。人が精神を病まなかったら、この世は破滅すると気づかされて粛然となる。人はもっと発見されたいと寂しがっている、と中井先生の本は語りかけてくる。
青木研次(脚本家)
ものわかりのよい優しいお医者さんだと思ってもよいこの人は、けっこう実は硬派でもある。そしてその二つはつながっている。
立岩真也(社会学者)
1934年奈良県生まれ。京都大学医学部卒業。神戸大学名誉教授。精神科医。
著書『中井久夫著作集――精神医学の経験』全6巻・別巻2(岩崎学術出版社、1984-91)『分裂病と人類』(東京大学出版会、1982、2013)『精神科治療の覚書』(日本評論社、1982、2014)『治療文化論』(岩波書店、1990)『こんなとき私はどうしてきたか』(医学書院、2007)『私の日本語雑記』(岩波書店、2010)『日本の医者』(日本評論社、2010)ほか。
みすず書房からは、この『中井久夫集』に収録しない『最終講義』(1998)『西欧精神医学背景史』(1999、新装版2015)以外に、16冊の単著、3冊の共著がある。翻訳書も、みすず書房からサリヴァン、ヴァレリー、カヴァフィスなど20冊以上を刊行。
![『中井久夫集』[全11巻]リーフレット(みすず書房)](/_wp/wp-content/uploads/2016/12/nakai_11vols.jpg)
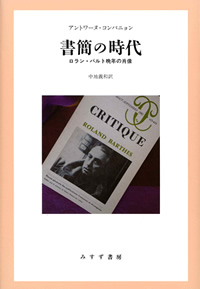
2016.12.12
アントワーヌ・コンパニョン『書簡の時代――ロラン・バルト晩年の肖像』 中地義和訳
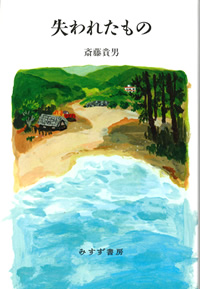
2016.11.30
斎藤貴男『失われたもの』