
2018.08.07
脱北者とオリンピックをめぐる小説は、朝鮮半島の現実直視、本音全開。そして哀しい。
チョン・スチャン『羞恥』 斎藤真理子訳
ゴウリ・ヴィシュワナータン『異議申し立てとしての宗教』 三原芳秋編訳 田辺明生・常田夕美子・新部亨子訳
2018.08.02
(編訳者の「まえがき」より抜粋してご紹介いたします)
本書は、米国コロンビア大学の英文学・比較文学科で長年にわたり教鞭をとるゴウリ・ヴィシュワナータン教授の仕事を本邦においてはじめて本格的に紹介するために、著者と訳者とのあいだの話し合いを通じて独自に編まれた論文集である。著者の来歴や本論集のねらいなどについては巻末インタヴューにおいて多く語られているので、ぜひそちらも合わせてお目通しいただきたい。
ゴウリ・ヴィシュワナータンと聞くと、まずは「エドワード・W・サイードの愛弟子にして後継者」という呼び名を思い浮かべる読者も多いだろう。実際、本邦において彼女の名前がもっともよく知られているのは、サイードの四半世紀にわたるインタヴューをまとめた『権力、政治、文化――エドワード・W・サイード発言集成』(Said 2001b/サイード 2007a)の編者としてではないだろうか。コロンビア大学におけるサイードの教え子でありかつ長年の同僚として、その仕事をもっともよく理解するヴィシュワナータンが、この重要な仕事を任されたのはきわめて自然のなりゆきだったのだろう。(中略)
サイードのもとで書かれた博士論文は、その年の暮に『征服の仮面〔Masks of Conquest〕』(Viswanathan 1989)というタイトルでコロンビア大学出版局から上梓され、ゴウリ・ヴィシュワナータンの名前は、英文学・比較文学のみならず教育史・思想史・南アジア研究などさまざまな分野で広く知れわたるようになる。また、同年コロンビア大学に呼び戻されたヴィシュワナータンは、サイードの同僚として、その逝去後は後継者として、今日に至るまで精力的に後進の指導にあたっている。
第二の主著である『群れをはなれて〔Outside the Fold〕』(Viswanathan 1998a)は、米国(おそらく世界)最大の人文系学会組織である米国現代語学文学協会(MLA)により権威あるジェイムズ・ラッセル・ローウェル賞を授与されたほか、米国比較文学協会(ACLA)のハリー・レヴィン賞ならびにアジア研究協会(AAS)のクマーラスワーミー賞の受賞と、異なる専門分野の各賞を「領域横断的」に総なめにした、記念碑的な作品である。本翻訳論集では、第二部において本書から中核的な二つの章(アンベードカル論およびラマーバーイー論)を訳出しているが、ここではその「まえがき」冒頭の一文を紹介したい。
おそらく改宗は、宗教の変更というその語がもつもっとも明白な意味においても、社会生活のなかで動揺を引き起こさずにはおかない政治的出来事の、最たるものである。(Viswanathan 1998a: xi)
「信仰」にかかわることがら、ことに「改宗(回心・転向)」といった個人の内面(魂)における激烈な葛藤と克服のドラマとして私秘的な物語に回収されがちなことがらについて、それをあくまで「社会」的〈生〉=(集団的)関係性の問題と位置づけ、そこに間違いなく「政治」性を見いだす批判的知性の鋭利な刃をきらめかせつつも、思いやりをこめて個々の「出来事」の特異性を見つめる文学的感性をもって対象に〈ふれる〉……これは、『征服の仮面』以来一貫してヴィシュワナータンが保持している〈読み〉のスタイルである。そして、この冒頭の一文におかれている「動揺を引き起こさずにはおかない〔unsettling〕」という語――くしくも、それは、自らの死を目前にしたサイードが「晩年のスタイル」を語る際に好んで用いることとなる語でもある――は、ヴィシュワナータンの仕事を考えるうえで、きわめて重要な意味をもっていると思われる。同書において、「改宗」がもつ〈異議申し立て〉の潜勢力――本翻訳論集の第二部の表題でもある「世俗批評〔secular criticism〕としての改宗」という危機的=批評的(クリティカル)契機――が開陳される場面でも、この語が登場する。
異議申し立てがもっとも力強く表現されるのが改宗、ことに少数派宗教への改宗であるならば、その理由を理解するのはそれほどむずかしいことではない。改宗は、変更不能な固定されたアイデンティティという概念を反故にすることによって、自己であること、市民・国民であること、共同体をなすこと、といったことがらを定義づけるさまざまな境界を動揺させ〔unsettle〕、それらの境界壁が穴だらけであることを暴露するのだ。(Viswanathan 1998a: 16)
ここで「異議申し立て」と訳した元の英単語は〈dissent〉である。「意見の相違」「不同意」を意味するラテン語由来の古い単語で、英国史の文脈ではとくに英国国教会反対(離脱)者のことを〈Dissenters〉と呼びならわし、また、米合衆国司法の場では、たとえば連邦最高裁判決に付される「少数意見」、すなわち多数決に敗れた少数派の判事が書き記す異議のことを〈dissenting opinions〉と称する。語源的には、dis-(異なる) + sentire(感じる、考える)であるから、文字どおりには「違和感を覚える」こと、さらに言えばその「違和感」をなんらかの方法で表現すること、と理解してさしつかえないだろう。(中略)
入植者たち〔settlers〕は、壁を築くことによって境界線を一方的に確定し、目に見える「外部」を捏造する。それは代理=表象(リプレゼンテーション)以外のなにものでもなく、権力〔potestas〕はそこにおいて代表権(リプレゼンテーション)を主張する。他方で、一方的に引かれた境界線の存在を認めず、怒りをこめてその壁をひたすら凝視するうちに、一見不動のものと思えていた巨大な壁がじつは穴だらけであることを看取するような危機的=批評的(クリティカル)な瞬間=契機(モメント)が訪れることがある。それは、ある種の異他=異端的(ヘテロドクス)行為・出来事であり、境界線の存在自体をぐらつかせる〔unsettle〕こととなるだろう。そうやって壁がぐらつくとき、偶然的にふと生起した「偏差」が予想外の「次元の開け」を生み、そこに、目に見えない「外」の力〔potentia〕が流入してくることがあるかもしれない。そういった「見えない力」に〈ふれる〉経験を共有するための多様な表現形態をヴィシュワナータンは一貫して探究してきたのだと言えるが、「改宗」論においては、どちらかというとその(世俗)批評的側面にウェイトがおかれていたものが、最近の仕事における「オカルト的なるもの」への関心はむしろ、そのような〈経験〉が切り開くオルタナティヴな〈生〉の技法(アート)を模索する方向へと向かっているようにみえる。そこで(あらためて)注目されていくのが芸術(アート)であり、なかでもとくに文学における想像力/創造力の問題であることは、深く首肯されるところである(本論集・第三部の諸論考を参照)。
このようにして見ると、最初期の〈英文学〉制度批判から改宗論をへて現在進行中のオカルト論にまで一貫しているのは、分離壁によって問題を解決〔settle〕しようとする権力――植民地政府、ドグマ的宗教、公定世俗主義など――に対する異議申し立ての「多様な表現形態」を「注意深く観察する」(巻末インタヴュー、423頁)態度だと言えるだろう。このような態度には、恩師サイードが「権力に対して真実を語る」と宣明する際の豪胆さは、たしかに見られないかもしれない。しかし、それは、そんな豪胆さがまたひとつの分離壁を知らず識らずのうちに築いてしまうことに「違和感」を覚える感性のあらわれであり、また、その新たな壁の存在によって聴き取れなくなってしまうかもしれない弱き声に「注意深く(ケア-フル)」寄り添う〈生〉を肯定する意志のあらわれでもある。この流れの中に、サイード的「世俗批評」の最良の後継者でありながらもサイード自身に伏在する「世俗/宗教」という分離壁をきびしく批判する態度があり、また、「苦痛する身体」への気遣い(ケア)から生じるヴェジタリアニズムやさまざまなスピリチュアルなライフスタイルを肯定的に見つめる繊細なまなざし(本論集・第七章)がある。ヴィシュワナータンは、誰もが認める「サイードの後継者」ではあるが、けっして「サイード主義者」ではないのである。(後略)
copyright Mihara Yoshiaki 2018
(筆者のご許諾を得て抜粋転載しています)

2018.08.07
チョン・スチャン『羞恥』 斎藤真理子訳
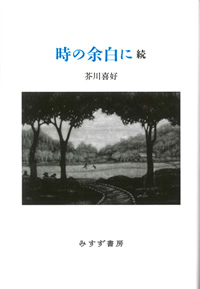
2018.07.27
芥川喜好『時の余白に 続』