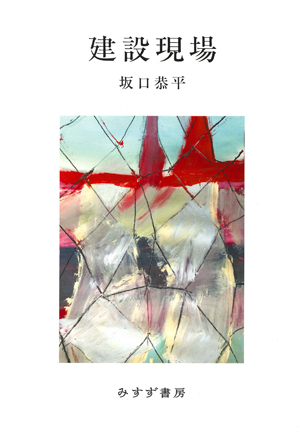
2018.10.24
坂口恭平『建設現場』刊行記念・10月20日ABC本店イベント
「書かずにはいられない」 満員御礼!
チャールズ・アフロン/ミレッラ・J・アフロン『メトロポリタン歌劇場――歴史と政治がつくるグランドオペラ』佐藤宏子訳
2018.10.15
ニューヨークのメトロポリタン歌劇場で今シーズンに上演されたオペラの映像を映画館で上映する「METライブビューイング」。60ヵ国以上の国で上映されており、日本はこの新しい試みをMETが始めた2006-07シーズンの上映8ヵ国のひとつで、この秋、13年目のシーズンを迎える。
司会進行役もオペラ歌手が務め、舞台裏のレポートや演出家、指揮者、歌手たちへのインタビューなども織り交ぜたこの「ライブビューイング」で、進行役が毎回きまって口にするフレーズがある。
「METライブビューイング」は皆さまのご寄付によって成り立っています――
世界五大歌劇場のひとつに数えられるメトロポリタン歌劇場が、なぜあんなにたびたび、観客からの寄付を呼びかけるのか。不思議に思う人も多いのではないだろうか。
歌劇場というと、国立・州立で、公の資金で設立、維持、運営されるもの――そんなイメージがある。METは、民間の個人出資者たちが共同で出資してできた国の後ろ盾をもたないオペラハウスであり、約3億ドルと言われる年間予算のうち、国やニューヨーク市の助成は数パーセントにも満たない。パリ・オペラ座やバイエルン国立歌劇場への公的補助が予算の約60パーセントを占めることを思うと、驚くべき数字だ。さらにMETがそれだけの運営資金を、チケットの売り上げと商業活動からの収益、民間企業からの寄付、そして、企業からの寄付総額をはるかに超える一般からの寄付で賄っている、と聞けば、ますます驚かずにはいられない。
メトロポリタン歌劇場への支援を惜しまない一般の観客たち。本書の著者であるミレッラとチャールズのアフロン夫妻もそんな熱心なオペラ・ゴアーとして、半世紀以上の年月をMETに通いつづけてきた。それぞれの研究専門分野は、オペラでもクラシック音楽でもない。そんな二人が数年をかけて、METのアーカイブの膨大な資料につぶさに当たり、整理を重ねることで浮き上がってきた、世界に類を見ない「民主化された歌劇場」の歴史――それに、自分たちがMETの客席で過ごしてきた時間がひとつに溶けあって、本書が生まれた。
METで上演されたことのない作品を含め、280を超えるオペラが本書には登場する。ある時代にさかんに上演された作品が、いまでは誰も思いだすこともない。と思えば、消えたと思われた作品が、ある時ふたたび命を吹き込まれて舞台の上にあらわれ、熱狂的に迎えられもする。第1次世界大戦中はワーグナーのオペラはすべてプログラムから削除された。第2次世界大戦さなかの1942-43年シーズンのオープニングは、ドニゼッティの『連隊の娘』。三色旗に代えてド・ゴール将軍率いる自由フランスのロレーヌ十字の旗が舞台に翻り、「ラ・マルセイエーズ」と「星条旗よ、永遠なれ」が演奏された。その一方で、ドイツやイタリアのオペラも上演されつづけた。それは、歌劇場の芸術に対する成熟が感じられる出来事だった。
誰もが知っている有名なオペラにしても、新演出につぐ新演出、とどまることを知らない読み替え演出によって、どれほど違う姿を見せながら、その命を保ってきたか。ひとつの歌劇場の歴史を追うなかで、オペラ作品がもつ動的な「生命力」とも言えるものが、見えてくる
とはいえ、本書の〈主人公〉はオペラの作品たちではない。タイトルロールは「メトロポリタン歌劇場」――ただの建物のように見えて、じつは人間と同じように、次々に生まれかわる細胞(歌手や演出家、指揮者にオーケストラ、経営陣に、制作に携わる人びと、そして観客……)を擁しつつ、時代時代の社会、人々の意識と呼応しながら、変わりゆくニューヨークという街のなかに130年の歴史を刻んできた。
そして、いま。そして、これから。
すべてが加速する現代に、オペラは、芸術はどんなメッセージを伝えうるか。METの歴史が、未来のオペラのありかたを描き出す。
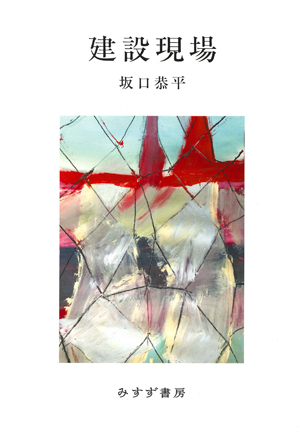
2018.10.24
「書かずにはいられない」 満員御礼!

2018.10.10
[第8回配本・全11巻]