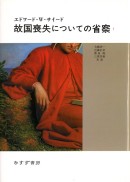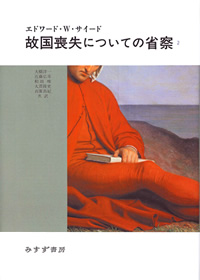トピックス
『故国喪失についての省察』 2
エドワード・W・サイード
大橋洋一・近藤弘幸・和田唯・大貫隆史・貞廣真紀訳 [全2巻・完結]
サイードの批評実践の集大成『故国喪失についての省察』の第2巻をお届けいたします。第1巻の刊行から長い月日が経過してしまいました。お待ちくださった読者の方々、ありがとうございます。ご期待を裏切らない内容になっていると思いますので、じっくりご堪能頂ければ幸いです。
ご存知のように、サイードは、単著としては3作目の『オリエンタリズム』で鮮烈な論壇デビューを果たしたのち、ポストコロニアル批評の旗手としてほとんど盲目的に崇拝される一方、それと同じくらいの批判や反感も買った人でした。サイード没後に刊行された『オスロからイラクへ』に序文を寄せているトニー・ジャットは、それをこんな風に表現しています。「これは皮肉な運命だ。崇拝者や敵たちがそれぞれ確信を持って彼のものだとした性格の、ほとんどどれにも彼はぴったりはまることはなかったからだ。生涯を通じてエドワード・サイードは、自分が関わるさまざまな主張とは、ちょっとずれたところで生きてきた」。
『故国喪失についての省察』第2巻では、第1巻に増してさまざまなトピックや人物が論じられますが、やはり全体がいくつかの問題意識によって揺ぎなく貫かれていることが分かります。それらの問題意識がなんなのかは、本書の論考を読み進むうちに、真摯に考え抜かれた思考を紡ぐとはこういうことだ、という感慨とともにあきらかになってくるでしょう。そしてまた、さきほど引いたジャットの意味するところも、なるほど、と思われてきます。
本書の終わりのほうに「敗北とは何か」という章があります。そこには、いちど「敗北した」大義も、それが真に考え抜かれたものであれば、別の場所で、別の人によって再起を果たし、それが一般性へのはずみを獲得するだろう、とあります。これが直接的に言及しているのはパレスチナ問題ですが、もちろん普遍的な意味もあるでしょう。主著に要約されるサイードの学術的業績は、敗北したどころか学問に新しい領域を切り拓き、20世紀後半でもっとも重要な学者の一人として、その名はすでに確立されているわけですが、批評家サイードが遺したものは、「別の場所で、別の人によって」、おそらく別のかたちでふたたび始まる可能性を求めているように見えます。完成品としての主著と違い思考生成の場そのものを見せる本書は、そのような可能性により開かれていると言えるでしょう。
- サイード『文化と帝国主義』 1(大橋洋一訳)はこちら
- サイード『文化と帝国主義』 2(大橋洋一訳)はこちら
- サイード『オスロからイラクへ』(中野真紀子訳)はこちら
- サイード『イスラム報道』(浅井信雄・佐藤成文・岡真理訳)はこちら
- サイード『音楽のエラボレーション』(大橋洋一訳)はこちら
- バレンボイム/サイード『音楽と社会』(中野真紀子訳)はこちら
- サイード『遠い場所の記憶 自伝』(中野真紀子訳)はこちら