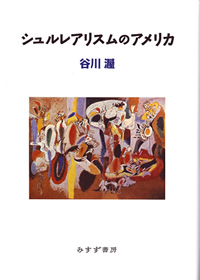トピックス
谷川渥『シュルレアリスムのアメリカ』
“生命形態的”絵画をめぐって
「つまるところ、本書はブルトンとグリーンバーグの言説を両軸として構成されるシュルレアリスム美術論であるといっていい」(本書「序」より)。
第二次大戦の勃発を機に多くのシュルレアリストがアメリカに亡命し、かれらが戦後のアメリカ美術に大きな影響を与えたことは、比較的よく知られた歴史的事実だが、これまで少なくとも日本では、その経緯を主題に据えた本は書かれてこなかった。その意味で本書は、長く待たれていた画期的な新研究であるといえよう。
本書でおもに論じられる芸術家は、順にパブロ・ピカソ、マックス・エルンスト、サルバドール・ダリ、アンドレ・マッソン、ルネ・マグリット、マルセル・デュシャン、マッタ、アーシル・ゴーキー、ジャクソン・ポロックの9人である。ごらんのように最後の2人はアメリカ人だ。とくにゴーキーは、アンドレ・ブルトンをはじめ亡命中のシュルレアリストと親しく交わり、しかも、シュルレアリスムを認めない批評家クレメント・グリーンバーグさえ「“アメリカ型”絵画」で「この国とこの時代が生んだ最も偉大な画家の一人」と呼んだように、本書の主題にとって試金石ともいえる重要な画家である。 そのゴーキーが、1945年にニューヨークで開いた個展に寄せて、ブルトンはつぎのように書いている。
- 「ぜひとも強調しなければならないのは、ゴーキーがあらゆるシュルレアリスムの画家のなかで、ただひとり、絵を描くために自然の前に陣どり、自然と直接の接触を保っていることなのだ。(…)要はある種の魂の状態を、意識としても喜びとしても、深化するためのスプリング・ボードとして働きうる感覚を自然から徴収することにある」。
一方グリーンバーグは、同じくゴーキーの個展を見てつぎのような展評を書く。
- 「以前の彼はキュビスムとポスト・キュビスムの平坦な、側面的な形態と平坦なテクスチュアの手法――スーラとセザンヌ以来、高度な絵画の多かれ少なかれ主流をなしてきた手法に執着していた。しかしいまや彼は突然、抽象的で、“生命形態的(バイオモルフィック)”なシュルレアリスム絵画のプリズム的な虹色と開かれた形態へと変化した。この新しい展開は(…)彼の作品の真面目さと力強さを弱め、彼のインスピレーションの依存的性質を際立たせる」。
評価の分かれ道は、“生命形態的”――画家のなかば無意識的な筆遣いから生じた、なにか原初的な生命の蠢きを感じさせる――形象をめぐっている。こうした形象こそが、マッソン、マッタ、ゴーキーなどを特徴づけるシュルレアリスム絵画の重要なイディオムであり、絵画におけるオートマティスムの具体例であることを、本書は鮮やかに描き出す。ちなみに問題のゴーキーの作品は本書のカバーを、マッソンとマッタの“生命形態的”作品は口絵を、ともにカラーで飾っている。ぜひ手にとってご覧いただきたい。
- ブラッサイ『語るピカソ』(飯島耕一・大岡信訳)はこちら
- ルヴァイアン『記号の殺戮』(谷川多佳子他訳)はこちら
- 『アルトー/デリダ デッサンと肖像』(松浦寿輝訳)はこちら
- 『デュシャン/大ガラス』奈良原一高写真集はこちら
- トムキンズ『マルセル・デュシャン』(木下哲夫訳)はこちら
- 村田宏『トランスアトランティック・モダン』はこちら
- 『ミシェル・レリス日記』1(千葉文夫訳)はこちら
- 『ミシェル・レリス日記』2(千葉文夫訳)はこちら