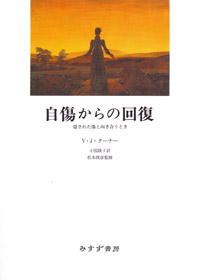トピックス
『自傷からの回復』
隠された傷と向き合うとき
V・J・ターナー 小国綾子訳 松本俊彦監修 [5月20日刊]
本書の監修者・松本俊彦医師は、以前、ある医学雑誌で以下のように述べている。
- 「自傷行為のような枝葉末節に関心を持たずに、もっと患者全体を診ていくべきではないか」。学会で自傷関連の発表をするたびに、評者〔松本氏〕は、フロアのベテラン精神科医からこういった意見に曝される。総論的には同感である。評者〔松本氏〕自身も、自傷をくりかえす患者の治療における最終的な目標とは、「切る/切らない」といったことではなく、患者自身の成長や成熟にあると信じている。けれども、各論的には異論がある。自傷行為が無視してもよい「枝葉末節」であるとは、とうてい思えない。
(「精神療法」誌、第33巻5号より)
この言葉から読み取れるように、彼は自傷行為があくまで精神障害に付随して起こる一症候としか捉えられていないことを危惧しており、なによりその「総論的」な理解によって自傷行為の治療が実際に行われていることを憂いていたのであろう。その彼が、「わが意を得たり」と邦訳作業に着手したのが本書である。本書は、自傷行為から回復した臨床心理学者が、当事者・支援者双方の視点から、回復に必要なことを綴った本である。
本書では自傷行為はアルコール・薬物依存症と同様に、「アディクション(=嗜癖)」ととらえている。自傷に依存していることを認めること、自傷したくなる気持ちをこらえる方法など、あくまで当事者の気持ちに寄りそうように回復を促すとともに、専門的な知見も申し分なく盛りこまれている。当事者・支援者が自傷に気づき、理解するためのすべてが、この本には書かれている。まずは自傷行為そのものを直視し、その真の問題を理解することが、なによりも著者そして監修者の望んでいたことであろう。
本書の中で著者は、自分が自傷に全人格的に依存し、自傷が生活をコントロールしはじめる体験を綴っている。当事者からみれば、自傷行為が自分の抱える問題の「枝葉末節」などとは捉ええないことを、本書が証明している。
手をカッターで切ったり、熱したスプーンでやけどさせたりする行為は、心の痛みの「鎮痛」のためにほかならない。アルコールならば、その鎮痛効果に思い当たる方も多いのではないだろうか。お酒に酔って、仕事の失敗や学校であった嫌なこと、家族にくりかえし言われる小言を忘れたくなる日もある……。行きすぎた譬え話かもしれないが、アルコール同様、自傷行為もけっしてまれな「鎮痛」の手段でないことにお気づきいただきたい。
- 小羽俊士『境界性パーソナリティ障害』はこちら
- 細澤仁『解離性障害の治療技法』はこちら
- セシュエー『分裂病の少女の手記』村上仁・平野恵訳はこちら
- ハーマン『心的外傷と回復』[増補版]中井久夫訳はこちら
- ヤング『PTSDの医療人類学』中井久夫他訳はこちら
- 宮地尚子『トラウマの医療人類学』はこちら
- 宮地尚子『環状島=トラウマの地政学』はこちら
- ヴァレンスタイン『精神疾患は脳の病気か?』功刀浩監訳・中塚公子訳はこちら
- ヒーリー『抗うつ剤の功罪』田島治監修・谷垣暁美訳はこちら