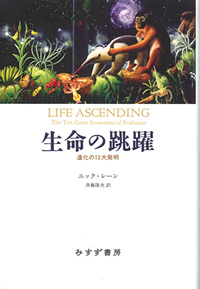トピックス
ニック・レーン『生命の跳躍』
進化の10大発明 斉藤隆央訳
よくできた「器官」だと考えられていたミトコンドリアや葉緑体が、じつは原核生物から進化したという奇想天外(!)な細胞内共生説が認められて以来、進化史における「偶然」の物語は格段に説得力をもつようになった。(そのいきさつは、ニック・レーンの前著『ミトコンドリアが進化を決めた』に詳しい。)進化の途上にはいくつかの、目を見張るような偶発的な事件があって、それが進化の道筋に、跳躍と呼ぶにふさわしい革新を与えたらしいのだ。
どんな場合でも偶然は私たちを驚かせるけれど、進化史においてはとりわけ、偶然の産物はまるで奇跡のように見える。ニック・レーンもそこに魅せられていて、進化の「偶然と必然」への驚嘆と畏敬が、『生命の跳躍』の全10章の底流をなしている。こう書くと、ジャック・モノーがずばり『偶然と必然』というタイトルの本で論じたテーマと同じものと思われそうだが、レーンの言う「偶然」は、モノーの言うそれとは異なる次元の「偶然」だ。モノーの「偶然」は、DNA上の“常に起きている攪乱”のことを指し、一方レーンの「偶然」は、ほんとうに歴史上たった一度しか起きなかったような偶発的“事件”のこと。モノー流の偶然と必然のプロセスに沿って粛々と進む進化の道行きを、レーン流の偶然が突然に、ぐいっと捻じ曲げてしまう。いや、捻じ曲げるというよりも、子どものころに絵本で読んだ、命のロウソクを接ぐ話を思い出す。死に瀕している男が死神の目を盗んで、短くなっている自分の命のロウソクに、まったく別の長いロウソクを接いでしまうショッキングな話だ。レーンの言う「偶然」はあの話のように、進化史にまったく新しい運命と可能性を接いでしまうように見える。
もっとも、別の運命を接ぐ事件が起こった後の展開は、受動的にちびていくだけのロウソクとは違う。そこが、進化の発明のまさに、まさにファンタスティックなところだ。最初の一歩は偶然でも、その先は必然性をもって、したたかに構築されていく──変異と、適応と、選択による創造のプロセス。たとえば『生命の跳躍』で描かれる眼の進化のシナリオによれば、あらゆる動物の眼の祖先となった原初の光受容細胞が生まれたのは、たった一度の“事件”だった。でもそこからレンズを備えた複雑な眼が進化する間には、方解石からミトコンドリアの集合まで、手近にあるレンズ様の物質を臨機応変に流用しながら眼の設計が発展する過程があったという。進化の「必然」の創造性も、人間のちっぽけな想像力などはるかに凌駕している。
どんなアクロバティックな偶然が、どれほど巧緻な必然が、進化の10大発明──生命の誕生/DNA/光合成/複雑な細胞/有性生殖/運動/視覚/温血性/意識/死──を生んだのか。その具体的中身は『生命の跳躍』を読んでのお楽しみ。ミクロの世界の隅々まで人の手が及ぶようになった今もやはり、生物学は涸れることのない驚きの泉だ。
- ジャック・モノー『偶然と必然』渡辺格・村上光彦訳はこちら
- カーシュナー/ゲルハルト『ダーウィンのジレンマを解く』滋賀陽子訳・赤坂甲治監訳はこちら
- A・M・ルロワ『ヒトの変異』上野直人監修・築地誠子訳はこちら
- J・S・ターナー『生物がつくる〈体外〉構造』滋賀陽子訳・深津武馬監修はこちら
- A・B・パーソン『幹細胞の謎を解く』渡会圭子訳・谷口英樹監修はこちら
- K・E・スタノヴィッチ『心は遺伝子の論理で決まるのか』椋田直子訳・鈴木宏昭解説はこちら
- J・ルドゥー『シナプスが人格をつくる』森憲作監修・谷垣暁美訳はこちら
- J=P・シャンジュー『ニューロン人間』新谷昌宏訳はこちら
- ヴァンダーミーア/ペルフェクト『生物多様性〈喪失〉の真実』新島義昭訳・阿部健一解説はこちら
- フランソワ・ジャコブ『ハエ、マウス、ヒト』原章二訳はこちら