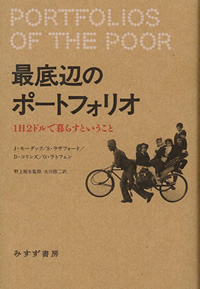トピックス
『最底辺のポートフォリオ』
1日2ドルで暮らすということ
ジョナサン・モーダック/スチュアート・ラザフォード/ダリル・コリンズ/オーランダ・ラトフェン 野上裕生監修・大川修二訳
マイクロクレジットについて、多重債務で自殺が増えているとか、色々きくけれど、実際のところ役に立っているのだろうか? そんな疑問に答えるのが本書。
マイクロクレジットの実態について知ろうとすれば、当然、最貧困にある人々が置かれている金融環境を知る必要がある。本書の基礎になっているのは、バングラディシュ、インド、南アフリカで、1年にわたって「お金のやり繰り」を聴き取った〈ファイナンシャル・ダイアリー〉と呼ぶ詳細な調査結果だ。その1例を見てみよう。
「サイフルとナルギスは若い夫婦で、小さな子どもが2人いた。彼らは読み書きができなかった。土地は所有しておらず、サイフルが自分で建てた小屋に住んでいた。サイフルは可能なときには地元の農場で働いていたが、その他のときはリキシャのドライバーとして雇われていた。農場で働くと、1日あたりおよそ80セント分の穀物と70セント程度の現金がもらえた。リキシャの仕事のときには、1日あたり1ドルから1.50ドルの稼ぎがあった。平均すると、1カ月に22日ほど働いていたことになる。この世帯はバングラデシュのサンプルのなかの最貧困層に含まれていた。上の子どもは学校に通っていたが、下の子どもはまだ赤ん坊だった。夫妻は2人とも体が丈夫で、ほとんど病気をしたことがなかった……」
このような聴き取りから、彼らのキャッシュフローとバランスシートを書き起こし、実際のお金の流れを把握したのがこの研究だ。
さて、ここから見えてきたマイクロファイナンス、そして、最貧困層をとりまくインフォーマル金融の実態とは? 雑誌記事などではとてもカバーできない、そのややこしく複雑で、しかもエレガント(!)な金融の姿を、初めてまとめて紹介します。
- 中村雄祐『生きるための読み書き――発展途上国のリテラシー問題』はこちら
- ベルーベ『ナノ・ハイプ狂騒』上 五島綾子監訳・熊井ひろ美訳はこちら
- ベルーベ『ナノ・ハイプ狂騒』下 五島綾子監訳・熊井ひろ美訳はこちら
- 川端清隆『アフガニスタン――国連和平活動と地域紛争』はこちら
- 斉藤道雄『治りませんように――べてるの家のいま』はこちら
- クラインマン他『他者の苦しみへの責任――ソーシャル・サファリングを知る』坂川訳・池澤解説はこちら
- ブライアン・アーサー『テクノロジーとイノベーション――進化/生成の理論』有賀監修・日暮訳はこちら
- デュフロ/バナジー『貧乏人の経済学』山形浩生訳[2月刊行予定]近刊情報はこちら