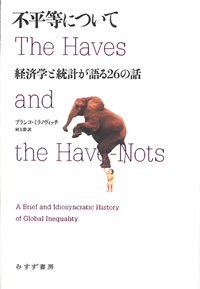トピックス
B・ミラノヴィッチ『不平等について』
経済学と統計が語る26の話 村上彩訳
本文より。
「カーネギー所有のUSスチール株は2億2500万ドルだった。〔古代ローマの〕クラッススの場合と同じく金利6パーセントとして、これに1901年当時の米国の1人当たりGDPである282ドルを付き合わせると、カーネギーの所得はクラッススを上回るという結論になる」
「崩壊当時のソヴィエト連邦は、その国境内に所得レベルが韓国とコートジボワールほども大きくかけ離れた諸国を抱える集合体だった。国家の団結を固めるためには、最も貧しい構成国の利益になるような広範囲に及ぶ再分配が必要であり、これなくしてソヴィエト連邦のような統一体が存在することはできなかったのではないだろうか」
「世界の人々の所得は二つの要因から説明できることになる。…すなわち国籍と、両親の所得階層だ。この二つの要因だけで個人所得の80パーセントを説明できる。したがって残りの20パーセント弱が他の要因によることになる」
「現在の米国大統領の祖父は、所得が自分の66倍もある人々の下男やコックとして働いていた」
「米国では、不平等は個人の問題である。EUでは、不平等は国の問題である。したがって、不平等と貧困に取り組む政策もまた、米国とEUとでは当然異なる。米国では居住場所を問わず、貧しい個人を対象とした社会政策が実施されている。一方EUでは、「結束」政策と呼ばれる社会政策が、貧しい国や地域(例えばイタリア南部)を対象に実施されている。なぜなら、それらの地域や国には、不釣り合いな数の貧しい人々が存在するからだ」
不平等の「小ねた」集へ、ようこそ。
- バナジー/デュフロ『貧乏人の経済学』山形浩生訳はこちら
- モーダック/ラザフォード他『最底辺のポートフォリオ』野上裕生監修・大川修二訳はこちら
- ポール・コリアー『収奪の星』村井章子訳はこちら
- 中村雄祐『生きるための読み書き』はこちら
- クラインマン/ファーマー他『他者の苦しみへの責任』坂川雅子訳・池澤夏樹解説はこちら
- ブライアン・アーサー『テクノロジーとイノベーション』有賀裕二監修・日暮雅通訳はこちら