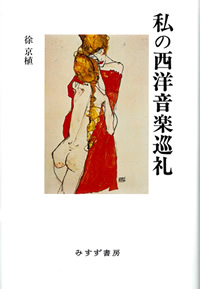トピックス
徐京植『私の西洋音楽巡礼』
小社刊行の『私の西洋美術巡礼』『汝の目を信じよ!』はじめ、在日として生きてきた軌跡と時代批判がみごとな言葉に結晶化した徐京植の文章は、重く、深く、読む者に思考と反省をうながし、開かれた世界に導いてくれるものである。韓国のインターネット・メディア「ナビ」にまずは連載された本書もまた、そういう一書である。クラシック音楽を主題としながら繰り広げられるその書きぶりは、重厚かつ重層的といってよい。しかし、本書の特徴をしるすとき、どうしても「重くて軽みのある」「軽みがありかつ重い」という背反的な表現になってしまう。なぜか。それは本書全編に登場するFの存在だ。「Fというのは、私にとって同伴者であり、友人であり、妻であり、時には娘のようでもある女性のことだ」。たとえば――
〈Fと親しくなってから、私は彼女に「ぼくの葬式は無宗教が望みだ。ただ、フォーレの《レクイエム》だけが静かに流れるといいけれど……」と言ってみたことがある。「死ぬなんて、いやや」と言うか、あるいは、「うん、かならずあなたの言うとおりにする」と答えるのではないか。感動のあまり泣き出したらどうしよう? そう思った。私はまだFという人間をよくわかっていなかったのだ。彼女はいかにも疑わしそうに「ええ? フォーレ?」と言ってから、声をあげて笑い出した。葬式にフォーレというのは、彼女からみれば、あまりにもステレオタイプだったのだ。それに、そもそも自分の葬式を演出しようという私の自意識過剰を笑ったのである。私は少し不機嫌になって、黙り込んだ。そんな私を気にかけることもなく、Fは笑いながら「あれのほうがええわ」と言葉を継いだ。「ほら、ティンゲリーのお葬式」〉
〈2001年の夏、私とFはザルツブルク音楽祭で、サイモン・ラトル指揮、ウィーン・フィル演奏のマーラー《交響曲第5番》を聴いた。演奏終了後、私は、いったいこの音楽は何を伝えたいのだろうか、と考えていた。マーラーのような大作曲家の作品を一流の指揮者と最高の楽団で聴いて、しかも演奏には破綻がなく、部分部分は美しいのに、こんなにも感興が薄いのはなぜなのか、納得がいかなかった。作品の発する一貫したイメージというものが見えないのだ。「どうだった?」とFが尋ねるので、首をかしげながらそのことを言った。Fはもどかしそうに、「一貫したイメージなんか要らんの。何事につけ、整然とした論理とか、必然的な結論を求めるのはあんたの悪い癖や」と言った。まだ納得できないでいる私に彼女はたたみかけた。「あのジョイント(joint)がええのよ。ジョイント、わかる?」「ジョイント? わからんね……」「いろいろなテーマやばらばらな各部分を繋ぐジョイント。マーラーはそのジョイントが絶妙なんよ」〉
自分の生い立ちや家族のこと、アウシュヴィッツ訪問、作曲家や曲についての縦横な分析や時代批判とならんで、なんとも微笑ましい(?)Fとのやりとりが本書を包んでいる。巻末には「オペラ編」「声楽と管弦楽編」の「私とFのベストスリー」の対談も付いています。
- シェング・スヘイエン『ディアギレフ』鈴木晶訳はこちら
- アンドレ・シェフネル『ドビュッシーをめぐる変奏』山内里佳訳はこちら
- 奥波一秀『クナッパーツブッシュ』はこちら
- エーファ・ヴァイスヴァイラー『オットー・クレンペラー』明石政紀訳はこちら
- チャールズ・ローゼン『音楽と感情』朝倉和子訳はこちら
- ジャック・アタリ『ノイズ――音楽/貨幣/雑音』金塚貞文訳・陣野俊史解説はこちら
- ノルベルト・フライ『1968年――反乱のグローバリズム』下村由一訳はこちら