
2013.11.11
『精神分析を語る』
藤山直樹・松木邦裕・細澤仁
歴史・文学・哲学はどう応答したか 田尻芳樹・太田晋訳
2013.10.25
〈ホロコーストは「私たちのありよう」と「私たちにとっての世界のありよう」を変えたというのは決まり文句である。けれども、この決まり文句が本当のところ何を意味しているのか、ホロコーストの後でどんな世界が明るみに出たのか、を考えつめることはもっと難しい。〉(本書より)
ホロコーストの後でどんな世界が明るみに出たのか。
暴力という言葉では十分に言い表すことができない、ホロコーストという出来事を考えること。それが思想の役割だと著者イーグルストン氏はいいます。
といっても、私たちの世界が今まで何も考えてこなかったということはなく、むしろ、ホロコーストの証言、ホロコーストを題材にしたフィクション、哲学、歴史記述は大量に存在し、今も世界中で生みだされています。
しかし、それらに取り組むまさにその過程で、私たちが陥りがちな思考のパターンを本書は指摘します。
思想においては、自らにとっての他者を同化する思考。文学においては、読むことで同一化する働き。歴史においては、客観的・中立的な記述を求める過程で起こる標準化。哲学においては、限界と解決を求めること。
イーグルストン氏は非常に明快に、問題点を腑分けして追求していきます。
ホロコースト体験を「読む」とはどういうことか。犠牲者に同一化するのはよいことか。読むことと責任の関係は。
〈間違いなくこの主題に関する決定的な仕事であり、今後長い間そうであり続けるだろう。歴史と歴史記述に関してはもちろん、ホロコースト関連文献、そしてポストモダン小説・批評に関する彼の知識の幅広さと奥行きはまさに驚くべきものである。きわめて重要な本だ〉(“Choice”誌)
608ページの大著ですが、記述は明晰そのもの。厚さに似合わずめげずに読み進めることができると思います。
私たちが直接体験していない、同一化できない死の記憶をどう継承するのか。ホロコーストへの絶えざる応答から思想の可能性を引き出す決定的な一書です。

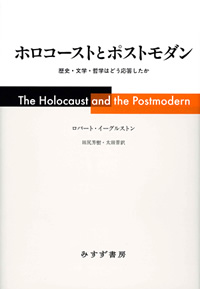

2013.11.11
藤山直樹・松木邦裕・細澤仁
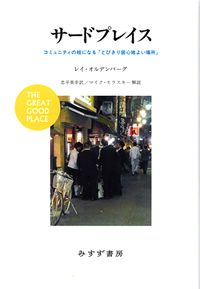
2013.10.25
コミュニティの核になる「とぴきり居心地よい場所」 忠平美幸訳 マイク・モラスキー解説