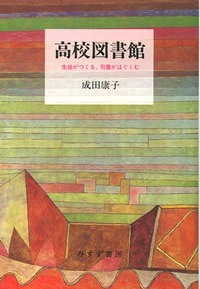
2013.11.11
成田康子『高校図書館』
生徒がつくる、司書がはぐくむ
藤山直樹・松木邦裕・細澤仁
2013.11.11
僕にとって精神分析というのは、こころの臨床をする上で一番本物っぽいっていうか、一番その人の全体性というものを相手にしている感覚があるものかなと思いますね。精神分析っていうのは、ひとつのまとまった文化なんですよ。
医療というのは、まず患者の苦痛を減らさなければいけない。でも薬で十分よくなる人って患者全体の三割か四割なんです。あとの患者さんには「生きにくさ」があって、その人たちが精神分析を求める、ということなのでしょう。
僕にとって精神分析は芸術と似ているんですよね。精神分析も芸術も、社会に直接役に立つものではないけど、人間の真実と出会えるものであり、それを特別に必要としている人も少数ながら存在すると思っています。
ジークムント・フロイトがヴィルヘルム・フリースとの自己分析体験を経て、はじめて「精神分析Psychoanalyse」という言葉を使ったのは、1896年と伝えられている。それから一世紀以上の時が過ぎ、私たちを取り巻く環境が一変した今日、精神分析は何をもたらし、どこへ向かっていくのか?
日本精神分析学会の現会長・藤山直樹、同前会長・松木邦裕、そして両氏に学び、解離性障害の精神分析的臨床で知られる細澤仁。この三氏が集い、10時間を超える対話のなかで生まれたのが本書である。
細澤氏は医学部に進む前に抱いていた精神分析への想いを、本書の冒頭で次のように語っている。
実のところ、数年前まで編集担当者もまったく同感だった。
これまでに精神分析臨床に関する本を何冊か担当してきたが、そのたびに登場する独特のボキャブラリー群やこころの動きの描写を前に、普段とは違う頭の部分を使い、校正をしているうちに違う世界へ行かなければならない感覚があった。こんなに浮世離れ……いや、こんなに高尚な治療法があるのかと、まさに先の細澤氏のように日本で実践している人がいるのだろうか? と思ったものである。
しかし、三氏の対話に同席しているうちに気づかされた。精神分析は金持ちの道楽でも、心理療法の一形態でもない。精神分析とは、生き方なのだ。患者の生活の中に何年も共に存在し、同じものを見つめていく。そんな生き方が、精神分析臨床家と呼ばれているのである。
本書のなかで語られる私史によれば、三人の臨床家は素朴な動機と出会いのめぐり合わせによって精神分析臨床の世界へと誘われている。
ひそかに細澤氏や編集担当者と同じように感じて精神分析臨床と距離をおいていた専門家の方、そしてこれからこころの専門家を目指す方にも、まずは本書の三つの生き方に触れてみていただきたい。
あるいは本書が、読者を精神分析臨床の世界へと導く出会いになるかもしれない。
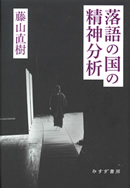

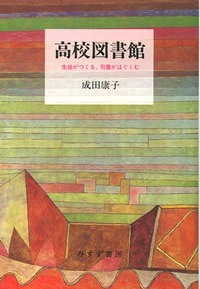
2013.11.11
生徒がつくる、司書がはぐくむ
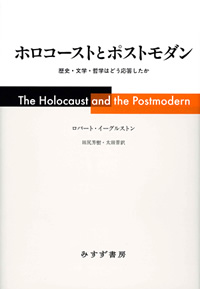
2013.10.25
歴史・文学・哲学はどう応答したか 田尻芳樹・太田晋訳