
2016.03.10
「現代の監視が身体の内奥へと向けられ…」(高野麻子「あとがき」)
高野麻子『指紋と近代――移動する身体の管理と統治の技法』
斉藤道雄『手話を生きる――少数言語が多数派日本語と出会うところで』
2016.02.29
〈「病気や事故のせいで、それまで耳の聞こえていた人が聞こえなくなってしまうことがあります。そういう人は、途中から聞こえなくなった人、っていう意味で中途失聴者っていうの」
「じゃあ、ろうが聴になることもあるの? 病気やなんかで、ろうが聞こえるようになるってことが?」
「それはないんじゃない? 耳の聞こえない人が病気になって聞こえるようになったなんて話、先生は聞いたことがないなあ。だから、ないと思うよ」
そうかぁ。よかった……
「じゃ、ある日突然、あたしが聴になるなんてことは、ないんだよね」
もういっぺん聞いたら、先生は笑いながら答えてくれた。
「だいじょうぶ、そんなことないから」
安心した。聴になったらどうしようって、ちょっとドキッとした。
あたしはろうのままでいられる。
あたしたちは顔を見あわせ、うなずきあった。みんな聴になるなんてことないんだ。〉
(『手話を生きる』冒頭「二つの世界」より)
日本という国の中の「少数言語」=日本手話。日本語とは異なるその言葉を母語として自由にあやつり、異なる文化を生きる、圧倒的少数者の話者――それがろう者・ろう児と呼ばれる人びとだ。その日本手話で授業を行い、手話と日本語のバイリンガル/バイカルチュラル教育を実践する日本初にして唯一の学校、明晴学園の校長を創立から5年間つとめた著者は、TBS報道局の記者・ディレクターとして手話とろうの世界に足を踏み入れました。
1993年、世界で唯一のろう者の文科系総合大学、ワシントンのギャローデット大学を訪ね、手話は言語であること、そして、ろう者とは手話という異なる言語と異なる文化を生きる少数派の人びとであることを目の当たりにした著者は、手話のテレビ・ドキュメンタリーをつくりながら、以来20年にわたって、英語や日本語とおなじ豊かさをもつ手話という言語の力を言語学という科学に照らしてたしかめる作業をかさね、やがて、明晴学園の前身であるフリースクール龍の子学園の立ち上げに関わってゆくことになります。
ろう者の立っている場所、聴者の立っている場所。そのどちらとも違う場所に、著者は足をしっかりと据えています。ろう者も書かない、聴者も書かない、誰も何も書かないままにしておいていいのか……その思いから、本書は生まれました。ろう教育の歴史、手話という言語が乗り越えてきた、そして今も向き合っている困難、欧米の事例や研究成果。日本手話と人工内耳をめぐる状況や、言語学からみる手話……手話をめぐるさまざまがシームレスにつながり、そのすべてが「手話を生きる」子どもたちのことばによって支えられています。
人間にとって母語は、まさに母親につつまれているような安心感とやすらぎであり、しっかりと揺るがない土台であるといえるでしょう。地球のあらゆる場所で生き延びてきた少数言語とおなじく、多くの話者をもたないけれど、そうした言語のひとつとして、豊かな表現と歴史をもった手話の今、そして未来。
聞こえないこと。それは、必死に受容し、絶え間ない努力によって乗り越え、克服すべき障害ではない。
ろうでいい、ろうがいい――

出版情報紙『パブリッシャーズ・レビュー みすず書房の本棚』2016年3月15日号の第一面に、鷲田清一氏(哲学)よりお寄せいただいた書評エッセイ「深すぎた溝を越えて――斉藤道雄『手話を生きる』を読む」を掲載しています。

2016.03.10
高野麻子『指紋と近代――移動する身体の管理と統治の技法』
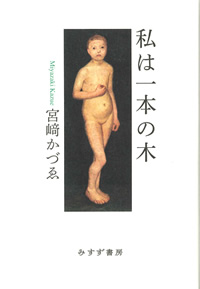
2016.02.10