
2017.02.15
哲学的肖像にして土方巽論の集大成
宇野邦一『土方巽――衰弱体の思想』
ジョーゼフ・ケアリー『トリエステの亡霊――サーバ、ジョイス、ズヴェーヴォ』鈴木昭裕訳
2017.02.10
はじめて訪れたトリエステ。夜中に到着したホテルでの朝食のとき、ボーイが急ぎ足で出たバルコニーに「私」も出て、おもわず声をあげる。
「サバが愛したトリエステ。重なりあい、うねってつづく旧市街の黒いスレート屋根の上に、淡い色の空がひろがり、その向こうにアドリア海があった。そして、それらすべてを背に、大きな白い花束のようなカモメの群れが、まるく輪をえがきながら宙に舞っている。しわがれた騒々しい啼き声は彼らだった。(…)サバがいたら。私は大声で彼の名を呼びたかった。朝の光のなかに、この金色の髪を風になびかせ、カモメとたわむれる長身の青年を見て、詩人はなんといっただろう」(須賀敦子『トリエステの坂道』)
須賀さんの、コルシア書店をめぐる文章でミラノを感じたのと同様に、こうしてわたしたちはトリエステを感覚的に知ることができた。ウンベルト・サバ(サーバとも)の詩を読んでみたい。その一心で翻訳をお願いした。未完のかたちで残された『ウンベルト・サバ詩集』の刊行は亡くなった年の夏になったが、それから20年が経とうとする今でも熱心な読者にめぐまれている。
イタロ・ズヴェーヴォの名をわたしたちが知ったのは、集英社版『世界の文学』「ジョイス/ズヴェーヴォ」によってではないか。一巻の半分以上を占めるズヴェーヴォの長編小説『ゼーノの苦悶』(原題は『ゼーノの意識』)は、精神分析医のすすめで書かれた回想録のかたちをとって、みずからのニコチン中毒の原因を探る「禁煙小説」である。「これが最後の一本だ!!」という主人公ゼーノの歓声と、禁煙した喜びのあまりタバコを喫ってしまうすがたに、大きくうなずいた読者は多かった(ほんとかね)。
今は亡き『批評空間』に連載されていたリチャード・クラインの『煙草は崇高である』でこの作品が大きく取り上げられ、ズヴェーヴォは一部マニアの注目を浴びる。前述の『世界の文学』で解説を読んでいれば、トリエステでズヴェーヴォに英語を教えていたのが、『ユリシーズ』を書きはじめたジェイムズ・ジョイスであり、『ゼーノの意識』を絶賛して出版に努力したことを知っていた。
『ユリシーズ』の主人公レオポルド・ブルーム。「ジョイスさん、スティーヴン・ディーダラスの相手がユダヤ人であるのは分かりますが、なぜハンガリー人の息子なんですか?」と問われたジョイスは眼鏡を取って、さりげなく、しかしきっぱり「実際そうだったからですよ」と言った。ジョイス伝のリチャード・エルマンはこのやりとりを踏まえて書いている。「原型はほぼ間違いなく、ハンガリー人の祖父を持ち、ブルームと同じ口髭を生やし、ブルームと同じように妻と娘のあったエットレ・シュミッツである。」エットレ・シュミッツはイタロ・ズヴェーヴォの本名。
そして、ジョイス。ジョイスは英語教師だったトリエステ時代に、弟スタニスロースが漕ぐニードルボートを一篇の詩にしている。「小舟の若者がきらめくオール越しに/恋にむかって叫びかけるのを聞いた/「もはや、もはや帰らぬ!」」(丸谷才一訳)。場所はトリエステの南にあるサン・サッバ。後にナチスが運営するイタリアで唯一の絶滅収容所があったところ。もちろん『ジアコモ・ジョイス』はトリエステで生まれた。女子生徒との親密な関係を夢見て書かれたこの作品について、エルマンは解説する。「豊かでもあり不毛でもある、逢瀬のエロチックな興奮とアイロニカルな喜びが語られ、彼は、この女がユダヤ人の娘として暗い東から来て、彼の西の血を支配するのを思い描いている。」
サーバ、ジョイス、ズヴェーヴォ。同時代のトリエステに存在していた三人が描き出す三角形。それを求めて、『トリエステの亡霊』の著者ケアリーは現代のトリエステに滞在する。「街を、端から端まで」(サーバ)通り抜ける。ケアリーは1927年生まれだから、エルマンの一回り年下、須賀さんより二歳年上である。三人の亡霊を追う探索者はやがて自分自身も亡霊になってしまうのか?
現在はイタリア北部の港湾都市トリエステの、複雑な歴史と文化のなかに暮らし、この町でなければありえない文学を生み出した人々がたしかにいた。忘れ去られようとするものに向けられた異様な情熱が、この一巻に凝縮している。翻訳は1990年代に白水社からタブッキやバリッコの作品を出していた鈴木昭裕。「本でできた町の謎にみちた物語」で、めくるめく小旅行をしていただきたい。

2017.02.15
宇野邦一『土方巽――衰弱体の思想』
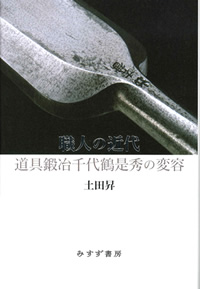
2017.02.10
土田昇