
2019.09.05
ロン・リット・ウーン『きのこのなぐさめ』 枇谷玲子・中村冬美訳
2019.08.27
中華系マレーシア人で現在はノルウェーに暮らす著者のロン・リット・ウーンさん。交換留学生としてやってきたノルウェーで建築を学ぶエイオルフ・オルセンさんと出会い、図書館でデートを重ね、夫婦となった。活動的で自分を律するのが得意な太陽のようなウーンと、物静かで自由を愛する月のようなエイオルフ。30年以上、二人は深く愛しあい生活を共にしてきた。そのエイオルフが、ある日、突然死んでしまう。奈落の底に突き落とされ、暗闇の中でうずくまるようにして時間を過ごす毎日だった彼女が、ふとしたきっかけで参加したのが、エイオルフといつか行ってみようと言っていた、きのこ講座だった。彼女は、現実世界とパラレルに存在するきのこワンダーランドの存在を知り、この国へ旅に出てみたいと思う。
『きのこのなぐさめ』ブックトレーラー(動画の画面上の三角の印をクリックすると再生が始まります。さらに全画面表示にもできます。動画がうまく再生されないときは、次のURLよりごらんください。https://www.youtube.com/embed/ZxOB7quKZ68)
きのこ王国をめぐる旅が彼女の心の痛みをどのようにやわらげ、傷を癒し、再生へと導かれていったかは、物語を読んでいただければと思う。心の回復のときを迎えた彼女は、さらに前へと進む力を得て、きのこへの恩返しともいえるこの作品『きのこのなぐさめ』を書き上げた。そして、きのこのマジックは彼女を、さらに広い世界への旅へと連れ出している。
デンマーク、ドイツ、オランダ、スウェーデン、フランス、フィンランド、アメリカ、イギリス、スペイン、そして日本…本書は、次々とさまざまな国で翻訳刊行され、その他の言語の翻訳も進行中。刊行された国々では、「ユニーク」「心がこもっていて正直」「深い」などなど、全くユニークな本として評判を呼んでいる。作品をとりまく話題を、訳者のひとり、枇谷玲子さんが詳しくレポートしてくれているので、ぜひご覧いただきたい。
この本には、きのこワンダーランドと、もうひとつ、自身の内面世界を彷徨う旅の二つが並行して描かれている。「現実」と思っていた世界が、予期せぬ力によって、突然、変容してしまった人にとって、世界という風景は、いままでとは違うものに見えてくる。この作品の真のテーマである、人間(認識)の再生の過程について、どのように描かれているのか、もう一人の訳者・中村冬美さんが一文をあらわしておられるので、こちらもぜひ本書を読むときのガイドにしていただければと思う。
『きのこのなぐさめ』はいろいろなきのこについて描いた自然の本でありながら、作家ロン・リット・ウーンが、夫を亡くした苦しみと絶望から少しずつ再生していく、グリーフケアの本でもあります。
本文の中では絶望から立ち直っていく様子を表す、キーワードがいくつか使われています。それは時には匂いといった感覚であり、時には眠りです。なかでも、心の様子を表すキーワードとして多く使われているのは、「光」です。
ここで、本書に出てくる「光」の表現を幾つかご紹介したいと思います。
最愛の夫エイオルフをある朝突然失った主人公は、初めのうちはただただ絶望していて、視界が悪く、どちらに歩いていっていいかも分からない、暗い絶望の世界にいます。
その後ふとしたきっかけから、きのこの世界に足を踏み入れた彼女は「日が暮れた後の森の小道を照らしてくれる」光を放つきのこに出会います。夜光性のきのこの光ですから、ぼうっとした淡い光でしょう。
ストーリーが進むにつれて、森へ入っていき、きのこ狩りを通して魂にまっすぐに差し込んでくる「細い金の光線」をその身に受けます。それは彼女自身が、再び自分の人生に、細いながらも光を招き入れた瞬間なのではないでしょうか。
44ページの病院の礼拝堂のシーンや101ページのフランシスコ・イェルペン‐愛する人を亡くした人々の集う自助グループ‐のシーンでは、厳かなろうそくの光がモチーフとなっています。
ストーリーの後半では、彼女はきのこ鑑定士試験に合格していて、それまではきのこの専門家について森へ連れていってもらう立場だったのが、自分がきのこの初心者を引率して森へと連れていく立場になっています。
すると森で目にするのは、「まだらに揺れる光のパッチワークの世界」です。だんだんと身体に注がれる光の量が増えているのです。
終盤になって、284ページでは、ノルウェー国内にはもう生息していないと思われていたサルコソマ・グロボスムSarcosoma globosumを見に、きのこ巡礼の旅に出ます。このきのこはゴブレットのような形をしていて、「早春の陽光を取り入れるのにほぼ完璧なデザイン」です。この頃には主人公は、まさに早春の陽光を心に取り入れようとしていたのではないでしょうか。
そして301ページ、「閉じられていた心のロールカーテンはさっと上がり」陽光は主人公の上に降り注ぎます。そればかりか彼女は「光の方に出て、小道を歩きながら砂利の音に耳を傾け」、最後には朝日の射す暖かなウッドテラスで朝食を食べるのです。
これらの光の表現は、本文の流れを壊すことなく、それぞれの文章の中できちんと意味を持って出てくるので、深く考えなければそのまま読み流してしまうでしょう。けれども後からこの本の印象を思い返すと、美しい宝石のきらめきのように、随所随所を彩っています。小道にポツポツと、きのこが顔を出しているように。
読者のみなさまは作家の心の動きとともに、暗い暗い砂漠から深い緑の森を通り、やがては陽光の降り注ぐ春の農園へと長い旅をしたような気分を味わうのではないでしょうか。

2019.09.05
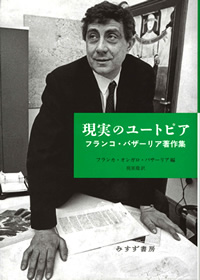
2019.08.26
『現実のユートピア――フランコ・バザーリア著作集』 F・O・バザーリア編 梶原徹訳