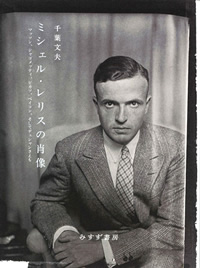
2019.10.29
ミシェル・レリスとは何者だったのか
千葉文夫『ミシェル・レリスの肖像――マッソン、ジャコメッティ、ピカソ、ベイコン、そしてデュシャンさえも』
カロリン・エムケ『なぜならそれは言葉にできるから』浅井晶子訳
2019.10.23
暴力をうけた人は、それを話すことができるだろうか。周囲の人はそれを聞けるだろうか。なぜ暴力は人を黙らせ、それは何を意味するのだろうか。
カロリン・エムケは、戦争で荒廃した国を長年旅している。そして旅で出会った人に、幾度も、かれらの経験を書きとめることを求められる。
なぜ、その人たちは語ることができなくなり、そして、聞くこと、伝えることを求めたのか。そこからエムケの思索がはじまる。
「いや、新しい靴を買っていったんですけどね」と、アデムはエムケに語った。1998年、ドイツからユーゴスラヴィアに送還され、そこで拷問を受け、再びドイツに送還された経緯を話していたときのことだ。「傷がついたレコードに落とした針さながら、アデムの話は常に同じ場所で軌道から外れた」。アデムの靴の話を、かけだしのジャーナリストだったエムケは記事にしようとしたが、記事は採用されなかった。
2001年9月11日、ワールド・トレード・センターの73階から逃げ出したジョーは、壮絶な体験を語る合間に、エムケに奇妙なことを言う。「僕のコーヒー、まだ机の上にあるはずなんだ」。
このような言葉が重要なのではないかと、エムケは考える。
自らの受けた暴力を語るときによく求められる、二つのことがある。ひとつは語りの首尾一貫性。それがないと証言は信用できないとみなされることが多い。もう一つは逆に、「語りえない」ということ。エムケはどちらにも反対する。暴力をうけた人が世界から切り離されてしまわないように、私たちにはまだできることがあるのではないかと。
暴力をうけた人が語るとき、そこには空白や断絶がある。語りの首尾一貫性ではなく、「それ」を聞くことが、世界への信頼を打ち砕かれた人が、世界へと戻ってこられる鍵になるのではないだろうか。
本書は、タイトルとおなじ「なぜならそれは言葉にできるから」という長いエッセイと、それに連なる短いエッセイからなっている。なかでも「旅をすること」は、自分の部屋から紛争地に出かけていくときの話や、両親との思い出など、どこか繊細で静かなエムケの姿がみえてきて、ここから読み始めたり、途中で立ち戻るのもいいのではないかと思う。
(編集担当:鈴木英果)
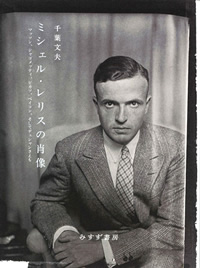
2019.10.29
千葉文夫『ミシェル・レリスの肖像――マッソン、ジャコメッティ、ピカソ、ベイコン、そしてデュシャンさえも』
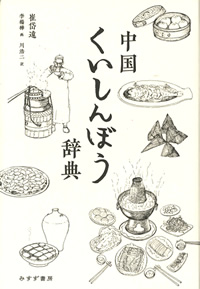
2019.10.23
崔岱遠『中国くいしんぼう辞典』 李楊樺画 川浩二訳