
2020.01.24
イギリス人も知らなかった「イギリスらしさ」
ケイト・フォックス『さらに不思議なイングリッシュネス――英国人のふるまいのルール 2』北條文緒・香川由紀子訳
岡田温司『映画と黙示録』
2019.12.20
地球が悲鳴を上げている。温暖化が原因で巨大化し進路も変えた幾つもの台風が各地で猛威を振るい、甚大な被害をもたらした今年ほど、そのことが身にしみて感じられたことはない。今後ますますこの傾向が強くなっていくことも予想される。
つい先ごろ世界のマスコミをにぎわした、弱冠十六歳のスウェーデンの少女の渾身の叫びは、この地球の悲鳴を代弁しているようにも聞こえる。彼女の訴える「絶滅の始まり」には、伝統的な「黙示録」の啓示と、新たな地質年代として提唱されている「アントロポセン(人新世)」の思想とがこだましているように思われる。たしかに、世界中の若い世代が広く彼女に共鳴し、現状をいっそう深刻に受け止めようとしているのもうなずける話である。いったい、人類はいつまで豊かな発展の妄想を抱きつづけ、自分たちだけが生き残ろうと欲望しつづけるのだろうか。未来の世代に計り知れない負債を押しつけることになるというのに。
「序」でも書いたことだが、小さなアポカリプス、あるいは弱いアポカリプスとも呼べるような光景が、わたしたちのまわり、とりわけネット上に氾濫している。T・S・エリオットの名高い詩句に借りるなら、「こんな風に世界は終わる/こんな風に世界は終わる/こんな風に世界は終わる/爆音ではなくて、すすり泣きとともに」が、ほぼ日常化しているとすらいえるかもしれない。その一方で、冷戦時代の終わりにいったんは沈静化したかにみえた核の脅威が、新たな政治地図とともに近年改めて表面化しつつある。つまるところ、「すすり泣き」と「爆音」の両方ともが現実なのである。
「黙示」において表象は、「爆音」と「すすり泣き」、閃光と暗闇、炸裂と消尽、過剰と不在という、両極性をはらんだ事態に直面させられる。さらに、希望と恐怖、救済と懲罪、ユートピアとディストピアという対をここに加えてもいいだろう。もちろん、テクノロジーもまた両価性をもっている。ポスト黙示録の想像力において、テクノロジーは破壊者でもあれば救済者でもありうる。小著の六つの章は、欧米の黙示録的な映画が、「爆音」と「すすり泣き」のあいだをいかに揺れ動いてきたかを示す試みであった、と最後にまとめることができるかもしれない。いずれにしても、希望にあふれる未来や、一部の強者や富裕者のサバイバルといった筋書きは、本文でも見てきたように、たとえそうした映画がなおも製作されつづけているとしても、もはやわたしたちの心を動かすことはないだろう。
私事にわたって恐縮だが、ここのところ立てつづけに映画についての本を、主に美術やキリスト教との関連から書いてきて、これが四冊目となる。思い返すに、ほとんど半世紀近くも前、中学生のころから大学まで、まるで取り憑かれたように映画を見てきて、その後、長らくその欲望に蓋をしてきたのだが、今や人生の暮方にかかって、その蓋を少し開けてもいいのではないかと考えるようになった。映画を専門にする研究者の方々には、いかにも素人臭いと危ぶまれる記述や分析もあるに違いなかろうが、美学や哲学はもちろん、美術史や芸術学でさえ、わたしは自分が専門家であると思ったためしはいちどもない。アガンベンはその自伝的エッセー『書斎の自画像』のなかで、自分のことをいみじくも「エピゴーネン」と呼んでいる。おこがましいのは覚悟のうえで、このひそみに倣うなら、わたしは自分を「ディレッタント」と呼んでおきたい。
Copyright© OKADA Atsushi 2019
(著者のご同意を得て転載しています)

2020.01.24
ケイト・フォックス『さらに不思議なイングリッシュネス――英国人のふるまいのルール 2』北條文緒・香川由紀子訳
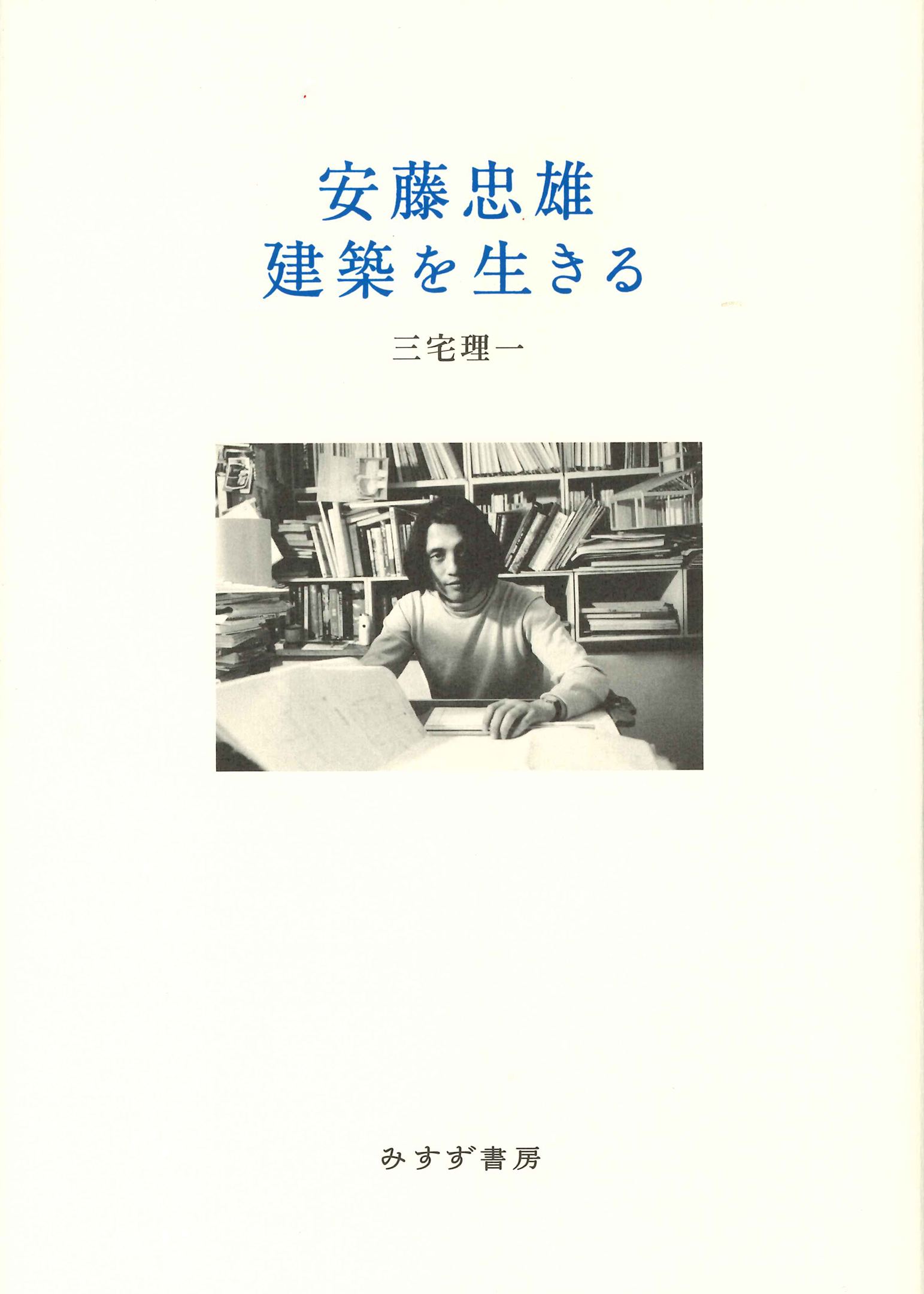
2019.12.20
三宅理一『安藤忠雄 建築を生きる』[24日刊]