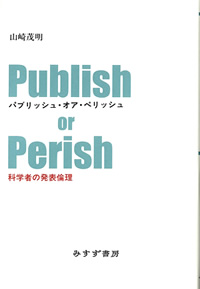トピックス
『パブリッシュ・オア・ペリッシュ』『科学者心得帳』
科学者の倫理と社会的責任を考える二冊
科学者の不正事件が新聞・TVで報道されるとき、必ずみんなが問うのは2種類の「なぜ?」である。一つは、「どうして、不正が可能だったのか?」「どのようにして、たくさんの専門家がこの人に騙されたのか?」という疑問。不正が入り込むシステムに関する疑問とも言える。もう一つは当然ながら、「そもそもなぜ、科学者が悪質で破廉恥な不正に手を出すのか?」といった、科学者の世界観や倫理観に関する疑問だろう。
山崎茂明『パブリッシュ・オア・ペリッシュ――科学者の発表倫理』は、科学者の営みに不正が入りこむシステムの問題に注目した本である。著者は、科学者の不正行為の枠組みや対応策についての知を体系化する地道な努力を重ねてきた、国内無二の専門家。本書では、「パブリッシュ・オア・ペリッシュ」という言葉に象徴される科学者の現実に深く分け入って、共同研究と共著論文の増加、量的な研究評価指標への依存傾向など、研究社会の構造がいまや不正を排除できない要因を具体的に指摘する。これまで業界内の閉じた議論の対象でありがちだったが、本書はそれをより幅広い議論の場に提起することを意図するものだ。
◆レフェリーシステムは完全なフィルターか
「後に誤りであることがわかった論文を出版してしまう」ことと、「後に高い評価を得た論文を却下してしまう」ことの、どちらが編集者にとって重大な失敗と考えるか。この問いへの答えは、欧米と日本では大きく異なっていた。欧米では、「後に誤りであると判明した論文」を採用してしまったことよりも、「優れた論文を不採用にする」ことのほうが、重大な失敗と考えていた(O'Connor M. Editing Scientific Books and Journals. Wells: Pitman Medical, 1978)。1960年代にThe Lancet誌の改革に努めたダグラス=ウィルソン委員長は「レフェリーの意見は慎重な考えにおもむく傾向にあり、価値ある論文を見逃し、彼らの分野の常識に支配されやすい」(Douglas-Wilson I. Editorial review: peerless pronouncements. N Engl J Med, 1977; 296: 877)とのべ、編集者は新しい独創性のある論文を積極的に刊行していくよう努力すべきとした。また、通常1論文にたいし2名のレフェリーで審査が行われるが、このレフェリー間の意見が大きく異なった時の編集者の対応原則は、「出版するほうがよい。なぜなら、そこに何か人をエキサイトさせるものがある」と考えている。レフェリーシステムは、研究情報の流れを阻害してはならず、科学研究を発展させていくダイナミズムを否定してはならないからだ。このような編集者の積極性は、不正行為論文を含め、誤りを含んだ論文が、見逃される危険をはらんでいるのである。
(中略)
論文ねつ造事件などがおきると、レフェリーシステムへの批判が噴き出すが、研究者への信頼と性善説を基盤としたこれまでの審査メカニズムは、完全なフィルターにはならない。レフェリーシステム自体が、新たな枠組みのなかで再構築される時期にきている。これまでの質のフィルターに加え、研究の公正さという要素をフィルターに強化していく必要がある。例えば、オーサーシップの厳密な適用を意図し、「著者同意書」に著者全員が自筆のサインをする。これを徹底することで、共著者全員で報告内容に責任を持つようになり、不正の抑止力になるであろう。
…続きを読む »
(山崎茂明『パブリッシュ・オア・ペリッシュ』第11章より)
◆オーサーシップの定義が揺らいでいる
研究論文の著者の定義は「発表された研究内容に責任を持ち、研究において十分な貢献を果たした人々」である。助言や技術的な協力、単なるデータ収集、研究組織の長というだけで、実際的な寄与のない人を「著者」に加えることはできない。謝辞の対象と著者を正確に分けることが研究者に求められている。しかし、実際には、オーサーシップをめぐる争いごとは、研究活動のなかで発生する苦情のなかで、主要なものになっていることをウィルコックスは報告している
(Lock S. A Difficult Balance: Editorial Peer Review in Medicine. London: Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1985)。定義が十分浸透していないばかりか、その運用に個人差が見られ、さらに研究風土と抵触する事例も見られる。
生命科学領域でスタンダードとして認められている国際医学雑誌編集者委員会が制定した「生物医学雑誌への統一投稿規程」の最新版(2006年2月)では、以下のようにオーサーシップを定義している。
「オーサーシップの認定は、下記の3項目をすべて満たさなければならない。
1)研究の着想とデザイン、あるいはデータの収集。あるいはデータの分析と解釈、などへの本質的な貢献があり、
2)論文の原稿執筆、あるいは重要な知的内容への批判的な改訂をおこない、
3)出版されるべき原稿への最終確認をおこなう。
オーサーシップの認定は以上にもとづいて判断される。」
(原文:Authorship credit should be based on 1) substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data; 2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and 3) final approval of the version to be published. Authors should meet conditions 1, 2, and 3.)。
ここで注意すべきは「あるいは(or)」の使い方である。第一項は、「研究の着想とデザイン、データの収集、データの分析・解釈」のいずれかで本質的な寄与をするものであり、3点をすべて満たす必要はなく、いずれか1点でもよい。第二項は、「論文原稿を執筆するか、内容面で知的な改訂を行う」。第三項は、「発表原稿への最終同意」である。そして、著者リストに名前の入る人物は、これらの3項目を同時に満たすことが求められている。この定義は、共同研究が主流になっている現代のスタイルのなかで、妥当な記載内容である。
…続きを読む »
(山崎茂明『パブリッシュ・オア・ペリッシュ』第10章より)
◆オーサーシップの厳格な適用は不正行為の防止につながる
不正行為の定義は、FFP(fabrication「ねつ造」、falsification「偽造(改ざん)」、plagiarism 「盗用」)を指すが、韓国のES細胞捏造事件だけでなく、ほとんどの不正行為事件にオーサーシップの誤用が付きまとっていることを本書第II部でも見てきた。
科学界では、身近な同僚同士が評価しあい、信頼性の高い知識を積み重ねていくことが前提とされている。オーサーシップの厳格な適用がなされないと、不正をチェックすることもできない。共同研究が普及する中で、個々の研究者の責任感が希薄になり、適切な相互批判や自由な意見交換が失われると、誤りや不正を見逃すことになる。そればかりか、不正論文に加担してしまう危険さえあるのだ。
不正行為を防止する重要なフィルターとしても、オーサーシップを正しく適用することが求められている。責任ある公正な科学研究を確立するために、オーサーシップについての討議を発展させる必要がある。
…続きを読む »
(山崎茂明『パブリッシュ・オア・ペリッシュ』第10章より)
本書から見えてくるのは、不正の土壌となっている競争、研究評価のあり方、教育のあり方は、現在の科学界の構造に根深く組み込まれていること。そして、表沙汰にならない不正が一部では常態化すらしているかもしれないという危うい現状である。科学界の外から科学と社会の将来を考える立場の人にとっても、研究者の現実をふまえた議論への糸口になるだろう。

一方、池内了『科学者心得帳』は、科学者の胸の内側の理屈に注目している。こちらの本は、自身科学者である著者が、道を踏み外さないための知識と知恵を整理して、後進の人たちのために記した覚書のような手触り。長年研究現場で重ねてきた経験と思索から得たものを後輩と共有したいという、メンターとしての著者の願いがストレートに表れている。科学分野の研究室に初めて入ったばかりの学生が、若い教官やポスドクと一緒にこの本の中のテーマについて、一つ一つ話し合うような研究室内の倫理教育の場があれば理想的ではないか。学生が幅広い観点から科学者の役割を考える足がかりになるだけでなく、それ自体が学生とメンターの関係を育む場にもなる。ディスカッションに必要な材料を、著者は数多用意してくれている。
- J・R・ブラウン『なぜ科学を語ってすれ違うのか』青木薫訳はこちら
- A・B・パーソン『幹細胞の謎を解く』渡会圭子訳・谷口英樹監修はこちら
- 柘植あづみ『生殖技術』はこちら
- T・M・ポーター『数値と客観性』藤垣裕子訳はこちら
- C・ウィットベック『技術倫理』1 札野順・飯野弘之訳はこちら