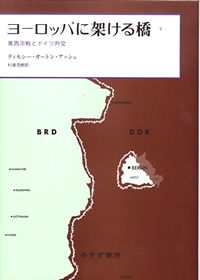トピックス
ガートン・アッシュ『ヨーロッパに架ける橋』
東西冷戦とドイツ外交[上・下] 杉浦茂樹訳
第二次世界大戦でヒトラーの第三帝国が崩壊すると、ドイツは4つの連合国(米英仏ソ)に分割占領され、首都ベルリンも4分割された(ヤルタ体制)。
しかしベルリンはソ連の占領区内にあったために、西側3カ国の統治する西ベルリンは「陸の孤島」となる。ソ連は、早くも戦後3年目に、東西ベルリン間の境界線を封鎖し始めた。その後も東西冷戦は激化し、1961年8月、東ドイツは「ベルリンの壁」の構築を開始。壁で隔てられた市民は突然、家族であろうと、会うことも電話をすることもできなくなった。壁を突破しようとして、射殺される犠牲者が出始める。
同じ1945年に第二次大戦に負けた日本。当初は分割統治案があり、北海道はソ連が領有を主張した。結局、アメリカの圧力に屈して実現しなかったが、もし、ソ連がもっと早く極東戦線に参戦していて、もっと強大だったら、どうなっただろう。もし、ドイツの戦後処理方式が踏襲されていたら? 琵琶湖あたりを境界線として東西に分割され、東京も分割されていたら、「西日本」から「陸の孤島」の「西東京」へ行く、とはどんなことだっただろう?
一見すると荒唐無稽のこんな事態が、ドイツでは現実だったと考えると、経緯は別として、事の深刻さに圧倒される。日本と違って、いくつもの国と複雑な国境線を接してもいる。
『ヨーロッパに架ける橋』は、ベルリンの壁構築から、1989年の壁開放までの時期を主にあつかう歴史書。しかも、ドイツ統一を悲願として地道に展開された、旧西ドイツの外交政策「東方政策(オストポリティーク)」と、東西両陣営の確執とを、政府レベル、民間レベルを含めて、迫力たっぷりに描いた、ル・カレ絶賛のドキュメントである。「オストポリティーク」という表現は、ドイツ語のまま世界中で認知されるほど有名になり、日本の新聞雑誌にもしばしば登場した。
著者のガートン・アッシュによると、西ベルリン市民にとって、フリードリッヒ通りの3ブロック先に住む兄弟は遠いモンゴルに行ってしまったも同然だった。東西間で、限定的な措置として、通行許可証協定が成立していたが、67年から69年には、年間6万人程度しか東ベルリンへは行けず、西ベルリンと西ドイツを結ぶルートの両端に設けられた要塞のような検問所と、車の下に亡命者がしがみついていないかどうかを調べる特殊な鏡は、スパイ小説を地でいくものだったようだ。西独政府は、市民が東独領を通過する料金を一括して支払っただけでなく、莫大な道路修繕費も支払った。陸上ルートで西ベルリンを出入りする人々の数は、1970年の700万人強から、86年には2400万人近くまで急増する。
さらに興味ぶかい数字がある。1963年、早くも経済的に下り坂だった東ドイツは、収監していた西側の政治犯に、「重要度」や経歴に応じた価格をつけて、西ドイツ政府に売り始める。1977年には、政治犯1人当たり95,847西ドイツ・マルク(約43,000米ドル)と決められた(当初は96,000マルクに設定されたが、あまりに歴然と身代金とわかるのはまずいと、わざと153マルク減額されたという)。こうして、1963年から89年までに、34,000人近い政治犯が西独政府に買い取られた。
一方、家族再会の値段は、80年代を通じて1人当たり4,500マルクが標準的な相場。最終的に2000人以上の子供が親との再会を果たし、家族の再会は計25万件以上になる。こうして、人道事業のために西独側が東独側に支払った金額は合計35億マルク前後に上った。
東独政府の懐に入ったこれらのマルクがどこへ流れたかは、また別のストーリーで、本書に詳しい。しかし膨大な出費をした西独政府には冷徹な計算があり、東独が経済的に安定することは、むしろ和解を可能にし、統一への近道になるという確信があった。
戦後、西ドイツは祖国統一を最優先課題としたから、西側陣営に対しては、もはや「危険なドイツ」ではないこと、西側の誠実な一員であることを印象づける必要があり、モスクワに対しては、東ドイツとの交渉はかならずモスクワを経由することを確約して安心させる必要があった。西ドイツにとっては、ヨーロッパの架け橋となって東西ヨーロッパの和解を達成することが、なによりも統一の近道だったのである。経済の側面も含めて、全方位の綱渡り外交はこうして生まれた。
■スパイ小説ばりのパーソナル・ヒストリー『ファイル』

1978年、「ぼく」は愛車アルファ・ロメオを駆ってベルリンへ向かった。ぼくはオクスフォードを出たばかりの歴史家の卵。ナチス政権下の抵抗が研究テーマだった。
ぼくの滞在はベルリンの壁の両側にまたがっていた。資料の山に埋もれ、人に会い、東欧を旅し、恋をした時代――だが、その一挙一動を秘密警察(シュタージ)が監視していたのだ。
東西ドイツ統合後に公開された記録のなかに、ぼくはもうひとりの自分を見つける。暗号名は「ロメオ」。複雑な思いと抗いつつ、ぼくは行動を開始した。ファイルを手がかりに情報提供者をひとりひとり訪ね、ドイツの過去と向き合う旅に出ようというのだ。
ジョン・ル・カレ、ジュリアン・バーンズらも絶賛した歴史家ガートン・アッシュの感銘深いパーソナル・ヒストリー。
- トニー・ジャット『ヨーロッパ戦後史』上(森本醇訳)はこちら
- トニー・ジャット『ヨーロッパ戦後史』下(浅沼澄訳)はこちら
- ジェームズ・ジョル『ヨーロッパ100年史』1(池田清訳)はこちら
- ジェームズ・ジョル『ヨーロッパ100年史』2(池田清訳)はこちら
- ゴードン・クレイグ『ドイツ人』(真鍋俊二訳)はこちら
- ロバート・ジェラテリー『ヒトラーを支持したドイツ国民』(根岸隆夫訳)はこちら
- ハンナ・アーレント『イェルサレムのアイヒマン』(大久保和郎訳)はこちら
- アンドルー・ゴードン編『歴史としての戦後日本』上(中村政則監訳)はこちら
- アンドルー・ゴードン編『歴史としての戦後日本』下(中村政則監訳)はこちら
- 戸谷由麻『東京裁判――第二次大戦後の法と正義の追求』はこちら
- 明田川融『沖縄基地問題の歴史――非武の島、戦の島』はこちら
- E・W・サイード『オスロからイラクへ』(中野真紀子訳)はこちら