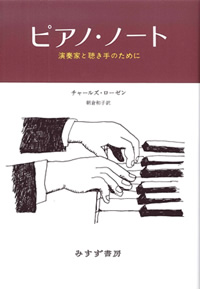トピックス
『ピアノ・ノート』
チャールズ・ローゼン 朝倉和子訳
初版刊行から3週間、まず『朝日新聞』と『日本経済新聞』に書評が出(10月11日)、それから営業部の電話は鳴りつづけて、一カ月強を経た現在、すでに第三刷に入りました。
「いまピアノを習っていたり、趣味で弾いたり、あるいは自分では弾かなくともピアノ音楽に関心を持つ人は、とにかく一度は本書を繙くべきだ」
「本書を読んで、いろいろと疑問が氷解した。たとえば、同じピアノを二人の演奏家が弾いて〈音色〉が違うのはなぜなのか? ホロビッツと猫が同じピアノの同じ鍵盤を一音だけ押したとき、そこに〈音色〉の違いはあるのか?」(奥泉光氏)
「ピアノは人間の身体による表現である点に改めて目を向ける。ピアノはより強く大きな音を求めて改良を重ねられていったが、その結果人間の身体の能力を超えて進化し、ベートーヴェンの時代では難なく弾くことが出来たグリッサンドも、今日のピアノでは指を痛めてしまう」
「(著者は)巨大なグランドピアノが〈ただの木材のかたまりになりかけ、不細工な前史時代の生き物として絶滅の危機に瀕している〉と述べる。…今日のピアノ界への警鐘とも言える」(西原稔氏)
では、『ピアノ・ノート』を買ってくださる読者はどんな方々だろう。営業部にはさまざまな注文のファックスを頂いているが、ピアノの先生方からの注文が思いのほか多く、これは嬉しい誤算だった。
それは、著者が「ピアノの衰退」を語っているからではない。日本で高度経済成長が続いていた一昔前、とくに都市部では子供たちの「ピアノのお稽古」は一般的な風景で、アップライト・ピアノはどんどん売れて家庭の居間の一角を占拠した。それらが邪魔者扱いされ、悲惨な運命を辿るようになってから、すでに久しいのだ。
しかし、流行としてのピアノのお稽古は表面的に目立たなくなっても、ピアノは依然として音楽を学ぶ基本であり、その尽きない魅力を、現に『ピアノ・ノート』の著者もたっぷりと書き込んでいる――「他の楽器ではなく、ピアノを選んだ理由」を。さらに最近、街のピアノ教室に通う人たちに、時間に余裕のできた熟年の人たちが増えているという。願わくば、この方々が楽器を奏でる愉しみを諦めるほど、経済が逼迫しませんように。
- 『グレン・グールド著作集』 1(野水瑞穂訳)はこちら
- 『グレン・グールド著作集』 2(野水瑞穂訳)はこちら
- 『グレン・グールド書簡集』(宮澤淳一訳)はこちら
- 『グレン・グールド発言集』(宮澤淳一訳)はこちら
- J・ホロヴィッツ『アラウとの対話』(野水瑞穂訳)はこちら
- 小沼純一『バッハ「ゴルトベルク変奏曲」世界・音楽・メディア』はこちら
- 『バレンボイム/サイード 音楽と社会』(中野真紀子訳)はこちら
- 青柳いづみこ『水の音楽――オンディーヌとメリザンド』はこちら
- 高橋悠治『きっかけの音楽』はこちら
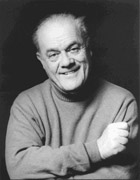 Photo : Courtesy of Indiana University
Photo : Courtesy of Indiana University