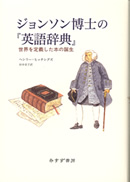トピックス
ヒッチングズ『世界文学を読めば何が変わる?』
古典の豊かな森へ 田中京子訳
本書の原題は、“How to REALLY Talk about Books You Haven't Read”――今度こそ、読んでいない本をいかに語るか。これを聞いて思い出すのは、ピエール・バイヤールの『読んでいない本について堂々と語る方法』(大浦康介訳、筑摩書房)だろう。じっさい、ページを開くと「どれだけ少ない知識で、どこまで語れるか」などという見出しが飛び込んできて、これはバイヤールの二番煎じ? と疑ってしまう。くわえて、著者自身もしれっと「この本は、バイヤールに触発されて書かれた」と言っているのだから、ますます、この本はどういう本なのかと危ぶまずにはいられないだろう。
が、著者が周到にしかけたこうしたトリックにひっかかってはいけない。たとえば、ヒッチングズはこんなふうに言う。「この本にとりあげられているのは、たいてい知っているはずだと思われている本や作家であり、われわれの知識の穴をどう埋めるかの現実的な対策である」と。そう言いながら、じつのところ、読まないで、その本の内容をよく知っていると人に思わせる方法を伝授する気など、さらさらないのだ。
誰もが知っているけれど実際に読んだことのある人はぐっと少ないホメロス、ダンテ、ジェイムズ・ジョイスに、長期入院でもしないかぎり手に取らない、かのプルースト。学生時代に有名どころをひとつかふたつ読んで知ったつもりになっているシェイクスピアにドストエフスキー、ジェイン・オースティン。極東からのエントリーは『源氏物語』……
ユーモアと辛口のスパイスがきいたヒッチングズの文章を読んでいると、今まで見えなかった世界がひろがっていく。鬱蒼と、道も見さだめがたく思われた昏い樹海が、じつはみずみずしく甘い匂いを放つ、豊かな森であることに気づく。
『英語辞典』で有名な、サミュエル・ジョンソン博士はあるときこう言った。「こんにちでは書く人ばかりだね」。それから250年後の21世紀――ブログの更新やつぶやきに大忙しの私たちの頭を、しばし、文学の森にあそばせてみたっていけないことがあろうか?
それぞれの本や作家にミニ知識とトリビア、楽しいコラム、巻末にはクイズも付した、若いヒッチングズらしいユニークな視点が満載。いわゆる古典案内の枠をはみ出した古典案内、ここに登場。
- オコナー『われらのジョイス』(宮田恭子訳)はこちら
- ノーマ・フィールド『源氏物語、〈あこがれ〉の輝き』斎藤和明他訳はこちら
- サザーランド『ヒースクリフは殺人犯か?』(川口喬一訳)はこちら
- 『エドマンド・ウィルソン批評集』1(中村・佐々木訳)はこちら
- 『エドマンド・ウィルソン批評集』2(中村・佐々木・若島訳)はこちら
- こんな授業が聞きたかった。――シリーズ《理想の教室》はこちら