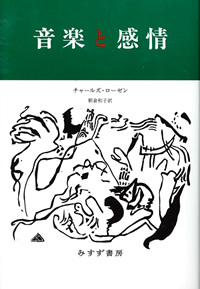トピックス
チャールズ・ローゼン『音楽と感情』
朝倉和子訳
『ピアノ・ノート』につづくチャールズ・ローゼンの第二弾『音楽と感情』。訳者から、みすず書房ウェブサイトのためにメッセージをいただきました。
訳者から読者のみなさまへ
朝倉和子
『ピアノ・ノート』(みすず書房2009年刊)で大ブレークしたチャールズ・ローゼン待望の第二弾をお届けできて、たいへん嬉しく思います。
原著(MUSIC AND SENTIMENT)の発売から数か月たった2010年夏、ロンドンの書店を訪れたときは平積みになっていて、みすず書房の編集部長によく似たしゃべり方をする店員さんがニコニコしながら、すでに53冊売れたと自慢げに教えてくれました。
今回の邦訳には、今年83歳になるローゼンが、長年コラムを書きつづけている『ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス』に、ショパンとシューマンの生誕200年を祝って寄せた2編の小評論も収録することができました。
『ガーディアン』紙の音楽欄は、ローゼンが今年5月にロンドンのクイーン・エリザベス・ホールでショパンを弾いたことを伝えています。現役バリバリの活躍ぶりですね。みすず書房編集部によると、この演奏を聴いた日本人読者のお一人から、「すばらしく美しい音色だった」と興奮まじりのご報告をいただいたそうです。なぜか、わがことのように嬉しくなってしまいました。
「音楽と感情」って、音楽好きにはたまらないテーマです。音楽を聴くと、なぜこんなに心が騒ぐの? なぜ涙が出てくるの? そんな音楽のいわば本丸に斬りこんでいくローゼンは、さあ、何を教えてくれるでしょう。楽しみですね。
ローゼンには『古典派様式』(1971)と『ロマン派世代』(1994)という2冊の大著があります。前者は18世紀後半に様式として確立された調性音楽の分析、後者は、その厳格なルールから解き放たれて開花したロマン派を論じ、文学や絵画、社会変化と連動する芸術運動としてとらえた刺激的な文化批評でもあります。両方ともまだ邦訳されていません。分厚い本で、2冊合わせると、『音楽と感情』の10倍以上のボリュームがあります。おまけにこの2冊は専門性が高く、けっして読みやすい本ではありません。
いっぽう『音楽と感情』は、古典派の成立過程と、そのあとのロマン派、そして現代音楽までを、“音楽の感情表現”という切り口で分析したユニークな音楽史です。つまり、ローゼンが前2作であつかった時代の両方を通して読めるありがたい存在です。しかし、コンパクトな本というのは、分量が少ない分だけ叙述が切り詰められたものになり、逆に読みすすめるのに苦労することがありませんか。
ローゼンは本書でこんなことを言っています――ベートーヴェンもバッハも最初からポピュラーだったわけではなく、登場してきたころは斬新すぎて、世間の人が彼らの描く感情世界に入りこみ、楽しめるようになるには数十年かかった。――人びとはまずその音楽を何度も耳にして、なじむ必要があったのです。
私はこう思いました。ローゼンの世界もこういうコンパクトな本で、まずなじんでみる。するとページのなかから透かし絵のように、だんだんとメッセージが浮かびあがってきて、大きなテーマがくっきりと見えてくる。そうなればしめたもの。たとえば『古典派様式』を読んでも、くどくどした専門的な分析がすんなりのみこめるようになり、純正律と平均律、協和と不協和、短調と長調など18世紀の音の世界が、端正で堅牢な建築物のようにその姿をあらわしてきます。
本にはさまざまな読み方があります。読者のみなさまも、ぜひご自分の読み方でこの珠玉のような本を味わっていただけたらと思います。
- 高橋悠治『カフカノート』はこちら
- 高橋悠治『カフカ/夜の時間――メモ・ランダム』はこちら
- 高橋悠治『きっかけの音楽』はこちら
- 舘野泉『ピアニストの時間』はこちら
- 青柳いづみこ『水の音楽』はこちら
- T・ペイジ編『グレン・グールド著作集』1 野水瑞穂訳はこちら
- T・ペイジ編『グレン・グールド著作集』2 野水瑞穂訳はこちら
- ロバーツ/ゲルタン編『グレン・グールド書簡集』宮澤淳一訳はこちら
- J・P・L・ロバーツ編『グレン・グールド発言集』宮澤淳一訳はこちら
- アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』1 柿沼敏江訳はこちら
- アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』2 柿沼敏江訳はこちら
- E・ヴァイスヴァイラー『オットー・クレンペラー』明石政紀訳はこちら