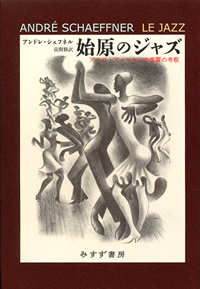トピックス
シェフネル『始原のジャズ』
アフロ・アメリカンの音響の考察 昼間賢訳
1926年に書かれた世界初のジャズ論。音楽のプリミティヴィズムに向かう音楽学者=民族学者シェフネルの驚異的な洞察力。訳者からこのウェブサイトのために、本書の魅力を語るひとことを特におよせいただきました。
アンドレ・シェフネル『始原のジャズ』の魅力
――訳者からひとこと
昼間賢
本書に描き出され、論じられているジャズは、私たちが知っている、または街なかで何となく聞いているジャズと比べると、だいぶ異なっています。ジャズが独り立ちしたのは、1940年前後の「ビバップ」の誕生によってでした。それまでは主に踊るための商業音楽だったのが、それからは主に聞くための芸術音楽になったのです。1926年に書かれた本書は、したがって後者とはほとんど関係ありません。まだドビュッシーやストラヴィンスキーの雰囲気が残る20年代のパリでは、ジャズといえば前者でした。したがってシェフネルが触発されたジャズは、ある種のポピュラー音楽だったことになり、シェフネルが音楽学から民族学へと研究領域を広げていくきっかけとなった本書の魅力は、まず、20世紀に始まるポピュラー音楽の黎明期が浮かび上がってくる点です。当時のジャズ(アームストロング、ベシェ、エリントン、等々)、そして同時代のクラシック(ガーシュインやミヨーなど)を聞きながら読むと、楽しさは倍増するでしょう。
本書の魅力は、それだけではありません。シェフネルの驚異的な洞察力は、ジャズの研究によってあらゆる音楽を超越し、様々な楽器に、音そのものに到達し、そして人間と音響のプリミティヴな関係に向かっています。そこでの主体は、アフリカの人々、そしてアフリカからアメリカに連行された人々です。しかしもちろん、ジャズは明らかに後者の音楽であって、シェフネルの真の狙いは、アメリカで「黒人」の音楽と「白人」の音楽が「融合」したように、音楽のプリミティヴィズムによってヨーロッパの芸術の再生の契機を探ることでした。ここで、訳者解説を斜め読みしてみましょう。
「シェフネルにとって音楽とは、自然的人間が文化的人間として立ち上がる際の最初の営みの一つ――料理や言語活動と並んで――だった。その位相では、ヨーロッパもアフリカもアメリカもなく、白人も黒人もなく、したがってボンゴ族の音楽から《春の祭典》への移行も、決して唐突ではない。むしろ、そこに西洋音楽の最先端を批評的に接続することで、その状態から、西洋音楽が生まれ変わるためのそれとは何か、西洋音楽においてジャズに相当するものは何か、などという問題意識があったはずだ。そして私たち後代の読者は、ジャズが目まぐるしく様式化していった挙句、フリージャズという「作品そのものが噴出である」ジャズに行き着いたことを知っているし、また、今日のいわゆる現代音楽の一部が、演劇的表現を重視し、踊りや身ぶりと密接に絡んだ自由度の高い音楽を生み出していることも知っている。……このように、ある面ではすべてが一巡したように見える今日、シェフネルの音楽観とその後のジャズの、むしろつながらなさが、私たちの感性と思考とを刺激するのではないだろうか。」
1925年秋、ジョセフィン・ベイカーの踊りに圧倒されたシェフネルが、その後マルセル・モースに出会い、師事し、わずか半年で書き上げた本書のうち、本論はわずか百頁足らずの小論ではありますが、ジャズだけでなくあらゆる音楽に、そして関連する芸術に関心がある方々にとって、様々な発想の宝庫であるでしょう。
◇刊行記念トークショー「《始原のジャズ》の衝撃」 開催のお知らせ[終了しました]
アンドレ・シェフネル『始原のジャズ』の翻訳刊行を記念して、訳者・昼間賢のトークの夕べ「《始原のジャズ》の衝撃」が、7月22日(日)16:00より東京・吉祥寺のサウンド・カフェ・ズミで開かれます。
ドビュッシーやストラヴィンスキーなどの雰囲気下の20年代パリに衝撃を与えた《ジャズ》の情勢とは? 何がそれほどの衝撃だったのか? 音源を聞きながら、《始原のジャズ》の世界へとご案内する、そんなひとときをと考えています。
- 『アラン・ローマックス選集』コーエン編・柿沼敏江訳はこちら
- スヘイエン『ディアギレフ』鈴木晶訳はこちら
- エクスタインズ『春の祭典』[新版]金利光訳はこちら
- ロス『20世紀を語る音楽』 1 柿沼敏江訳はこちら
- ロス『20世紀を語る音楽』 2 柿沼敏江訳はこちら
- ローズ『ブラック・ノイズ』新田啓子訳はこちら
- エシュノーズ『ラヴェル』関口涼子訳はこちら
- レヴィ=ストロース『遠近の回想』[増補新版]竹内信夫訳はこちら