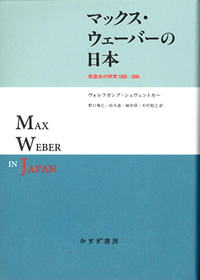トピックス
『マックス・ウェーバーの日本』
受容史の研究1905‐1995
ヴォルフガング・シュヴェントカー 野口雅弘・鈴木直・細井保・木村裕之訳
著者の「日本語版への序文」の出だしは次のように始まる。
「ベルリンの壁が崩壊する約一ヶ月前の1989年10月1日に、私は二年間の予定で東京に来た。その年の12月のある週末に、ウェーバーに関する古本を探しに神保町を訪れた。その一つの古本屋で――南海堂書店だったと思う――マックス・ウェーバーの奇妙な論文集を見つけた。ブックカバーは日本語で、本の中身はドイツ語だった。その本は1921年初版のGesammelte Politische Schriften(『政治論集』)で、1954年に日本で、みすず書房によってリプリントされたものだった。この本が、私が日本で買った最初の本になり、本書『マックス・ウェーバーの日本』の一部になった。」


 『政治論集』リプリント版の函(上)・とびら(中)・月報(下)
『政治論集』リプリント版の函(上)・とびら(中)・月報(下)そして、さまざまな偶然と必然の結果、本書はみすず書房から刊行されることになった。
本書は、1905年の福田徳三による『国家学会雑誌』のウェーバー紹介記事から1995年までの日本におけるウェーバー受容を追った画期的研究で、なぜ日本でこれほどまでに「ウェーバー、ウェーバー」なのかの意味を解読した本だが、みすず書房だけの刊行物を見ても、そこにはいろんな歴史物語が見え隠れしている。
うえに記したリプリント版も1950年代前半および1970年代後半に十数冊刊行しているが、翻訳されたものでも『権力と支配』(1954)『家産制と封建制』(1957)『古代ユダヤ教』(全2巻、1962、1964)『歴史は科学か』(1965)『宗教社会学論選』(1971)『政治論集』(全2巻、1982)があり、さらにマリアンネ・ウェーバーの『マックス・ウェーバー』にはじまり数多くの研究書が刊行されている。大塚久雄、丸山眞男の著作をはじめ、ウェーバーに直接間接触れられているものを入れると、いったい、みすず書房から刊行した本の何冊がウェーバー関係の本ということになるのだろうか。
ところが、その現象も、1990年代後半になると、ぴたりと止まる。これは日本における本の売れ行きが落ちるのと符合している。大学の機能が変わり、それに伴ってアカデミズムおよび反アカデミズムの意味が不透明になり、人文・社会科学書が読まれなくなったことと、ウェーバー受容のあり方はどう関係しているのだろうか。
まずは本書を読み解くところから、本書の研究が終わる「1995年以後」についても考えることが、次の課題かもしれない。
- ヴェーバー『宗教社会学論選』大塚久雄・生松敬三訳はこちら
- マイヤー/ウェーバー『歴史は科学か』森岡弘道訳はこちら
- マリアンネ・ウェーバー『マックス・ウェーバー』大久保和郎訳はこちら
- 大塚久雄の本はこちら
- 丸山眞男の本はこちら
- ロバート・N・ベラーの本はこちら
- 柳父圀近『ウェーバーとトレルチ』[オンデマンド版]はこちら
- 野口雅弘『闘争と文化』はこちら