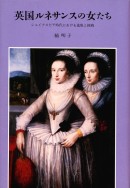トピックス
楠明子『シェイクスピア劇の〈女〉たち』
少年俳優とエリザベス朝の大衆文化
シェイクスピアほど多くの読者に恵まれた作者もいないのではないか? それに比例して研究者の数もまた厖大である。日本文学でいえば、芭蕉か漱石に匹敵しようか。
とうぜん、この領域で真に独創的な研究をするのはなかなか至難の業であろう。本書はそのなかでこの難関をクリアーしたみごとな成果ではないか?
シェイクスピアの作品中でいちばん有名なのはたぶん『ハムレット』であろう。読んだり見たりしないひとでもこの作品の名は知っている。この有名な劇において登場する女性はたった二人、オフィーリアと王妃ガートルードだけである。これはいかにも少ない感じがするがどうだろう。いろいろ答えはあるだろうが、シェイクスピアの劇団において女役を演じることのできる俳優の数に限りがあったと考えるとすっきりする。『ハムレット』に限らず、シェイクスピアの作品に女性の出番が少ないことはこう考えると得心が行くのではないか。感嘆すべきは数少ない少年俳優たちを効率よく使いわけたシェイクスピアの才能である。
「明日は聖ヴァレンタインの日……生娘の私を中に入れてくれたのだけど、部屋から出る時は、生娘ではなくなっていた」――気の狂ったオフィーリアが口ずさむ歌である。本来なら、育ちのよい娘が歌うような内容ではないが、この性的隠喩に満ちたバラッドは当時流行していたものである。 だから、宰相の娘がとつぜん猥雑な歌を口にしても、観衆は馴染み深い大衆文化の表現として違和感なく受け入れたと思われる。クレオパトラの言動もまた同断である。この女王は一貫して当時一般的であった〈じゃじゃ馬〉として描かれている。そこで観客の身分の上下に関係なく、大衆の文化として少年たちが展開するレトリックに満ちた科白がすんなりと受容されるのである。
本書は、シェイクスピアの作品における少年俳優たちの意味、当時の大衆文化との関わりをみごとの解明した独創的な研究である。これを一読すれば、シェイクスピアの作品がいちだんと面白くなるだろう。
- 楠明子『シェイクスピア劇の〈女〉たち』の詳しい書誌情報はこちら
- 楠明子『英国ルネサンスの女たち――シェイクスピア時代における逸脱と挑戦』はこちら
- 楠明子『メアリ・シドニー・ロウス――シェイクスピアに挑んだ女性』はこちら
- ウルフ『女性にとっての職業』出淵・川本監訳はこちら
- 川本静子『ガヴァネス――ヴィクトリア時代の〈余った女〉たち』はこちら
- 宮田恭子『ジョイスのパリ時代――『フィネガンズ・ウェイク』と女性たち』はこちら
- 宮田恭子『ジョイスと中世文化――『フィネガンズ・ウェイク』をめぐる旅』はこちら
- 宮田恭子『ルチア・ジョイスを求めて――ジョイス文学の背景』はこちら