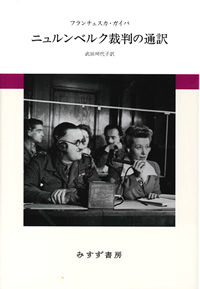
2013.10.25
フランチェスカ・ガイバ 『ニュルンベルク裁判の通訳』
武田珂代子訳
2013.10.10
最近文庫化(ヤマケイ文庫)された高桑信一さんの著書『山の仕事、山の暮らし』は、福島県の西端、只見の奥山のゼンマイ小屋で、ゼンマイ採りの夫婦と初めて出会う場面から始まる。そのときの新鮮な驚きを、高桑さんはこう記していた。
「いっぱしの登山家をきどった私は、夏は沢登りしかしてこなかった。登山道を外れ、渓谷から頂を目指したとはいえ、それは山麓から山頂までの、点と点を結ぶ線でしかなかった。そんな私に、長谷部さんは面としての山を教えてくれたのである。その、山頂にこだわらない広がりのおもしろさと豊かさを知った私は、前にも増して足繁く只見にかよった」
本書『山と渓に遊んで』は、そんな高桑さんが、かつてどんな“登山家きどり”だったのか、どんな沢登りをしてきたのか、“面としての山”とはいかなるものか、その後の只見がよいはどうか、といった事どもが時代を追って詳細に語られた、興味つきない自伝である。
くだんのゼンマイ採り、長谷部昭信さん房子さん夫妻も本書に登場する。なにより、その長谷部さんとおぼしいゼンマイ採りに初めて言われたつぎのようなせりふが、なんとも痛快だ。
「なにが目的で山さ登るんだ。釣りが。違う? 山菜が。それはまずいな。ゼンメエはおらがだの飯の種だから、それを採られるのは困る。ウドやらコゴミやらを土産にするくれえなら、ちっとはかまわねえ。山菜でもねえ? それならなんだ。理由がなくて山には入らんめえ。野鳥の観察が? 岩石の採集が? そんな連中とたまには会うな。それも違うってが。遊びだって? 金払ってが。金払って楽しみだけで、こんなあぶねえ山のなかを登ったり下りたりしてるってが。おらにはわかんねえな」
はい、ごもっとも。いっぱしの登山家きどりも形無しである。山のことは山に教えてもらうに如くはない。それでも山に登るだけでは、じつは山のことはよくわからない。山を暮らしの場にしている山びとに教わることで、初めて見えてくるものがある。それが“面としての山”である。こうして高桑さんの只見がよいは始まった。
只見のゼンマイ小屋を訪ねる山旅を重ねるうち、ふいに高桑さんに幼年時代の思い出がよみがえる。幼年時代を過ごした秋田県男鹿半島の砂浜での、天草干しの光景である。
「なにより驚いたのは、その匂いだった。干しあげたゼンマイを嗅がせてもらった私は、その匂いに驚嘆した。海藻そのものだったのである。(…)
私にはゼンマイの匂いがもたらす、海と山との抜きがたい輪廻のような、間然するところのない関係性に思いを馳せたのである」
山と渓に遊んだ半生を振り返りながら高桑さんは、ひとたびみずからの幼年時代へと立ち帰って、「私は山の子であり、海の子であった」ことに思いいたる。山から渓を通じて海へ、そしてまた山へと循環するこの国の自然に育まれ、営まれてきた山びと、海びとへの共感が、高桑さんの文章の根底にはある。いままさに失われようとしているそんな暮らしへの畏敬と憧憬が、本書に彫りの深い光芒を与えている。


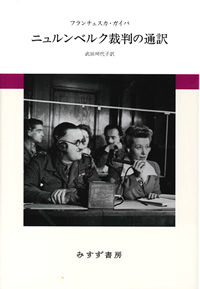
2013.10.25
武田珂代子訳

2013.10.10
「あの頃」を呼び起こす音楽