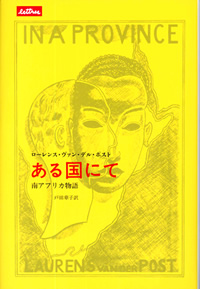
2015.04.23
L・ヴァン・デル・ポスト『ある国にて』
南アフリカ物語 戸田章子訳 〈文学シリーズ lettres〉
生まれてきた不思議、死んでゆく不思議、生まれてこなかった不思議
2015.04.22
「自分の始まりはどこか」――小さな子どもの心にある日ふと訪れる、この大きな問い。
その答えを求めて、さまざまに考え、感じ、探求するとき、子どもはどんな不思議を体験しているのか。その不思議を、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンの論文「インファンティアと歴史」を下敷きとして、著者は「インファンティア」と呼ぶ。
イタリア語でInfanziaは、まず「子ども・幼児期」を意味する。そのInfanziaという言葉を、アガンベンは「言葉で捉えることができない、語り得ぬ位相」と規定した。ラテン語Infansは「無言の、黙っている」「幼少の、子どもじみた」、そしてInfantiaは「つかえがちな下手な話し方、子どもらしいこと」の意味を持つ。「語らぬ、語り得ぬ」の意味を強調したアガンベンのInfanziaの規定を受け継ぎつつ、本書は、そこにあらためて「子ども」の意味を回復させていこうとする。すべてが淡い霞に包まれていた子どもの頃の不思議な感覚。言葉によって写し取ることのできない、在ることの不思議……
気がついたときには、もう、いた。生まれてこないこともありえたはずなのに・自分のかわりに別の誰かが生まれてくる可能性もあったはずなのに、このからだの中に生まれてきていた。そして、いつか必ず死んでゆく。二つの「いない」に挟まれた「自分が・ここに・いる」ことの不思議。
ライフサイクル研究と死生学の接点をなすテーマに踏み込む本書は、あるときは、学校教育の場でのデス・エデュケーション、性教育の問題ともかかわりを持ち、あるときは、生殖補助技術や出生前診断といった生命倫理の問題にも向き合っていくことになる。 哲学や精神分析、文学の中にあらわれた出生と死のさまざまな位相。アガンベンにはじまり、フロイト、クライン、ラカン、漱石、九鬼周造、アレント、阿闍世物語とエディプス物語、埴谷雄高の『死霊』、ファラーチ『生まれなかった子への手紙』……
存在の問いが発せられる場所としての「子ども」の頃の記憶を蘇らせることによって、ともすれば死ばかりに気をとられがちな私たち大人の目が、誕生の不思議、生まれてこないという存在のしかたに開かれてゆく。日頃、突き詰めて考えることを避けがちな、死と誕生にまつわる問い。そのわからなさ、神秘にやわらかに近づく、魅力にみちたアプローチ。
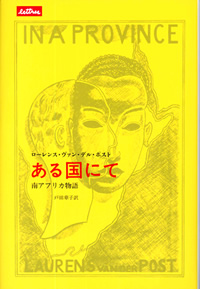
2015.04.23
南アフリカ物語 戸田章子訳 〈文学シリーズ lettres〉
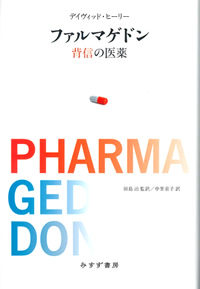
2015.04.13
背信の医薬 田島治監訳 中里京子訳