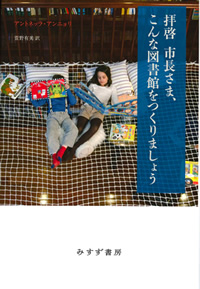
2016.04.13
「訳者あとがき」とインタヴュー記事「どんな町にも“知の広場”を」
アントネッラ・アンニョリ『拝啓 市長さま、こんな図書館をつくりましょう』
池内紀『亡き人へのレクイエム』
2016.04.13
池内紀先生とのふだんのやりとりはファックスが中心である。そこにはいつもしみじみ味わい深いカットが添えられていて、届いたファックスを綴ったファイルは、事務連絡帳でもあり、季節折々のカット集でもある。
いまの時季だと、風に吹かれてのんびりとそよいでいる木。小鳥が伝言を運んでくるときもある。大事に机にしまって、ときどき取り出して眺めている。楽しい。
今年の年明け、寒い日であった。届いたファックスになぜか食パンの絵が。ゆうに半斤はありそうだ。今日は食パン?
新聞、雑誌などに発表した数々の追悼文や解説。それらを大幅に加筆、修正、再構成して、いまは亡き大事な人たちをめぐる本をつくりましょう、という企画をご相談していた。『亡き人へのレクイエム』というタイトルの、その本の原稿が、「食パン」みたいになったとファックスにはあった。
数日後、先生は「食パン」をみずから編集部に届けてくださった。リュックから取り出されたそれは、まさに食パンの厚さであった。
一人のひとについて、違った角度から複数の媒体に書いた原稿を必要な部分をハサミで切って糊で貼ったり、新たに書き加えた原稿用紙が加えられていたり、そして随所にブルーの万年筆で加筆修正がなされていた。「パン」の喩えにふさわしく、あたたかい血の流れや肉のやわらかさを感じるものだった。そのもの自体から、亡き人たちへの思いが伝わってくるような原稿であった。
「あとがき」にはこのようにある。
「最初の追悼文をもとにして、それを何倍かに書きたした。初出のエッセイの後半部だけ生かして、前半がかわったケースもある。記念年が過ぎて、何かちがう気がするところは修正した。死者については、感じとり、本質と思うところをきっちりとらえて書く。それ以上にもそれ以下にも書かない。人間の内部は、やわらかくて壊れやすいのだ。だからこそ、とりわけ礼儀が必要だろう。死者には反論ができないからだ」
本書におさめられた28人の「守護天使」。
「徒党を組むのをいさぎよしとしなかった」人たちである。ここにある文章を読むと、亡くなった人のような気がしない。それはまちがいなく、彼らは言葉を通していまも生きているからだろう。

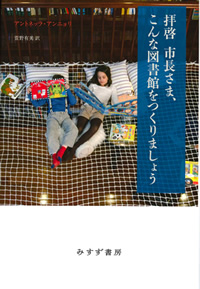
2016.04.13
アントネッラ・アンニョリ『拝啓 市長さま、こんな図書館をつくりましょう』

2016.03.25
牛尾京美『ベイリィさんのみゆき画廊――銀座をみつめた50年』