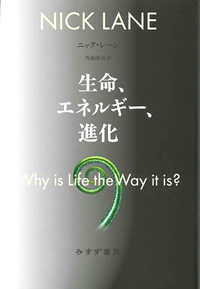
2016.10.14
ビル・ゲイツ評、HONZ客員レビューとして掲載
ニック・レーン『生命、エネルギー、進化』 斉藤隆央訳
ロジェ・グルニエ『パリはわが町』 宮下志朗訳 [20日刊]
2016.10.13
ロジェ・グルニエの新刊を出すたびに、これで終わりかと思うようになってから、もう十年を越えているのではないか。『別離のとき』がフランスで出版されたのが2006年で、訳者の山田稔さんは「あとがき」で、作者が80代に入ってから書かれたこの短篇集は「文字どおりの最新作」であり、グルニエは87歳の現役作家だと書いておられた。
そしてエッセー『写真の秘密』の原書出版は2010年。訳者の宮下志朗さんは「あとがき」で、「1919年生まれだから、もはや卒寿を越えたことになる。とはいえ彼はまだ矍鑠としているようなので、これからも小説やエッセーを発表して、わが国のグルニエ・ファンを喜ばせてもらいたい」と書いている。
こんどのエッセー『パリはわが町』は昨年春の刊行なので、95歳で書いた本(今月現在では97歳)ということになる。なんだか、ポルトガルの映画監督マノエル・ド・オリヴェイラのような話になってしまうが、こうなればもう、百歳の現役作家を目指してほしい。なにしろ、新作が期待をこれほど裏切らない書き手も珍しいからである。
そもそも、畢生の大作とか空前絶後の傑作とかいう形容詞のぜんぜん似合わない作風である。あるインタビューに答えて、ご本人はこんなことを言っている。「自分はもともとペシミストなのだ。人間には考えること、信ずることがあるが、また気質というものもある。人生はおそろしく、何も期待すべきことはないと考えながらも、同時にいつも陽気でいることもできるのだ。自分がそうだ。」
グルニエ本に必ず存在する、この「苦い陽気」をいちど味わってしまうと、けっこう中毒になる。『写真の秘密』の新聞書評で、写真家の石川直樹さんが、上手な喩えを用いている。「ユーモアを交え好々爺のように語りながら、しかし時折ナイフの刃をちらつかせるような文章は、まさに老練というにふさわしい。」
『パリはわが町』の巻末で著者自身が断っているように、この本に出てくる事実や人物は、これまでのグルニエ本で書かれたことも少なくない。それでも読まされてしまう魅力が、この特別な作家にあるのは確かなことだと思う。やはり『写真の秘密』の書評から、池内紀さんの指摘を引かせていただく。「グルニエのような作家はドイツにはいない。よく知らないがアメリカにもいないと思う。日本にいてくれるといいのだが、やはりムリだろう。こんな作家を生み出すためにはパリという街と、そこに流れている時間と、そこで生きていた人間が必要だ。」
池内さんの批評が予想のように的中した作品が、この『パリはわが町』である。パリで生まれ育ったパリジャンではなく、占領下のパリに出てきた青年が、レジスタンス、戦後のジャーナリズムや放送業界、出版界と文学者たちの世界で、いつも陽気なペシミストとしてパリに生きて、書き続けてきた。そんな人間の、長年にわたる出会いと記憶が、小さなエッセーの集合体として本になっている。有名無名を問わず、20世紀を生きていた男女が寸描される。「わたしの町ということになれば、それはパリである」と、サラッと書き出しながら、この本に登場する人々(ほとんどはあの世の住人)の面白いこと、面白いこと。祖父が19世紀パリの印刷工だった話から始まって、自伝のような流れになっているが、どこから読んでもかまいません。ぜひどうぞ。
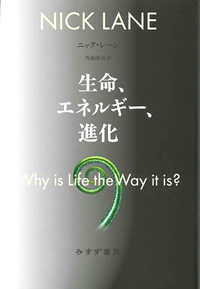
2016.10.14
ニック・レーン『生命、エネルギー、進化』 斉藤隆央訳

2016.09.27
内田博文『治安維持法の教訓――権利運動の制限と憲法改正』