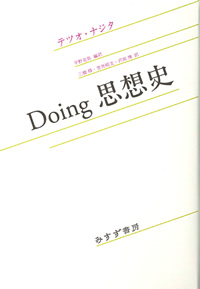トピックス
テツオ・ナジタ『Doing 思想史』
平野克弥編訳 三橋修・笠井昭文・沢田博訳
まず、このタイトル、思想史を「する」とは? 実はこの表現のなかに、ナジタは複数の意味を込めている。彼は今、徳川時代に庶民が創造した「講」の歴史を書こうとしている。今まで書かれたことのない歴史を書くこと、形を与えること、そのための新しい方法をみつけること、それがいかに時間のかかる困難な作業か、この実感は、彼にとって「する」でしかないようだ。
さらに、グローバリズムや地球の温暖化、経済倫理の脱落の問題などに直面する今こそ、徳川時代の破天荒な、孤軍の思想家たちを思い出すべきだ、とナジタは熱く語る――安藤昌益、山片蟠桃、富永仲基、二宮尊徳、緒方洪庵…。官製の「歴史」とは無縁の視点がここにある。ナジタが語りだすと、この傑物たちは無理なく「今の人」になり、躍動しはじめるのだ。こんなかたちで「歴史」と向き合うこと、それはもはや「読む」ではなく「する」という経験だ。
しかし、どうして徳川時代なのか。それは、明治以降の近代化の意味、そこで得たものと抑圧したもの、日本に限らずおよそ近代性とは何か、という問題を考えつづけるナジタが、ついに発見した時代だった。
この本を読む順序としては、ます、第2部にある「Doing 思想史」の4回シリーズの講義から入るのがお薦めだ。コンパクトに、なぜ「思想史」を「する」のか、どんな方法で「する」のか、入り口はどこか、などが具体的な人物や営みをめぐって展開される。思想史がぐっと身近になるだろう。
- アンドルー・ゴードン『日本の200年』上(森谷文昭訳)はこちら
- アンドルー・ゴードン『日本の200年』下(森谷文昭訳)はこちら
- アンドルー・ゴードン編『歴史としての戦後日本』上(中村政則監訳)はこちら
- アンドルー・ゴードン編『歴史としての戦後日本』下(中村政則監訳)はこちら
- ノーマ・フィールド『天皇の逝く国で』(大島かおり訳)はこちら
- J・M・ヘニング『アメリカ文化の日本経験』(空井護訳)はこちら
- テッサ・モーリス=鈴木『辺境から眺める』(大川正彦訳)はこちら
- 萩原延壽『自由の精神』はこちら
- 原武史『可視化された帝国』はこちら
- 丸山眞男『戦中と戦後の間』はこちら
- 『丸山眞男書簡集』全5巻はこちら
- 『丸山眞男話文集』 1 はこちら
- 『藤田省三著作集』全10巻はこちら
- 『藤田省三対話集成』 1 はこちら
- 『藤田省三対話集成』 2 はこちら