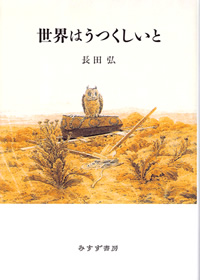トピックス
長田弘『世界はうつくしいと』
長田弘の詩集『世界はうつくしいと』が書店に並びました。表紙カバーでは、19世紀ドイツの画家フリードリヒの描いたミミズクがこちらを愛嬌のある目でじっと見ています。
ところで、詩集の書評が一般新聞に載ることはけっして多くありません。小説のようにプロットを紹介したり、評論のように主旨を要約したり、学術書のように著作の位置を測定したり、こうした手法が詩集には適用しにくいからでしょう。丸谷才一や篠田一士が、かつて朝日新聞の文芸時評に田村隆一や吉岡実の新詩集をとりあげて読書人に知らしめた、そんな時代は例外です。 しかし、マスメディアでは語られない詩の言葉は、今やネット上のブログを介して伝えられています。そこでは長田弘の詩集から気に入った詩を引用して、たとえばこんなコメントがなされているのです。
- 「難解な語句をほとんど使わず、一読してナルホドと納得できる。気になる語句を読み返すと、奥行きのある深い意味が浮かび上がって、心に染みいるような感興を味わうことが出来る」(「武蔵野日和下駄」)
- 「詩に流れているゆったりとしたなつかしい時間。これは、そのまま、詩人長田弘の生きている時間なのだろう。長田弘の詩は、時間からもぎ取られた果実なのだと思う」(「Delfini Workshop」)
そして、このブログを読んだ人の中には、詩集を手に入れて読む人もいるはずです。つまり個人から個人へ本を手渡しすることが、空間の制約なしにおこなわれている。これは口コミとかネチコミとかいう浮ついた語で言われるような情報伝達とは同じものではないでしょう。
『世界はうつくしいと』に収められた27篇の詩は、めぐりくる季節ごとに雑誌「住む。」(泰文館)に書き継がれました。あとがきには「寛ぎのときのための詩集」でありたいと述べられています。深夜に一人聞くアダージョのように、心を世界につなげながら一人としてある、そのためのよき道具として、願わくはお手元にこの詩集を置かれんことを。
- 長田弘の翻訳絵本『エミリ・ディキンスン家のネズミ』はこちら
- 《詩人がおくる絵本》シリーズ全7冊はこちら
- 《詩人がおくる絵本》2 シリーズ全7冊はこちら
- 長田弘・編集のアンソロジー『本についての詩集』はこちら
- 長田弘 連続対談『問う力――始まりのコミュニケーション』はこちら