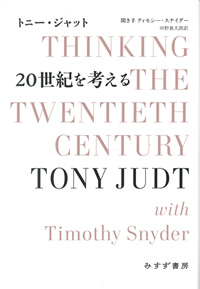
2015.06.25
トニー・ジャット『20世紀を考える』
聞き手 ティモシー・スナイダー 河野真太郎訳
太平洋におけるヨーロッパ神話の生成 中村忠男訳
2015.06.11
もっとはっきりいってしまえば、わたしは現地人がヨーロッパ人の神を創造したのではなく、ヨーロッパ人こそが自分たちのためにそんな神を生み出したのではないかと考えている。すなわち、「ヨーロッパ人という神」とは征服と帝国主義と文明という、容易に分かつことのできない三幅対から生み出された神話だというわけである。
キャプテン・ジェームズ・クックは1768年、1772年、1776年の三度の航海で、ハワイをはじめ、タヒチ、トンガ、ニュージーランドなどに上陸し、ヨーロッパと南太平洋の島々に決定的な影響をもたらした。著者オベーセーカラは、クックの航海を、未開の地の「発見」ではなく、相互関係のはじまりとみている。現地人のまなざしから見たヨーロッパ人=クックとは、どのような人物だったのだろうか。
1779年1月17日の日曜日、クックがハワイ島のケアラケクア湾に上陸したとき、島はちょうどマカヒキ祭の時期で、クックはハワイに伝わる「ロノ神」が降臨したとして、熱烈な歓迎を受ける。そして同年2月14日、おなじケアラケクア湾で、クックはハワイ人の手によって殺害される。そしてクックは神として祀られた。
著者オベーセーカラは、この「キャプテン・クックの列聖化」に疑問を唱える。ハワイ人は本当にクックを、人の姿をした神とみなしたのか。オベーセーカラはキャプテン・クックが殺害される最後の数日間に着目し、航海誌を詳細に分析して、クックの列聖化神話がどのようにつくられたのかを読み解いていく。
そこで見えてきたのは、人道主義者にして神というクック像とは違う姿だった。クックの列聖化はハワイ人というよりも、文明の象徴としてクックを列聖化しようとするヨーロッパ人による神話化の働きであり、理性的かつ普遍的なヨーロッパ人という像をハワイ人に投影しようとする心理化の現れである。
オベーセーカラが本書で提示したこの説は、人類学にスキャンダラスともいえる論争を巻き起こした。直接批判されたマーシャル・サーリンズから、クリフォード・ギアーツ、イアン・ハッキングまで、論争は延々10年も続いた。
クック神話の終わりは、歴史の新たな始まりでもある。人類学の西洋中心主義を鋭く批判した本書は、ヨーロッパ人とハワイ人の歴史的な出会いと、植民地主義に限らずいまなお続く暴力の鏡像関係を明らかにし、他者について語ることの倫理と政治を切り開いた。
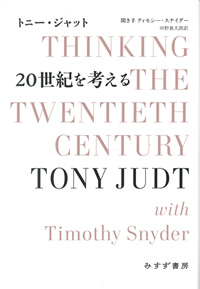
2015.06.25
聞き手 ティモシー・スナイダー 河野真太郎訳

2015.06.10
そのロジックと国際社会の課題 山岡由美訳 李鍾元解説