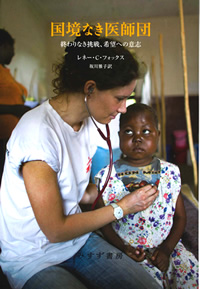
2016.01.12
レネー・C・フォックス『国境なき医師団』
終わりなき挑戦、希望への意志 坂川雅子訳
戦時治安法制のつくり方
2015.12.25
治安維持法が刑罰法規であったにもかかわらず、戦後の研究はもっぱら歴史学や政治学などにおいておこなわれてきた。本書は刑法学者が治安刑法の歴史、論理と運用を解説し、現在の日本で戦時体制が着々と準備されているさまを分析する。
戦前、治安維持法を生み出したのは政党政治であり、「議会制民主主義」だった。大日本帝国憲法を「逸脱解釈」した事実上のクーデターだった。
戦時体制下の非人間的な行為の多くは法令に基づいておこなわれる。戦争は法をこまめに制定しつつ、改正しつつ、準備され遂行される。
治安政策は強化され、マスメディアも含めた徹底した情報統制と世論誘導を行い、隅々まで国民監視ができるようにし、厳しい思想統制を行って戦争に反対や疑問の声を上げないようにした。
戦死や空襲や自然破壊など、想像を絶する「犠牲」を正当化するために「国民のための国家」ではなく、「国家のための国民」が標榜された。
戦前と現在ではもちろん時代状況は違う。だが為政者はしっかりと歴史から学び、方法論が再現されつつある。平時の治安政策から戦時の治安政策へと変化しているさまは、まるで戦前に学んだ設計図が存在するかのようだ。ひるがえって私たちの方はどうだろうか。歴史から学んでいるだろうか。
形式的な「法の支配」や「量の民主主義」(多数決主義)は悪法をももたらす。悪夢のような第二次世界大戦への反省から、戦後世界で、「人間の尊厳」や少数者の権利を守る「質の民主主義」を確立する方法が追求された。「量の民主主義」が「質の民主主義」の提案を受け入れたときに、社会は進歩する。現在、日本の違憲立法審査権、三審制、弁護権、裁判員制度は「質の民主主義」を守るためにも機能しているだろうか。
傷ついたり、四肢をもがれたり、病気をかかえたり、職を失ったり、貧困にあえいだり、生きる意欲をなくしたり、そういった人たちのために社会はある。
(第3章より)
著者はとくにマイノリティの人権法を専門とし、国家による強制隔離の違憲を訴えたハンセン病国賠訴訟の原告を法理論面から支えた。勝訴判決後はハンセン病検証会議の副座長をつとめた。著者はその経験から多くを学んだという。
老いても、病んでも、「人間の尊厳」が守られる社会。そうした社会は、ふつうの人々を含むすべての人々にとって生きやすい社会であろう。
戦争の犠牲者は国家でも為政者でもない、「ふつうの人々」、それも最も弱い立場にある人々である。
人類史上未曾有の被害を生んだ世界大戦を二度と起さないこと。「平和の防波堤」として、基本的人権を保障すること。第二次世界大戦後の世界はこれをすべての国のすべての国民が守るべき「共通の尺度」とした。国連の「人権に関する世界宣言」(1948年)の採択とともに、各国に共通する国際問題と位置づけられた。
国民の人権を無視する国は、他国を侵略し、世界戦争を引き起こす可能性があるからだ。
戦争で戦争を防止することはできない。戦争が生むのは新たな戦争だけだ。その悪循環に陥らないために、人々に基本的人権を保障し、人々が「武器」をとるのではなくて、「勇気」と「理性」「知性」をもって戦争の防止に全力を傾ける社会をつくること。日本も戦後憲法とともに、その闘いの最前線に立つことを誓ったのではなかったか。
法律家の闘いの武器は「歴史的なものの理論化」という法理であり、「非合理的で非人道的な誘惑」に対する毅然とした態度である。そして、磨きぬかれた市民的公共性が大きな武器になる。
(「おわりに」より)
権力の側にではなく、現場に立つ法学には、現実を切り開く「哲学」が満ちている。
今ならまだ引き返せる。来る2016年、新年の希望とともに本書をおくります。

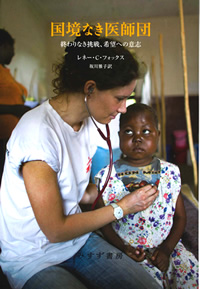
2016.01.12
終わりなき挑戦、希望への意志 坂川雅子訳

2015.12.24
利己的なわれわれはなぜ協調できるのか