トピックス
『ロスコ 芸術家のリアリティ』
美術論集 [クリストファー・ロスコ編/中林和雄訳]
川村記念美術館「マークロスコ 瞑想する絵画」展、開催
現代抽象絵画を代表する作家、マーク・ロスコ[Mark Rothko 1903-70]。その代表作として人びとの知るところとなった「シーグラム壁画」の半数の作品がこの春、日本にやってくる――
作品の配置から照明、展示… 画家本人の構想に従って、ひとつの大きな空間に、そのために描かれた連作の大作を展示するこの壮大なプロジェクト「シーグラム壁画」は、結局、実現をみないまま頓挫。以来、数十年にわたって、30点の作品はアメリカ、イギリス、そして日本の美術館に別々に所蔵されていたが、このたびの川村記念美術館(千葉県佐倉)の展覧会は、現在、考え得るかぎり最高の出品・展示によって、ロスコ芸術の到達点の全貌に接近しようとするものだ。
暗色で覆われた画布。あらゆる色を失ったようでいて、実はあらゆる色、そして光さえもその中に吸収し、封じ込めたかにも思えるロスコの絵は、何を「語る」のか?
本書で、ロスコはみずからの作品について、何も語らない。絵画はみずから「語る」。それを翻訳する、あるいは解説をくわえる、どのような言葉も、ロスコは与えてはくれない。
- 「……それぞれの芸術の真実、リアリティは、その分野の内側にとどまっているから、各々の分野に固有の方法によって感じ取られなければならないのだ。」
(本書「芸術、リアリティ、官能性」より)
絵画は、語っている。差し出している。それは、ぼんやりと絵の前にただ佇んでいるだけでは受け取ることのできないものではあるが、困難なエクササイズによってようやく勝ち獲ることのできる果実でもない。ロスコはむしろ、芸術家が鑑賞者を、キャンバスの中にひろがる「造形の旅」にどのように誘い、引きこまなくてはならないかを考えているのだ。一枚の絵画の本質に出会い、何物にも替えがたい造形的経験へいたる旅へ。
- 「的確な見方をすることによって、ひとつの全体としての絵画が持っている生命を知ることができるようになる。そして、私たちの認識や情動から、つまり私たちの様々な連想や、それらが私たちに感じさせたものから生まれる全体的な効果とは、私たちが享受した造形的な旅の結果なのである。……重要なことは、旅の全体が喜びであるということであり、様々な要因のすべてが一斉にこの喜びに寄与している、ということなのである。」
(本書「主題と題材」より)
あるときは論争的に、あるときは哲学的に。ぼろぼろになった紙にあらっぽくタイプされた草稿は、いま、一冊の本として、20の視点から記された議論の文脈をかぎりなく正確に復元され、私たちに手渡される。6歳で、自死というかたちで父との別れを経験した息子の手によって、特別の想いと理解をもって編まれた本書は、今後けっして出てこないもの。唯一の美術論集、ついに刊行。
「マーク・ロスコ 瞑想する絵画」 川村記念美術館[終了しました]
■展覧会の概要
50年以上にわたって散逸したままだったマーク・ロスコの代表作〈シーグラム壁画〉の半数となる15点が初めて一堂に会し、あらたなロスコ空間を創り上げます。そのほか、展示模型や関連作品、本邦初公開となるロスコの書簡などをあわせてご紹介し、晩年のロスコ芸術の真髄に迫ります。
■会場・会期
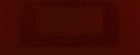 マーク・ロスコ 《壁画セクション7》 1959年 テート
c1998 by Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko
マーク・ロスコ 《壁画セクション7》 1959年 テート
c1998 by Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko- 川村記念美術館[DIC株式会社]
- 千葉県佐倉市坂戸631番地
- 電話 0120-498-130 または 043-498-2131
- 2009年2月21日(土)―6月7日(日)
- 休館日 月曜日(ただし5/4は開館)、5/7(木)
- 李禹煥『余白の芸術』はこちら
- 李禹煥『時の震え』はこちら
- 『イリヤ・カバコフ自伝』(鴻英良訳)はこちら
- 『ジャコメッティ エクリ』(矢内原伊作・宇佐見英治・吉田加南子訳)はこちら
- 『ルドン 私自身に』(池辺一郎訳)はこちら
- ブラッサイ『語るピカソ』(飯島耕一・大岡信訳)はこちら
- 岡本太郎『リリカルな自画像』はこちら
- 岡本太郎『疾走する自画像』はこちら
- 酒井忠康『若林奮 犬になった彫刻家』はこちら
- 佐谷和彦『佐谷画廊の三〇年』はこちら
- 白倉敬彦『夢の漂流物(エパーヴ)』はこちら
- 『コレクション瀧口修造』はこちら
- 『飯島耕一 詩と散文』はこちら
